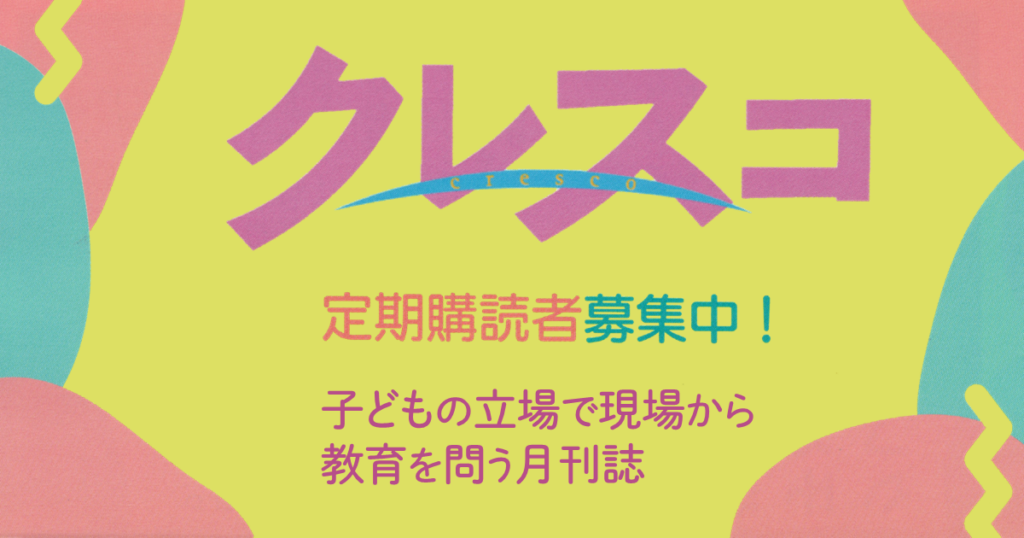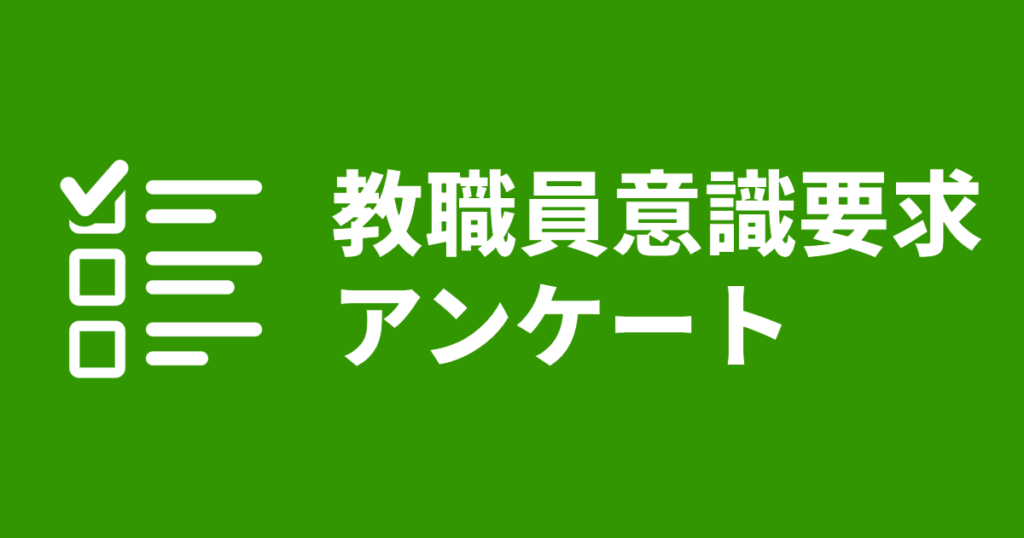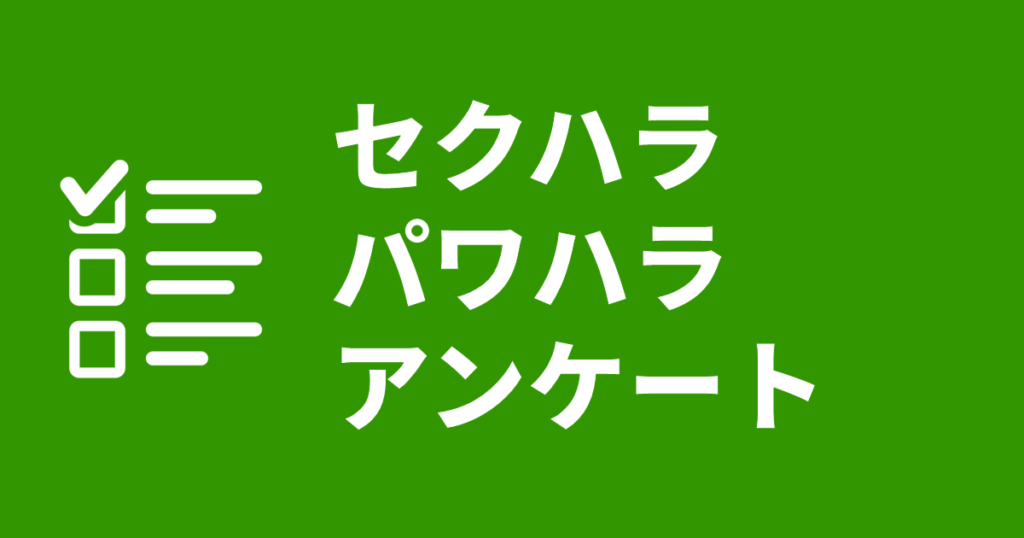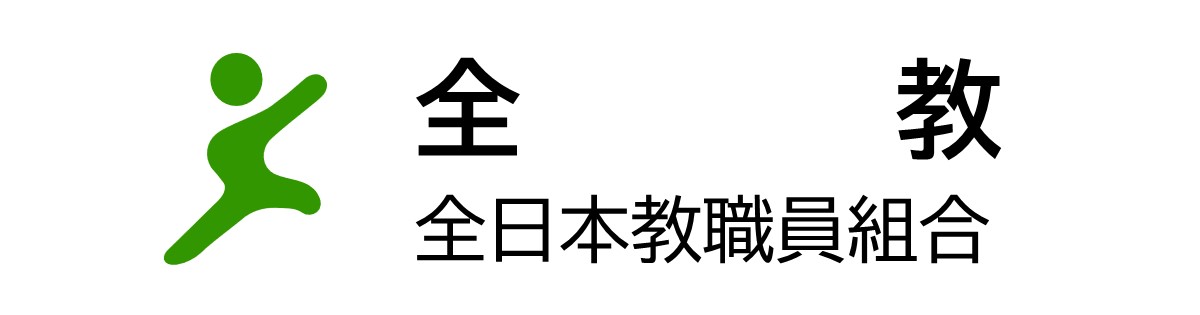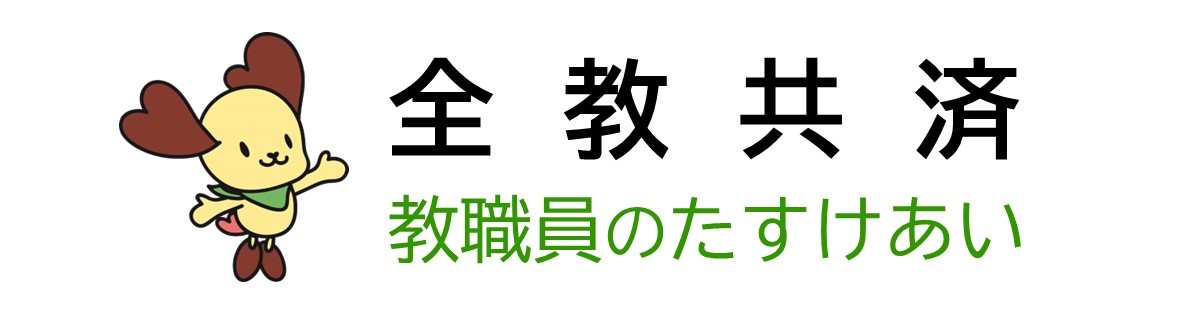全教(全日本教職員組合)・教組共闘会議は、2025年7月18日に「教育に穴があく(教職員未配置)」実態調査結果(2025年5月)を発表しました。
資料(PDFファイル)は全教(全日本教職員組合)のウェブサイトからダウンロードできます。

調査の目的
深刻となっている教職員未配置の実態を明らかにし、改善を求める。
調査方法
全日本教職員組合・教組共闘連絡会に参加する組織を通じ、各都道府県市区町村教育委員会に対して、教職員未配置の実態を明らかにすることを求めるとともに、調査用紙を組合員に配布する等して教職員未配置の実態を集約した。
(1)調査対象日
2025年5月1日
二次調査を2025年10月に予定
(2)調査項目
- 教職員未配置数
- 都道府県市区町村、学校種別、未配置数、未配置の職種・教科・担任の有無、校内対応等
調査への回答
36都道府県・ 12政令市から集約した。
教職員未配置数は小学校1478人(前年同期1736人)、中学校1184人(前年同期1247人)、高等学校418人(前年同期433人)、小中一貫校・義務教育学校・中等教育学校10人(前年同期7人)、特別支援学校514人(前年同期480人)、校種不明58人(前年同期148人)、合計3662人(前年同期4051人)となった。
36都道府県12政令市だけでも3600人超の未配置
※表中の「小中一貫校等」には義務教育学校・中等教育学校を含みます。
(1)未配置の状況
①校種別の欠員の内訳
| 校種 | 定員① | 中途退職② | 代替者③ | 不明④ | 加配⑤ | 短時間勤務・時間講師⑥ | 教員以外⑦ | 教職員の欠員合計(①から⑦合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 300 | 6 | 510 | 399 | 93 | 166 | 4 | 1478 |
| 中学校 | 216 | 1 | 267 | 299 | 56 | 344 | 1 | 1184 |
| 小中一貫校等 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| 高等学校 | 160 | 6 | 89 | 101 | 6 | 49 | 7 | 418 |
| 特別支援学校 | 94 | 7 | 189 | 167 | 0 | 51 | 6 | 514 |
| 不明 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 校種合計 | 771 | 20 | 1058 | 1024 | 160 | 611 | 18 | 3662 |
| 校種 | 産育休 | 病休 | 看休 | その他・不明 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 235 | 127 | 5 | 143 | 510 |
| 中学校 | 127 | 69 | 2 | 69 | 267 |
| 小中一貫校等 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 高等学校 | 36 | 31 | 0 | 23 | 89 |
| 特別支援学校 | 101 | 51 | 1 | 36 | 189 |
| 不明 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 校種合計 | 499 | 279 | 8 | 272 | 1058 |
- 「未配置なし」との回答が1政令市
②未配置に対する対応
- 見つからない
-
人的措置なし、校内の教職員でやり繰り、少人数授業取りやめなど
- 非常勤等で対応
-
授業の「穴」のみ埋めるが、校務分掌など他の業務は埋まらない
(2)教職員未配置の特徴
- 「定数の欠員」が771人と、全体の約21%になっている。
- 5月1日時点で既に20人の途中退職者による未配置が報告されている。
- 「代替者の欠員」が、「産育休」「病休」「看護休」「他、不明」を合わせて1059人と、全体の約29%で、「定数の欠員」を上回った。
- 未配置に対する対応として、「見つからないまま」が64.4%で最も多い。「非常勤等で対応」が昨年度の72.7%から大きく減らして31.6%になっている。また、昨年度同時期には見られなかった兼務が3.4%報告されている。
- 事務職員や部活動指導員、特別支援学校の調理員、介助員等の「教員以外」の職員についても欠員が報告されている。学校現場全体の人手不足が起きている。
(3)教職員未配置の実態(記述欄より抜粋)
授業や子どもたちへの影響
- 担任不在のクラスは既に崩壊していた。(小学校)
- 家庭科の授業が一カ月なし。やっと見つけた方が時間講師のため回復のコマが増やせない。(小学校)
- 保健体育の病休代替が見つからない。体育の授業は他教科の先生がしてくれている。保健は課題になることが多い。教頭が代替の方を探している(高等学校)
- 現在、免許外の教師が3人で対応しています。昨年は私自身、社会科教師ですが2年生の理科を持たされました。教師生活35年目にして初めての教科で、戸惑い、不安な毎日を送っていました。実験はもちろんできず、ただ単に教科書をなぞるだけの授業だけしかできず、生徒達に十分な学力をつけることができませんでした。(中学校)
- 日によって教師が入れ替わるため子どもが落ち着かない。(特別支援学校)
- 家庭科の代替が見つからず、非常勤3人で数時間ずつ担当。実習には他教科の教員が手伝いで入っている(手伝いで入る教員は、自分の授業に上乗せでボランティア)(義務制)
- 家庭科の育休・病休代替がみつからず、座学のみ(実習は動画を視聴でやったことに・・・?)(高等学校)
- 講師がみつかるまでは、自習プリントで対応することが多く、生徒の学びの要求に十分こたえられない実態がある。(高等学校)
- 教頭と教務も他の学校に比べて多く授業をもっている。(小学校)
- 教務が家庭科専科や特別支援学級のTT、教頭が5年算数のTT に入っている。(小学校)
学校現場が敬遠されている
- 産育休2のうち、講師1名が4月1日から来るはずだったが、3月末に「やっぱり辞める」ということになり、2名未配置でスタート。(小学校)
- 初任研補充講師が4月30日で突然の退職。非常勤も補充されていない状況。教科が中心となり対応している。とりあえず、非常勤講師を探していく(高等学校)
- 学校(管理職)としては求人を出したり、ご退職なさった先生方に連絡を取ったりして動いているようです。ただ、目処が一向に立たないようですので、望み薄といった感じです(特別支援学校)
影響を受けやすい特別支援学級
- 普通学級優先になっていて、支援は後回し。このまま今年度は経過しそうな雰囲気。(中学校)
- 特別支援学級の加配が来なくて、1人で対応。5月になって、非常勤の人が来て、他の非常勤の人と午前午後交代で入っている。(小学校)
- 特別支援学級2名足りないが、1日4時間勤務の人を入れたので、未配置数は1名になっている。足りない分は、特別支援学級の先生たちで何とかしている。(小学校)
対応する教員に負担増、悲痛な声
- 本来は、教員2 人+実習教員がいるべきチームで行う授業を、全盲の先生が一人で対応している。(特別支援学校)
- 毎年、常勤枠が見つからず、非常勤にバラして運用、これが当たり前のようになっていて、65~74歳のベテラン非常勤に頼っている。授業さえうまくまわればOK といった雰囲気もある。(高等学校)
- 前年度も機械科の常勤を見つけることができなくて、欠員のまま一年過ごした。今年も同じく見つけることができなくて欠員となり、県が専任として配置しないことに怒りを感じているが、あきらめムードもある。(高等学校)
- 年度途中復帰予定の育休代替などは、非常勤で授業のみ対応で済ませ、校長は常勤を探す気もない(高等学校)
- 地理の教員が病休だが、代替者がみつからないため、新しく着任してきた世界史の教員が地理の授業も行っている。教材研究の時間が2倍必要になり、しかもこれまで担当したことのない科目のため、毎日夜中の2時過ぎまで授業準備をしている。周囲の教員も「そのうち倒れるのでは」と心配している(高等学校)
- 兼務に出ている先生からは、移動が大変。学校にいないことも多いのに、生徒指導主任や部活動の主顧問を任されて大変という声。一方、担任を持ちたいのに、兼務のために持てないという実態も。
- 兼務の場合の移動時間も時数に含めるようにしたというのが、昨年度の申入れでの県教委の回答にあった。少しでも働きやすくということかもしれないが、その状況の中で孤独を極めて辞職した若い教員がいた(中学校)
- 給食員が配置できないことにより、(現在6人配置のところに3人しか配置されていない)食数に限界があり、職員は給食が食べられないことが常態化し、現在配置されている給食員の出勤状況によっては、子どもたちにも給食を提供できなくなることがある。もうこういう状態が3~4年続いている。(特別支援学校)
昨年度同時期の同回答との比較で未配置はほぼ同水準、依然として年度当初から多くの未配置がある、極めて深刻な状況
昨年度同時期の調査にも回答のあった都道府県、政令市の内、今回の調査にも回答のあった33都道府県9政令市のみを抜き出して、比較を行った。
(1)今回調査結果(33都道府県9政令市を抜粋)
| 校種 | 定員① | 中途退職② | 代替者③ | 不明④ | 加配⑤ | 短時間勤務・時間講師⑥ | 教員以外⑦ | 教職員の欠員合計(①から⑦合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 194 | 6 | 365 | 375 | 12 | 160 | 3 | 1115 |
| 中学校 | 167 | 1 | 220 | 267 | 4 | 341 | 1 | 1001 |
| 小中一貫校等 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 高等学校 | 152 | 5 | 81 | 91 | 6 | 48 | 7 | 390 |
| 特別支援学校 | 91 | 7 | 180 | 166 | 0 | 51 | 6 | 501 |
| 不明 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 校種合計 | 605 | 19 | 847 | 957 | 22 | 600 | 17 | 3067 |
| 校種 | 産育休 | 病休 | 看休 | その他・不明 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 138 | 94 | 5 | 128 | 365 |
| 中学校 | 100 | 55 | 2 | 63 | 220 |
| 小中一貫校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高等学校 | 33 | 27 | 0 | 21 | 81 |
| 特別支援学校 | 95 | 49 | 1 | 35 | 180 |
| 校種不明 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 校種合計 | 366 | 225 | 8 | 247 | 847 |
(2)2024年度5月分結果(33都道府県9政令市を抜粋)
| 校種 | 定員 ① | 中途退職② | 代替者③ | 不明④ | 加配⑤ | 短時間勤務・時間講師⑥ | 教員以外⑦ | 教職員の欠員合計(①から⑦合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 345 | 3 | 478 | 450 | 16 | 160 | 4 | 1456 |
| 中学校 | 141 | 3 | 195 | 203 | 2 | 351 | 3 | 898 |
| 小中一貫校等 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 高等学校 | 183 | 4 | 97 | 84 | 0 | 29 | 0 | 397 |
| 特別支援学校 | 104 | 1 | 139 | 214 | 1 | 10 | 7 | 476 |
| 校種不明 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 25 |
| 校種合計 | 777 | 11 | 912 | 962 | 33 | 550 | 14 | 3259 |
| 校種 | 産育休 | 病休 | 看休 | その他・不明 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 222 | 145 | 2 | 109 | 478 |
| 中学校 | 99 | 50 | 1 | 45 | 195 |
| 小中一貫校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 高等学校 | 34 | 26 | 0 | 37 | 97 |
| 特別支援学校 | 57 | 48 | 6 | 28 | 139 |
| 校種不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校種合計 | 415 | 269 | 9 | 219 | 912 |
(3)未配置に対する対応の比較(33都道府県9政令市を抜粋)
(4)比較の結果
わずか1 か月での退職による未配置が昨年度の1.73 倍に
- 昨年度のほぼ横ばいの規模で依然として多くの教職員未配置が起きている。小学校は前年比の約0.77倍と、各自治体での対応の成果が見られるが、高校では約0.98倍と横ばいであり、中学校は約1.12倍、特別支援学校で約1.05倍と増加している。未配置全体に占める割合は、小学校が前年度の約45.7%から約36.4%へと減らした一方、中学校が約27.6%から約32.6%と明らかに増えている。
- 5 月1 日時点での途中退職者による未配置が約1.73 倍に増えている。
- 未配置が起きた時の対応として、非常勤等での対応が前年の71.2%から31.6%、約0.44倍と割合を大きく減らしている。その分、「見つからないまま」が昨年比の28.2%から64.4%へ、2.28倍と大幅に増えており、早くも現場の人手不足が見られ、年度の後半に向けて深刻な実態が懸念される。また、前年度には報告のなかった兼務での対応が、既に38件、3.4%も寄せられている。
- 短時間勤務や時間講師などの非常勤教職員の未配置が、前年度比約1.09倍と増え続けている。小学校、中学校ではほぼ横ばいの中、高校で約1.66倍、特別支援学校では5.1倍にも増えている。未配置全体に占める割合が昨年度の約16.9%から、約19.6%へ増えた。
- 前年同時期と比べて、未配置の総数が増えた自治体は20、総数が減った自治体は22 になる。校種別では、小学校で未配置人数が増えた自治体が11 に対し、減った自治体は19。中学校で未配置人数が増えた自治体は16、減った自治体は9。高校で未配置人数が増えた自治体は13、減った自治体は14。特別支援学校で未配置人数が増えた自治体は13、減った自治体は16。
- この調査結果とは別に、臨時免許発行により未配置を埋めているケースがあるとされているため、実態はさらに深刻と言わざるを得ない。
調査結果のまとめ
今年度の調査結果
- 全教・教組共闘連絡会の調査で、36都道府県12政令市で3662人の教職員未配置(教員未配置は3644人)が起きており、依然として改善されず、さらに深刻な実態が明らかになった。
- 代替者の未配置合計が5月1日時点でも1058人確認されている。年度途中から休職に入る教職員の替わりが既にいない状況であり、教職員未配置がさらに増加していくことが懸念される。
- 教職員未配置への対応として、人員が配置されず、校内での対応を余儀なくされているケースが最も多い対応として確認された。教職員を探しつつ、限られた人員で何とかせざるを得ず、管理職が学級担任を持つなど報告がある。また、少人数指導の教員を学級担任に充て、やむなく少人数指導や少人数学級を見送る等の実態があり、子どもたちの学習権に深刻な影響を及ぼしている。また、非常勤等で授業の「穴」のみを埋めるケースも次いで多く報告されている。しかし、非常勤等では授業の「穴」を埋めることができても、非常勤の業務外である校務分掌をはじめとした授業以外の業務負担は、残っている教職員が負うしかなく、長時間過密労働に拍車をかけている。
- 教職員未配置の解消のため、臨時的任用教員や非常勤講師を探すが、5月時点で「今年度は未配置のまま行く」と見つかる見込みが無くあきらめている場合もある。多くの学校では、教職員が見つからず、未配置のまま教育活動を学校全体で負担しているのが実態であり、教職員の多忙化を深刻化させている。
昨年度との比較から
- 昨年度同時期にも回答のあった33都道府県9政令市で比較したところ、未配置は全体で0.94倍と、ほぼ横ばいで、引き続き多くの未配置があることがわかった。
- 中学校での未配置総数が約1.12倍で、校種別に見ても中学校の未配置が拡大している自治体の方が多い。中学校35 人学級が実際に実現されるかどうか、深刻な状態である。
- 未配置に対しての対応として、見つからないまま校内での対応を余儀なくされているケースが最も多い。非常勤等の人手は5月1日時点で既に確保することが困難になっていると推測される。それらが予測されていたからか、前年度には見られなかった兼務での対応が報告されている。これも深刻な人手不足の表れと言える。非常勤等での対応、件数としては約3 倍報告されている。授業の「穴」だけでも埋めようとする現場の様子が浮き彫りになっている。正規や常勤講師で未配置を埋めることができず、非常勤講師の取り合いが起きている。
- 前回調査と比較しても、学校現場の実情は依然として深刻であり、子どもたちの学習の保障や、教職員の健康が懸念される。
「教育に穴があく(教職員未配置)」の改善・解決のために
改定給特法等では解決されない深刻な実態
教職員未配置は国が正規教員を抜本的に増員するための「定数改善計画」を策定してこなかったこと、人件費抑制のための「定数崩し」や「総額裁量制」によって、正規で配置すべき教職員が臨時的任用教員や非常勤講師に置き換えられ続けた結果、引き起こされている問題である。
教員採用試験は、ついに小学校で1 倍を切る自治体が複数出るなど、募集倍率低迷が一層深刻化している。これは、募集段階で示されていた給特法等改定案の「処遇改善」策が、募集増につながっていないことの表れと考える。採用倍率回復策としての採用試験前倒しは、教職志望者が減り続けている中での牌の奪い合いに過ぎず、大量の辞退者を出すなど効果は見込めない。それどころか、採用する自治体側は見通しが立てづらい状態になっている。
特別免許状の授与は、教員免許状における専門性との矛盾を孕んでいる。臨時免許状は「普通免許状を有する者を採用できない場合に限り、例外的に授与する」ものであるにも関わらず、年間1万件前後の授与を行わざるを得ない状態にある。免許外教科担任制度は、担当する教職員に過重な負担を強いている。
求められているのは「主務教諭」の設置ではない
改定給特法等により、新たな職として「主務教諭」を置くことができる、とされた。主務教諭は「児童等の教育をつかさどるとともに、学校の教育活動に関し教職員間の総合的な調整を行う」とされている。しかし、モデルとされる「主任教諭」を設置している東京都は、2022度に全教の行った勤務実態調査で、月の時間外労働が114時間と、全国平均を18時間も上回っている。さらに、2024年度に新規採用された教員の内、5.7%も1年以内に離職している。新たな職を置くことが労働環境改善に資する根拠はどこにもない。必要なのは新たな職ではなく、教職員増である。
現場の声を真摯に聞く姿勢を
早急に抜本的な改善策を講じなければならないことは明白であり、義務・高校標準法改定による基礎定数からの抜本的な教職員定数改善を行うことをはじめ、学校現場で働いている各種スタッフの正規化など、働き続けられる環境整備が必要である。
学校現場で常態化している過労死ラインを超える長時間過密労働、教育の自由を奪う管理・統制の強化、ハラスメントの増加等によって、教職員の早期離職があることや教員志望者が減少していることも背景にある。教職員不足による教職員の働き方は限界を超えており、子どもたちへの影響も深刻である。直ちに改善・解消が求められる。
教職員を増やし、少人数学級化を図ることで、学級事務や校務分掌など1 人あたりの業務量を削減することこそ行うべきである。教職員が心身や時間的に余裕を持って、子どもたちとかかわり、授業や学校行事、自主的研修など行えるよう、国が責任をもって教育予算を増額して、教育条件整備を行う必要がある。
教育を取り巻く諸問題解決に向けた全教提言「このままでは学校がもたない!子どもたちの成長が保障され、せんせいがいきいきと働くことができる学校をつくる」(全教7つの提言)、及びILO/ユネスコ教員の地位勧告適用合同専門家委員会(CEART)の第15期最終報告書(2025年2月)も踏まえ、「教育に穴があく(教職員未配置)」問題を改善・解消するよう以下求める。
すぐにできる職場環境改善を行い、教職員の負担を減らすこと。
- すべての都道府県・政令市・市区町村に組合代表も含めた総括衛生委員会を、すべての職場に衛生委員会等を確立し、実効ある取り組みをすすめること。(提言5)
- 教育の専門職としてふさわしい適正な賃金水準を確保すること。(提言4)
- 各学校において行われる各種取り組みについて、教職員が納得して行えるよう、トップダウン型の学校運営から、民主的な学校運営へ切り替えること。(提言7)
- 教員1人あたりの持ち授業時数を軽減すること。そのために授業時数の点検を行い、「余剰時数1」が過剰になっている場合は速やかに2・3学期の授業時数を減らすこと。来年度の教育課程編成においても過剰な「余剰時数」の確保を行わないことを徹底すること。また、各校で取り組めるよう各教育委員会は励行、尊重すること。(提言1)
- 管理職や同僚間のあらゆるハラスメントの根絶を行うこと。各教育委員会は現場に負担を求めることなく実効ある対応をするために、ハラスメント窓口への相談内容の匿名性の確保や、ハラスメント根絶に向けて徹底的な対応を行うこと。教職員組合に寄せられたハラスメント相談に対して、解決に向けて協力して取り組むこと。
- 観点別評価を機械的に押し付けず、「通知表」の簡素化や面談への置き換えなどの取り組みについて、必要に応じて各校で行うこと。また、各校での取り組みや判断を各教育委員会は尊重すること。
- 国・教育委員会による学校現場への調査や報告書等のさらなる削減・簡素化を行うこと。
- 官制研修や年次研修を見直し、教職員の負担軽減を行うこと。
- 教員採用試験において、常勤講師などで現に学校現場で働いている教職員の負担を軽減すること。
- 病気休職者を増やさないために、人事異動については機械的でなく、本人の希望を尊重すること。
- 病気休職者の復帰に当たっては、現任校に限らず、異動しての復帰をひろく認めること。
- 文部科学省は教職員の欠員に関する調査を毎年行い、その結果を公表すること。その際、2022年1月に公表した『「教師不足」に関する実態調査』で除かれた養護教諭や栄養教諭等、事務職員等、学校現場で働いている全ての職種を対象にすること。また、非常勤講師、再任用教員(短時間)をフルタイム勤務に対する勤務時間数に応じた人数(換算数)として計算しないこと。調査結果をもとに適切な教職員数が配置できるような予算要求を行うこと。
中・長期的に、教職員不足を解消し、また「20人以下学級」を展望した少人数学級の段階的実現に向けて教職員を確保すること。そのための予算確保と職場環境改善、待遇改善を図ること。
- 教育予算の対GDP比をOECD諸国平均並みに引き上げること。
- 教職員にも残業代を支給し、見合った給与を支払うとともに、必要な人数の教職員を配置すること。(提言4)
- 義務・高校標準法改正による抜本的な定数改善を行うこと。(提言1)
- 「定数くずし2」「総額裁量制」を見直すとともに、義務教育費国庫負担金を 2 分の 1 に戻すこと。(提言1)
- 管理的・競争的な教育施策を見直すこと。(提言3)
- 全国学力・学習状況調査の悉皆調査を中止すること。(提言3)
- 教職員評価制度見直すこと。(提言3)
- 学習指導要領を見直し、過大・過密な内容を改めるとともに、学校現場に押し付けないこと。(提言3)
- 教員が受け持つ授業時間(コマ数)の上限を定めること。(提言1)
- 定年延長に係り、高齢期雇用者の処遇を抜本的に改善すること。
- 臨時的任用教員、非常勤講師等の処遇を抜本的に改善すること。
- 学校にかかわるスタッフを正規化、処遇を抜本的に改善すること。
- 教員がより多くの時間を教育に関する活動に充てられるように、十分な学校職員数を確保するための措置を講じること。(CEART 第15 期最終報告書 164(e))
- 教育政策を議論、決定する場に、全教・教組共闘連絡会をはじめとする複数の教職員組合を参加させ、現場の声を反映させる仕組みへ変えること。(CEART 第15 期最終報告書 164(f))
- 余剰時数
-
各教科で定められている「標準授業時数」が、休校や学級閉鎖などの措置が取られても下回らないように、多めに確保された授業時数のこと。
- 定数くずし
-
2001年の義務標準法改正で、正規教員の代わりに短時間勤務の非常勤教員に置くことができるとしたことによる、教職員の非正規化が進んだ要因のこと。