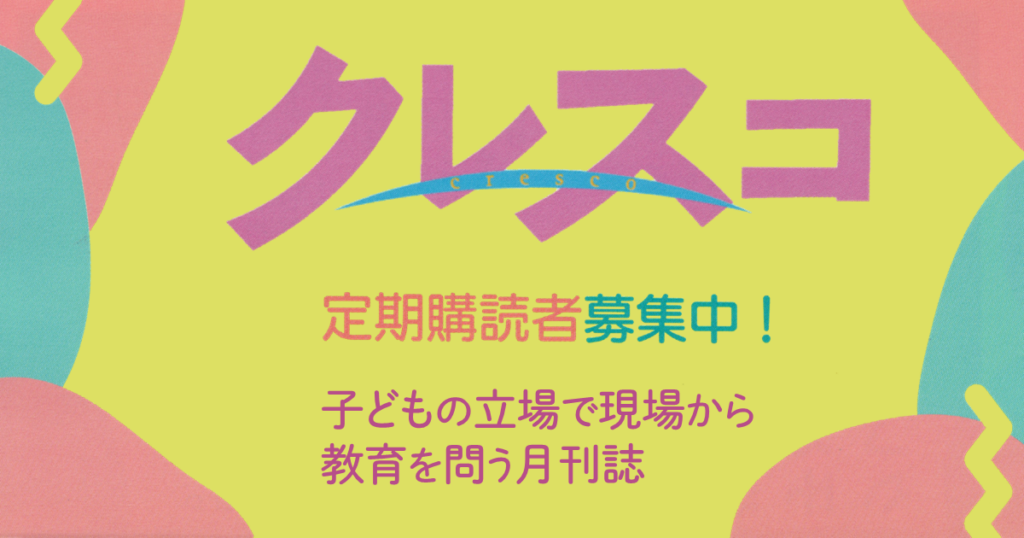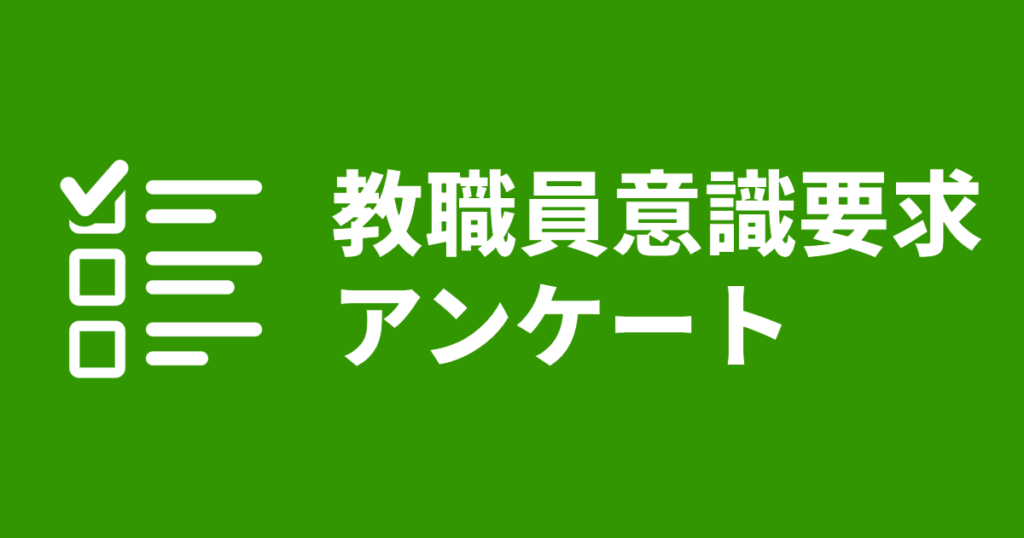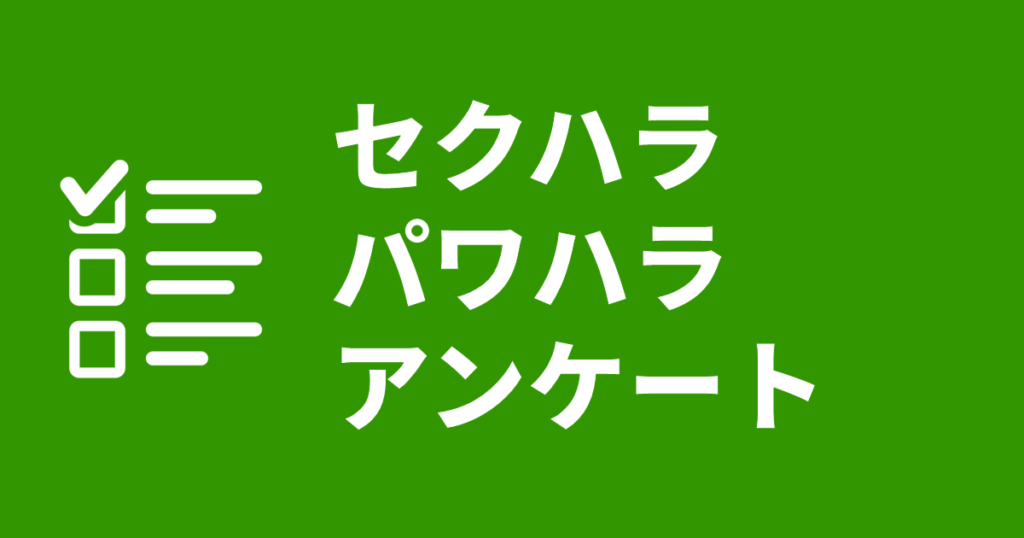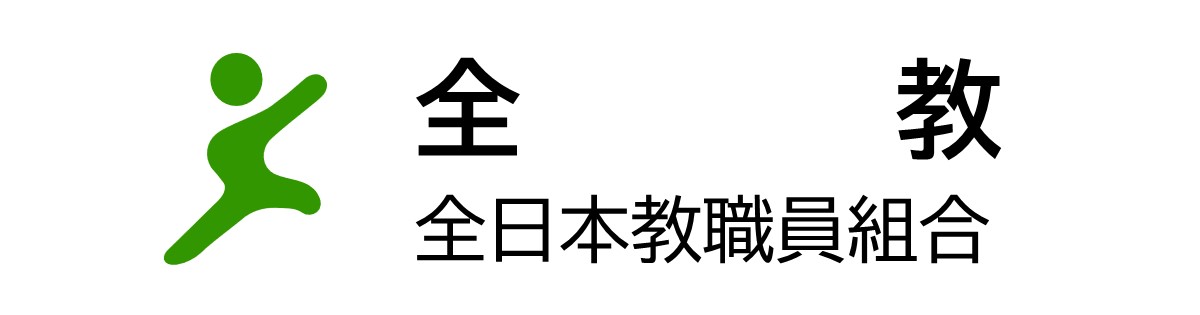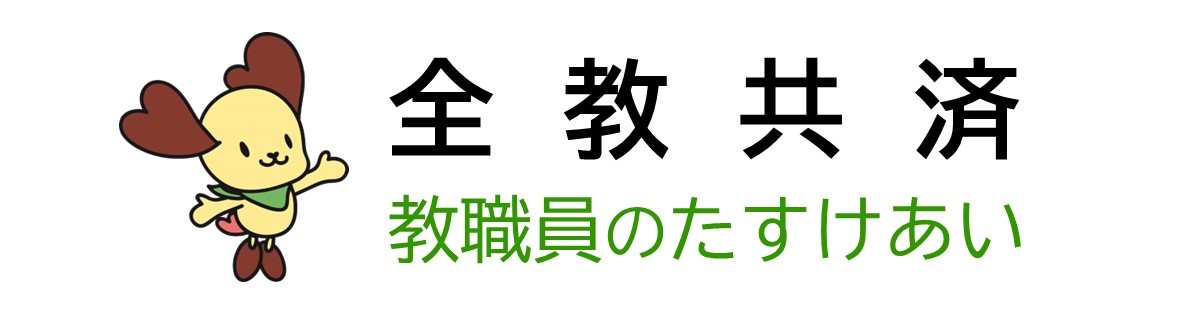全教(全日本教職員組合)は、5月28日、書記長談話『学問の自由を侵すことは断じて許さない 日本学術会議法改悪に抗議し、撤回を求める』を発表しました。
5月13日、新しい「日本学術会議法案」が衆議院本会議において、自民、公明、日本維新の会などの賛成多数で強行可決されました。学術会議を特殊法人化し、会員以外で構成される「(会員)選定助言委員会」「運営助言委員会」を設置し、さらに首相が任命する「監事」や内閣府設置の「評価委員会」が活動の点検をするということです。新しい「日本学術会議」は、組織的にも財政的にも政府の管理が強まり、学術会議の独立性・自主性が失われます。
問題の発端は2020年10月の菅政権による6人の候補に対する任命拒否です。その経緯はいまだ明らかにされていません。政府および自民党は学術会議のあり方に問題をすり替え、自民党は「政策決定におけるアカデミアの役割に関する検討プロジェクトチーム」を立ち上げ、2020年12月に「日本学術会議の改革に向けた提言」を発しています。そこには「『政策のための科学』の機能を十分に果たしているとは言い難い」と書かれています。学術会議の独立性を否定し、政治や経済に奉仕させる方向性をはっきりと示しています。
日本学術会議は、学問や科学が政治権力によって制約を受け、利用された反省を踏まえ、1949年に設立されました。日本学術会議法 は「科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される」と述べています。そして独立機関として政府の学術政策について提言や勧告をしてきました。また、1950年に「戦争を目的とする科学の研究は絶対にこれを行わない決意の表明(声明)」、1967年には「軍事目的のための科学研究を行わない声明 」を発出しています。そして2017年の「声明 」では当時の安倍政権による軍産学共同をすすめようとする動きを批判しました。そこには「科学者コミュニティが追求すべきは、何よりも学術の健全な発展であり、それを通じて社会からの負託に応えることである」という理念が貫かれています。
「国を代表する科学者組織」であるためには、国家財政による安定した財政基盤が必要です。しかし、新しい日本学術会議法案は、法人化を口実に学術会議への国庫負担を、「予算の範囲内において…補助することができる」にとどめています。民間からの寄付への依存が高まり、企業の利益に資する研究偏重のおそれがあります。そして、「学問の軍事利用」につながるこの法案は、到底許されるものではありません。
全教は、戦前・戦中の教育への痛切な反省をふまえ「教え子を再び戦場に送るな」の決意を心に刻む教職員として、この新しい「日本学術会議法案」を見過ごすことはできません。学問の自由は教育基本法や「ILO/ユネスコの教員の地位に関する勧告」にも位置づけている通り、教職員がその専門性を発揮し、教育活動を進めることと不可分です。学問の自由の侵害は真理・真実を追求する教育をゆがめ、教育を受ける権利をも揺るがすものです。
全教は、新しい「日本学術会議法案」に対して強く抗議し、撤回を求めるとともに、多くの人々と力を合わせ、憲法をいかし、民主主義にもとづく政治の実現と、学問の自由と教育の自由の保障を求めてたたかいをすすめる決意です。