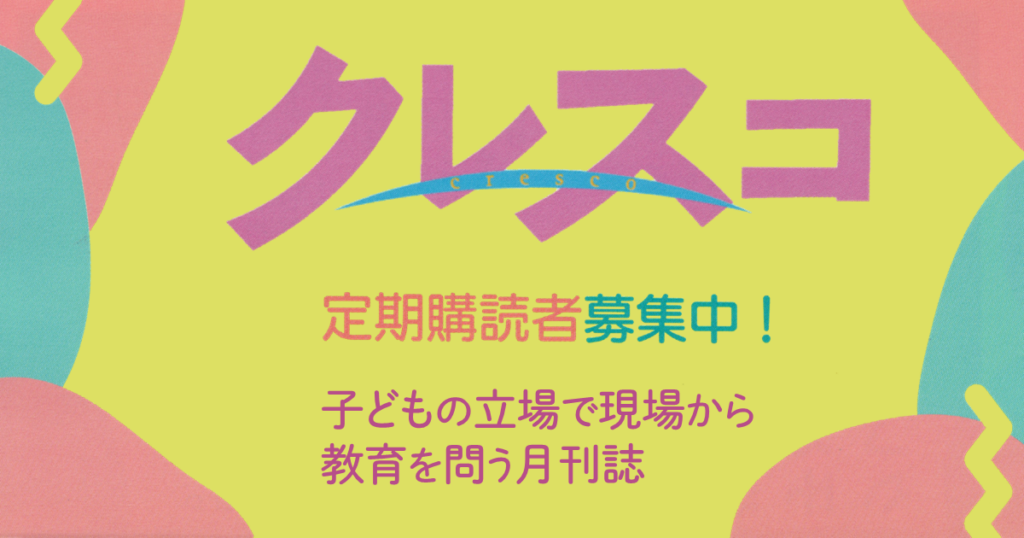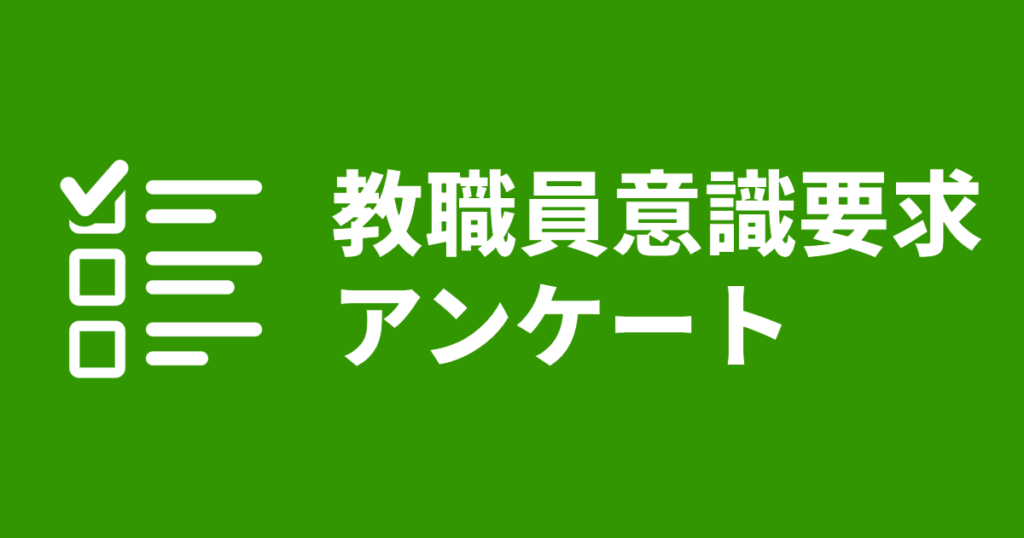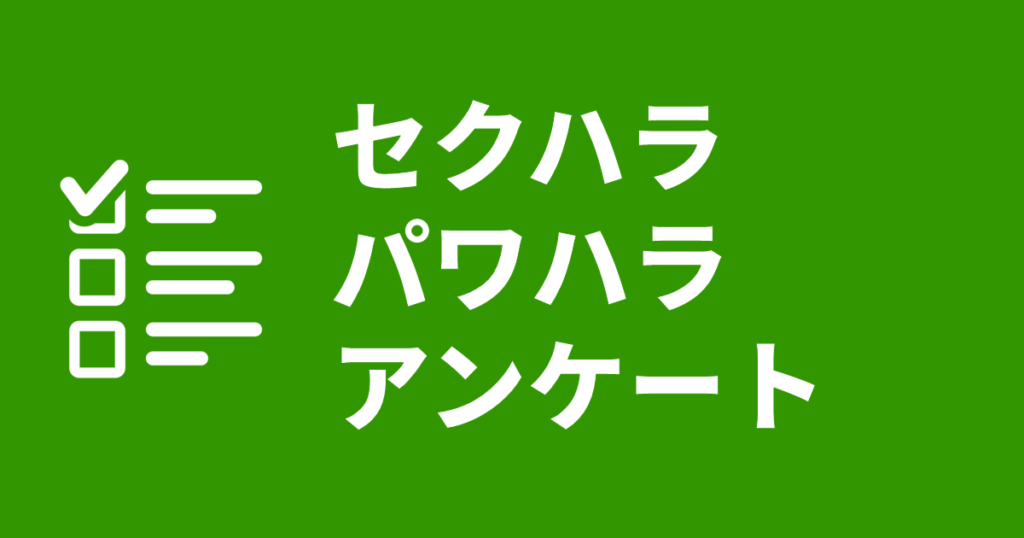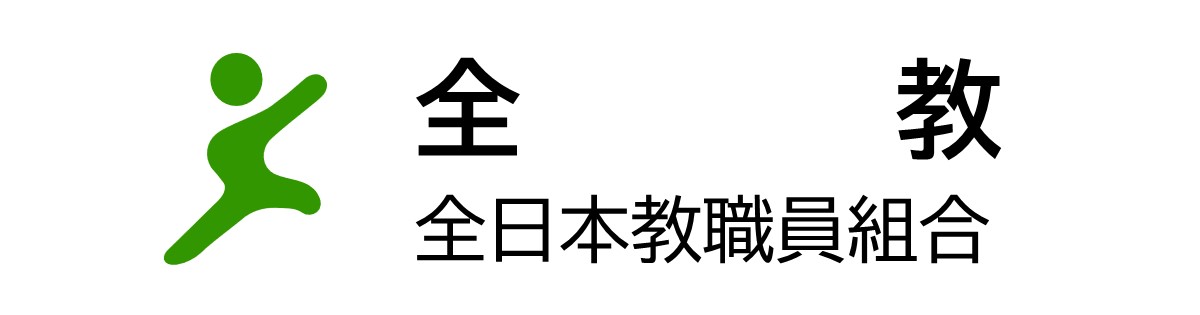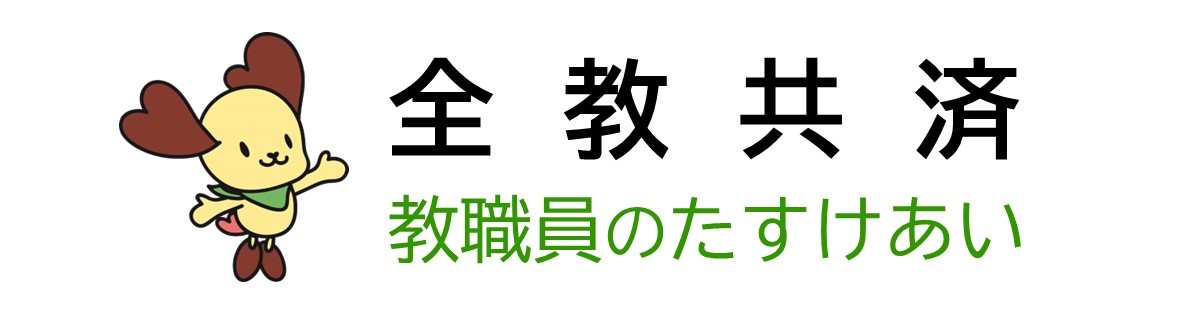全教(全日本教職員組合)は、9月26日、書記長談話『教育への政治的介入に反対し、防衛省が小学校へ配布した「まるわかり! 日本の防衛~はじめての防衛白書2024」の回収と、2025年版を学校へ送付しないことを求めます』を発表しました。
『まるわかり! 日本の防衛〜はじめての防衛白書』は2021年度から、その年の「防衛白書」を小学校高学年から中学生高校生向けに解説したものとして作成され、毎年防衛省ホームページに掲載されてきました。
ところが、今年6月に『まるわかり! 日本の防衛〜はじめての防衛白書2024』(以下、冊子)が小学校へ配布されている県があることが明らかになりました。2024年度に防衛省が文科省に学校への送付を申し入れた際、文科省が「送付の可否は都道府県教育委員会の判断」と回答し、防衛省が教育委員会に打診し了解のとれた数県に冊子を直接配布したことを確認しています。
2024年度版の冊子は、2022年12月に国会審議も経ないまま閣議決定された「安保3文書」を基盤とし、大転換された政府の防衛政策を一方的に主張し、偏った価値観を押し付けています。安保3文書の中には「我が国と郷土を愛する心を養う」 「安全保障教育の推進」などが明記されており、こうした方針の具体化と捉えられます。
この冊子は中国、北朝鮮、ロシアを「脅威」であるかのように強調し、「日本が位置する地域は安全とはいえません」、北朝鮮は「すでに日本を攻撃する能力を保有しています」と記述しています。これらの表現は、子どもたちに、特定の国に対する偏見や対立意識を抱かせるおそれがあり、多面的な国際理解の推進に逆行します。
また、「ウクライナは防衛力が足りなかったため攻められた」といった解説は、事実関係が不確かなまま軍備増強を正当化するものです。小学生には「抑止力」 「集団的自衛権」といった概念は理解が難しく、戦闘機などの装備の写真や攻撃の可能性を強調する内容を提示することは、発達段階に適さず、恐怖心や不安感を抱かせる懸念があります。
さらに問題なのは、防衛白書の配布方法です。冊子とともにアンケート用紙が送付された県があり、アンケートの「活用実績」や「今後の望ましい活用方法」を問う項目に、「総合的な学習の時間に使用」があり、授業等で使用することを促しています。これは学校で決めるべき教育課程への政治的介入にあたります。
同時に、日本国憲法第9条の平和主義の理念に反し、軍事力による「抑止力」や「反撃能力」の保持を当然視する方向へ誘導しかねません。憲法で強調されている「平和的手段による解決努力」はどこにも記載されておらず、教育の場でこうした価値観を無批判に子どもたちへ提示することには大きな問題があります。さらに、子どもの権利条約で示されている「平和と寛容の精神」を育てる教育などにも抵触する恐れがあります。
加えて、7月15日に発刊された『まるわかり日本の防衛2025』 2021年度版から記載されてきた「非核三原則」「専守防衛」「軍事大国にならないこと」の記述が削除されました。構成も大きく変更し、22ページから34ページに拡大して自衛隊の活動を詳しく紹介し、職業としての魅力や処遇の良さを強調しています。災害支援派遣での活躍を前面に出しつつ、実質的には自衛官勧誘やリクルートにつながる可能性もあり、義務教育段階の教育現場で、そのような情報を子どもたちに提供することは、きわめて問題があります。しかし、防衛省はこの2025年度版の冊子も「配布の在り方を検討していく」と述べています。
現在の学校は、外国にルーツを持つ子どもたちが多く在籍し共に学ぶことを大切にする教育がおこなわれているにもかかわらず、この冊子は差別や排除を助長し、共生社会を築く上での障壁ともなりかねません。
今こそ軍事的手段による「抑止」や「反撃」ではなく、対話や外交、国際協調などの平和的な手段で安全保障を考える力を育む教育こそが求められていると考えます。
全教は、引き続き、防衛省に「まるわかり日本の防衛」の学校配布計画の中止を求めてとりくみます。また、「教え子を再び戦場に送るな」のスローガンを掲げ、日本国憲法と子どもの権利条約に基づいた教育の実現のために奮闘していく決意です。