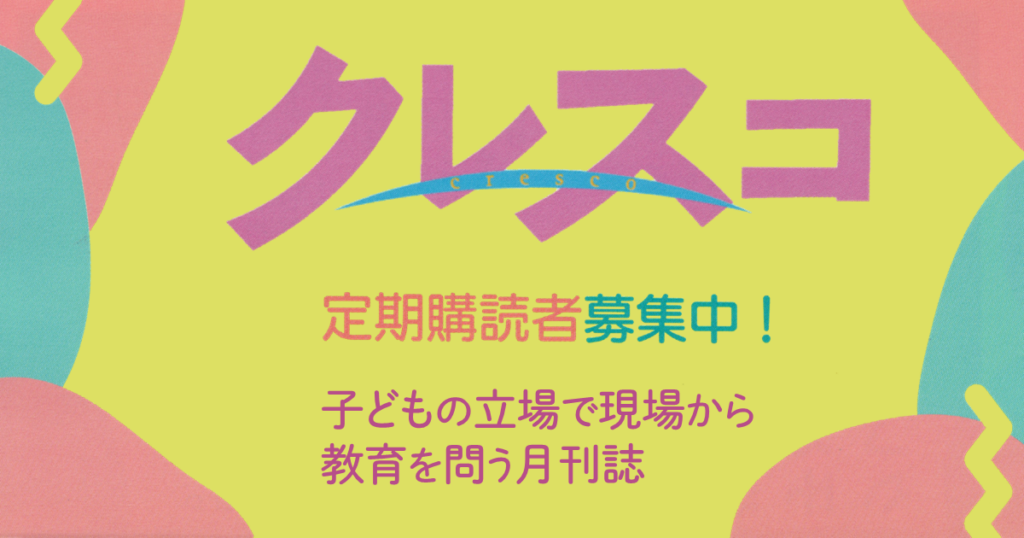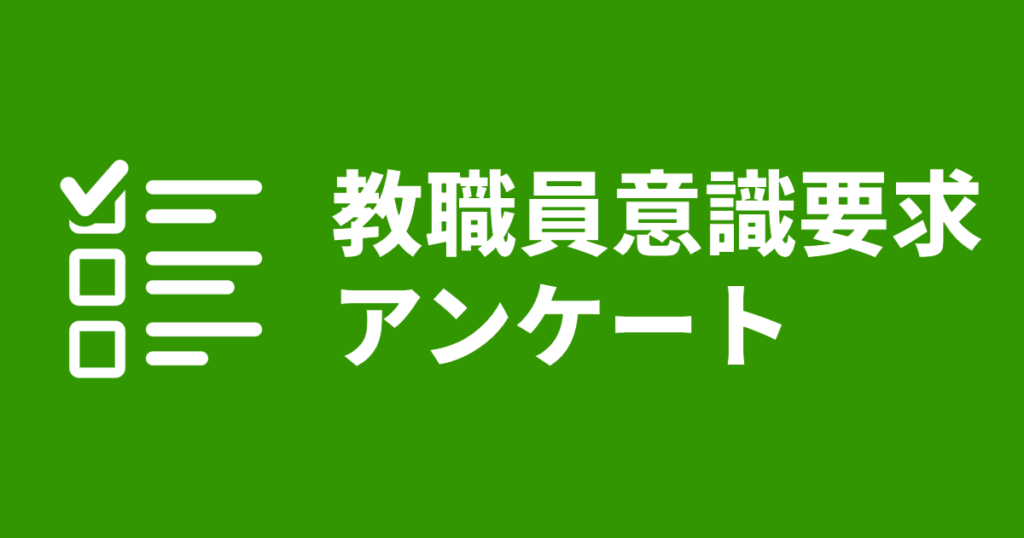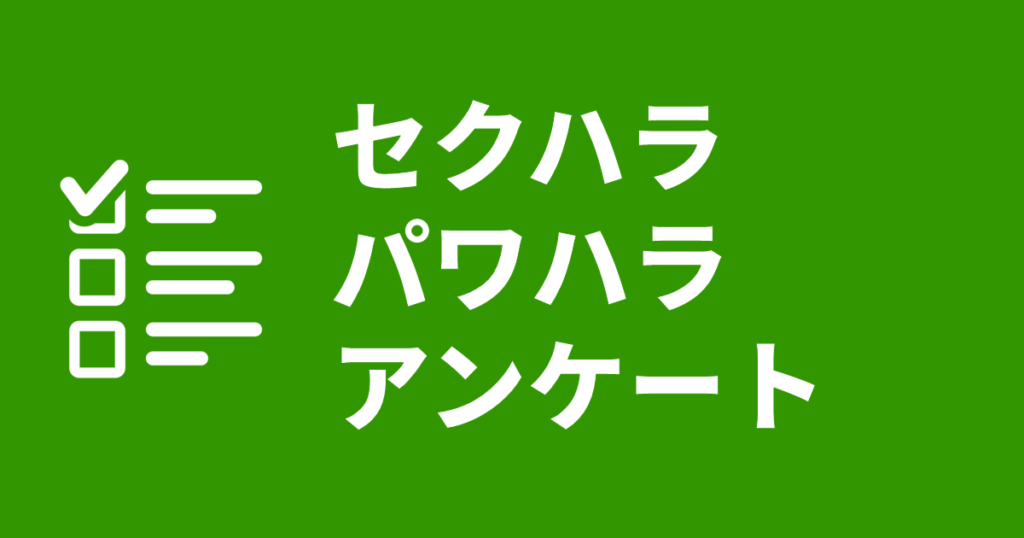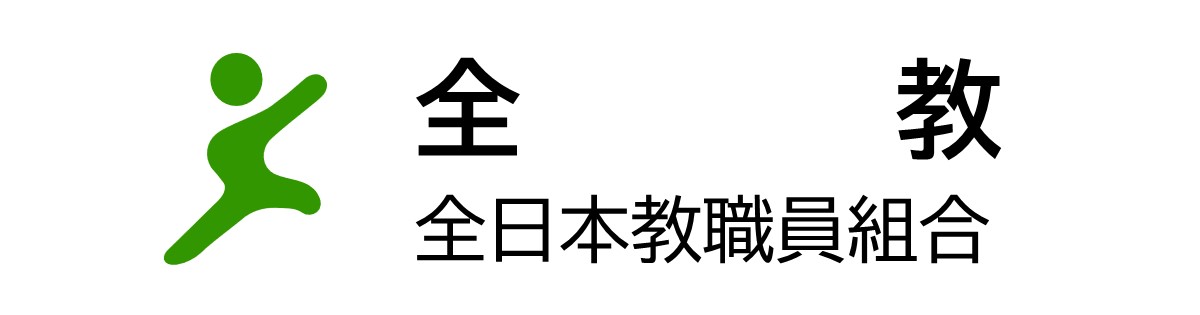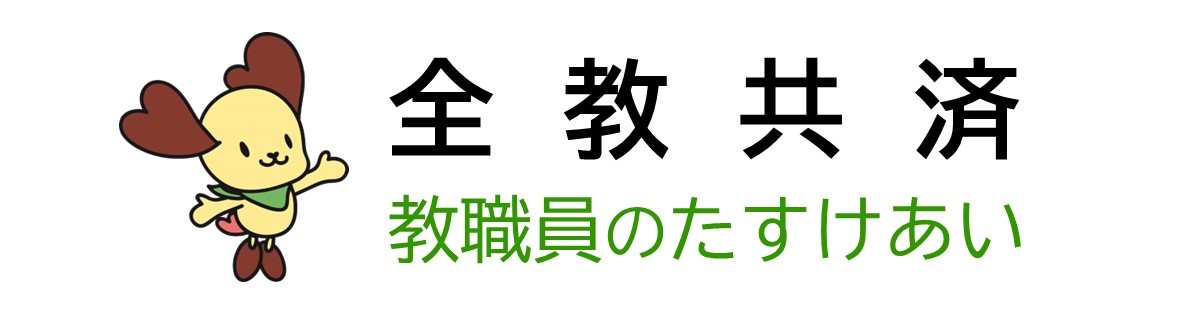全教(全日本教職員組合)は、9月3日、書記長談話『2026年度文部科学省概算要求について』を発表しました。
2026年度概算要求が8月29日に締め切られ、各省庁の概算要求総額は過去最高の122兆円に達することが明らかになりました。文部科学省概算要求は一般会計で6兆599億円、そのうち文教関係予算は4兆5083億円となっています。文教関係予算の内容は保護者、教職員、地域の願いである、教育無償化、抜本的な少人数学級化、教職員定数改善、「教職員未配置」の解消等には程遠い要求となっています。一方で、防衛予算の要求額は8兆8454億円で、文教関係予算の要求額の2倍近くになっています。
教職員定数は、今年度は「新たな『定数改善計画』」と称し、9214人の増員を打ち出しました。その中には「中学校における指導体制の充実(35人学級)」5800人が含まれ、中学校での35人学級に向けて来年度からの3年間で17400人を増員することが明らかになりました。少人数学級の前進は、大きく評価するところです。「いじめ・不登校対応等のための体制整備」1897人の中には「養護教諭の配置充実」として配置基準の見直しが明記され、実現すれば全校配置や複数配置基準の引き下げが前進します。私たちが長年求め続けているゆきとどいた教育の実現へ、義務標準法の改正を含めて確かな前進が見られます。給特法改定審議のたたかいにおいて抜本的な定数改善を粘り強く訴え、改定給特法の附則に書き込ませた、私たちのたたかいの成果です。「通級や日本語指導等のための基礎定数化」348人、「特例定員」3345人を加えると、12907人増となります。
しかし中学校の35人学級は段階的ではなく今すぐにでも全学年で行うべきであり、高校の少人数学級化、小学校も含めて20人学級を展望したさらなる少人数学級化が必要です。
「教師の処遇改善」では、教職調整額の引き上げや、主務教諭の創設などが明記されました。教職調整額の引き上げは、すべての教員の賃金改善となるものであり、重要です。しかし、「定額働かせ放題」と言われている今の働き方は変わらず、さらに悪化させるおそれがあります。実際に生じている時間外労働に対して残業代を支給できるしくみをつくり、長時間過密労働に法的な歯止めをかけることが必要です。主務教諭の創設は学校内の分断につながりかねません。階層化によって、向き合うべき子どもたちの実態よりも、自らへの評価を高めることを優先させる教職員を生み出す懸念があります。業務の複雑化や偏りなど、多忙化を助長することも懸念されます。また、特別支援教育に携わる教員の「給料の調整額」縮減は処遇の改悪であり、専門性の軽視です。
また、定数の12907人増、「処遇改善」で161億円増にも関わらず、義務国庫負担金は今年度比でわずか294億円増にとどまっています。今回は示されていない教職員定数の自然減のことも含め、実際はどの程度の定数増か、疑問と言わざるを得ません。
「高校生等への修学支援」は、要求額を示さない「事項要求」となりました。現在は年収910万円未満世帯の「高等学校等就学支援金」、910万円以上世帯の「高校生等臨時支援金」という制度に分かれていますが、私たちは、そもそも授業料を「不徴収」として真に無償化へ進むべきであると考えています。加えて、来年度からは私立高校生も対象として45.7万円が支給される見込みとされています。
しかし、今回の概算要求では何も示されていません。「令和8年度予算の編成過程において成案を得て、実現する」とあり、現段階においてもなお何も決まっていないことを、文科省自身が認めています。それは同時に、今後の政治情勢で白紙撤回される可能性も含んでおり、2012年に国際人権規約A規約(13条2項b、c)の留保を撤回し、高等教育までの無償化をすすめると世界に向けて宣言した日本においては、あってはならない後退です。防衛費の増額と違い、なぜ決断できないのでしょうか。同じく事項要求とされた「給食無償化」を含め、速やかな制度設計と確実な予算措置、さらなる充実を強く求めます。
また、「高等学校教育改革の実現」が新たに創設され、事項要求となりました。「公立高校などへの支援の拡充を含む教育の質の確保」を目的にしているとされています。しかし、その方向性として示されているのは「産業界等の伴走支援による専門高校の機能強化・高度化」「DX・AI等の人材育成」「グローバル人材の育成等」とされています。私たちは、教育を通じて人格の完成を目指すのであり、人材の育成を行っているのではありません。公立高校へ必要なのは少人数学級化、その実現のための予算増と高校標準法改正です。
全教は、「戦争する国づくり」のための軍拡予算を大幅に削減し、国の責任による35人以下学級早期実現、20人学級を展望した少人数学級のさらなる前進、正規・専任の教職員増、給付奨学金制度拡充、公私ともに学費無償化など、子どもの権利が保障され、子どもが安心して学べる教育予算への抜本的な転換を求め、全国の保護者・教職員・地域住民とともに、政府予算編成に向けて全力を上げ奮闘する決意です。