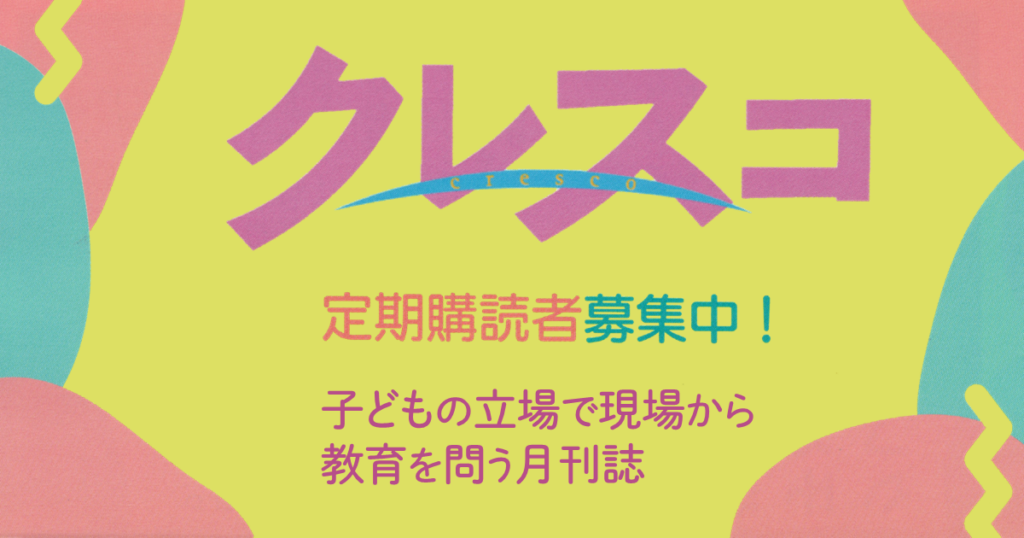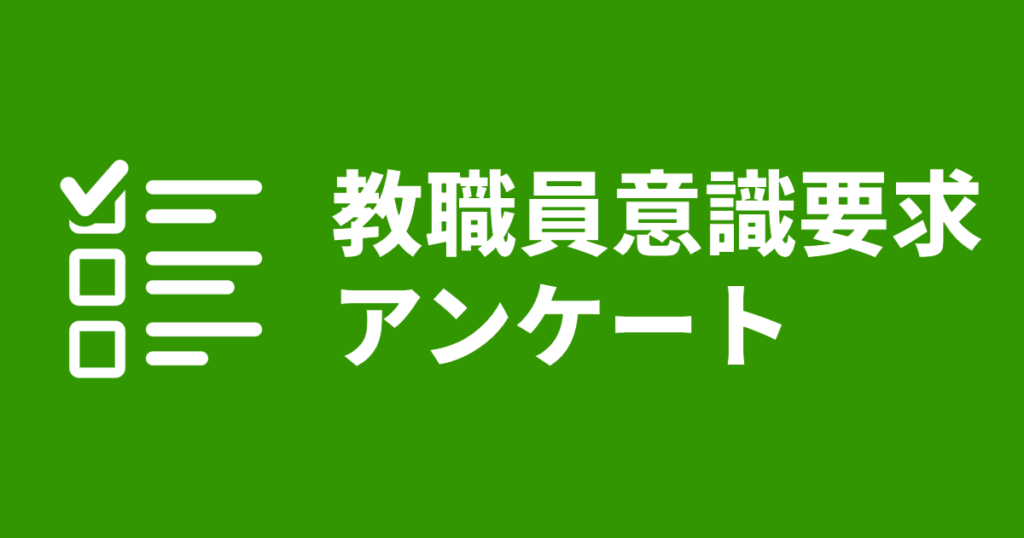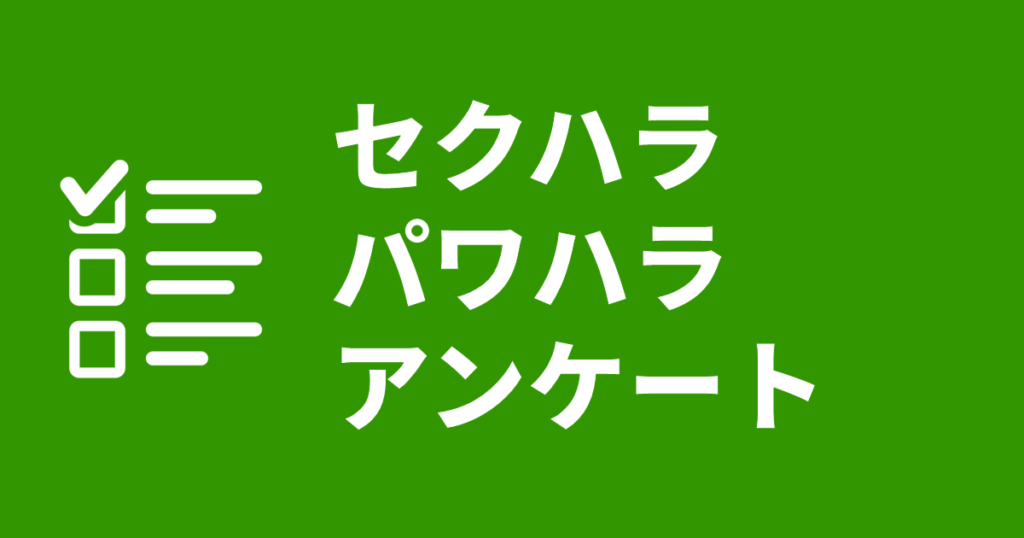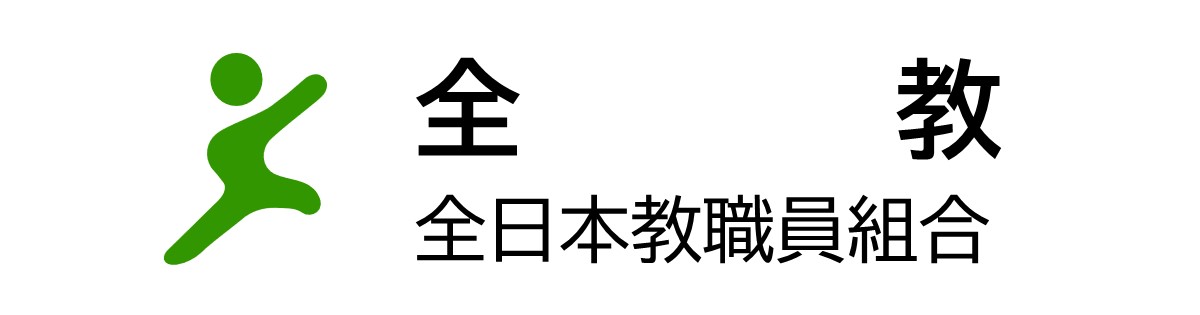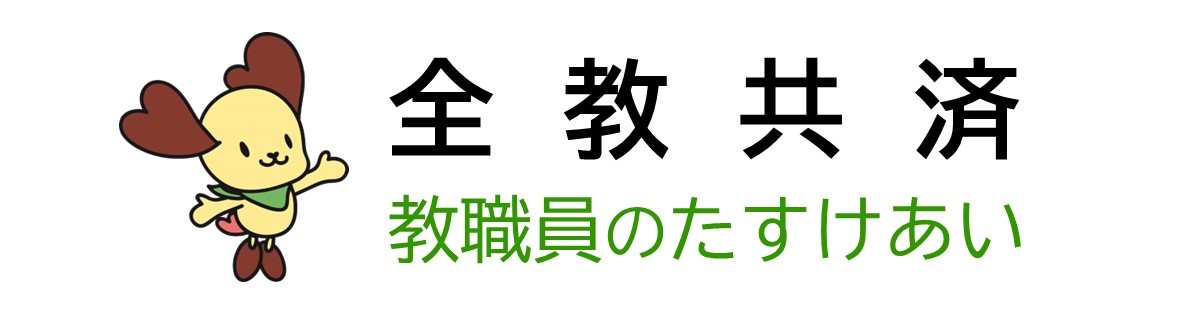新聞全教北九州2024年6月号の特集「国策標語でみる戦時体制下の子ども」を一部加工したものです。印刷にはA3の用紙が必要です。
- ページ番号と「新聞全教北九州」の表示を削除しています。
- 紙面右上に著作権表示を追加しています。
用語と参考文献
新聞全教北九州で4面に掲載していた用語と参考文献です
用語
- 御盾
-
天皇の盾
- 戦技
-
個人が習得すべき軍隊生活や戦闘に必要な技術。敬礼等の所作、射撃、格闘、ほふく等の運動、救護、陣地構築などがある。
- 中等学校
-
旧制中学校、高等女学校、実業学校の総称。戦後は新制高等学校に移行した。
- 国民学校
-
1940年「国民学校令」により国公立の小学校・高等小学校は、国民の基礎教育の場と規定され、国民学校初等科・高等科に改組された。戦後、初等科は新制小学校に、高等科は新制中学校に移行した。適用外の私立学校は引き続き「小学校」と称した。
- 青年学校
-
尋常小学校卒業で就職した青少年に軍事教練を含む社会教育を実施することを目的とした普通科2年、本科3年(女性)または5年(男性)からなる学校。修業年限は男性7年、女性5年。1939年に男性のみ義務教育となる。戦後、普通科は新制中学校、本科は新制高等学校の定時制に移行した。
- 満蒙開拓青少年義勇軍
-
16歳から19歳の男性を「満州国」に開拓民として送出した組織。8万6千人が送出されたといわれ、これは「満州国」への移民の約3割を占める
- 職業紹介機関
-
戦時体制の進展に伴い「職業紹介所」は、「国民職業指導所」(41年)「国民勤労動員署」(44年)と労務統制機関へ変貌した。この機関が発出する「徴用令書」は「赤紙」に対し「白紙」と言われた。戦後「公共職業安定所」となった。
参考文献
表題の漢字は現在のものに改めています
- 日本宣伝協会『国策標語年鑑 昭和十八年度版』(1944)
- 近代日本教育制度史料編纂会『近代日本教育制度史料第7巻』(1956)
- 学校給食十五年記念会『学校給食十五年史』(1962)
- 法政大学大原社会問題研究所『別巻 日本労働年鑑 太平洋戦争下の労働者状態・労働運動』(1964)
- 文部省『学制百年史』『学制百年史 資料編』(ともに1981)
- 厚生省『厚生省五十年史 記述篇』(1988)
- 早川タダノリ『「愛国」の技法』(2014)
- 大蔵省印刷局編『官報 昭和十八年九月二十三日』(1943)
- 日本職業指導協会『国民学校修了者の進職指導』(「職業指導 昭和十八年十二月号」1943 )
- 逸見勝亮『日本学童疎開史研究序説』(「北海道大學教育學部紀要51号」1988)
- 中村祐司『戦時下の国民体育行政―厚生省体育局による体育行政施策を中心に―』(「早稲田大学人間科学研究 5巻第1号」1992)
- 坂上康博『太平洋戦争下のスポーツ奨励―1943年の厚生省の政策方針、運動用具及び競技大会の統制―』(「 一橋大学スポーツ研究29巻」2010)
- 首藤卓茂『軍需工場などへの福岡市と近郊女学校生の通年勤労動員』(「福岡地方史研究61号」2023)
- 中島寧綱『職業安定行政史 : 江戸時代より現代まで』(一般財団法人日本職業協会のウェブサイト)
- 『学童疎開とは』(全国学童疎開連絡協議会のウェブサイト)
- 写真はすべてウィキメディア・コモンズ