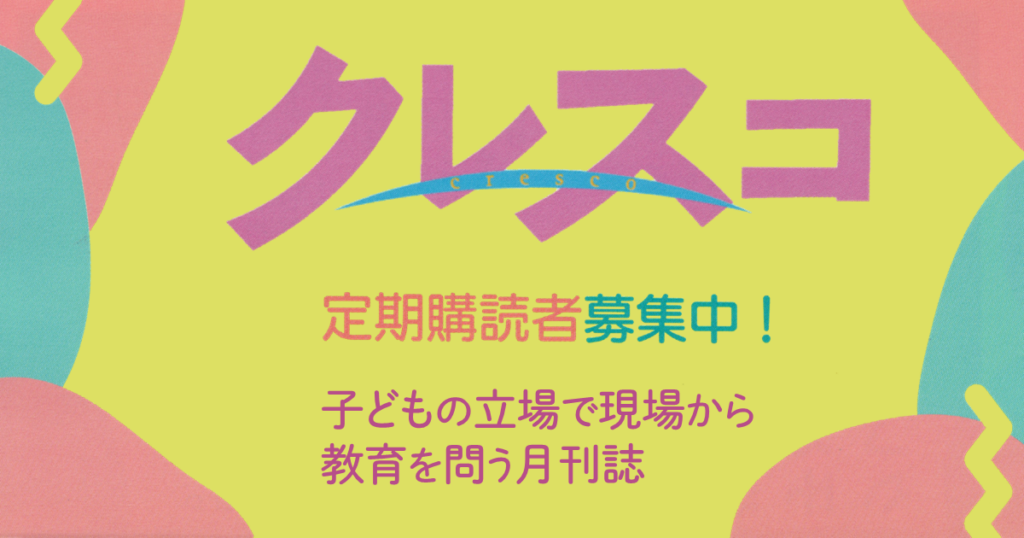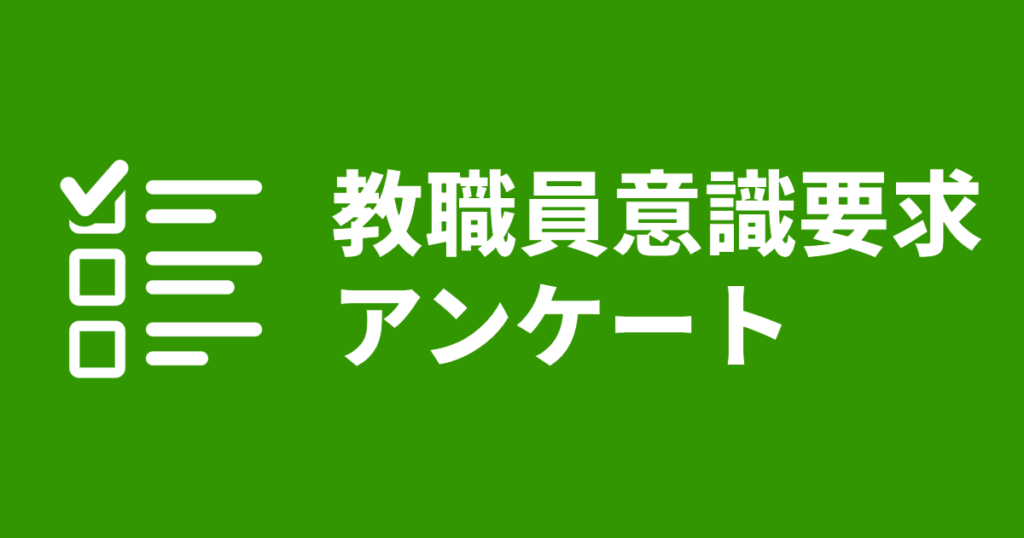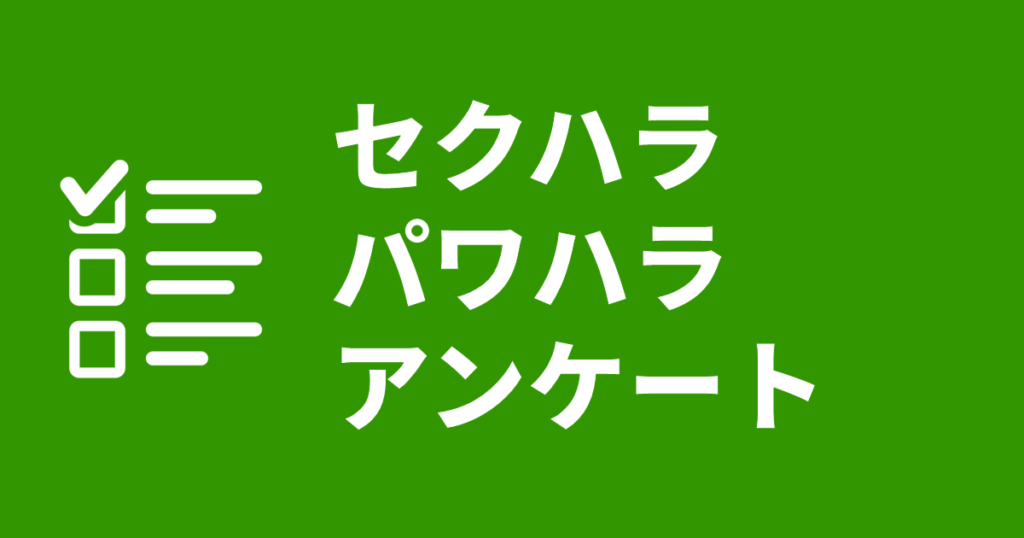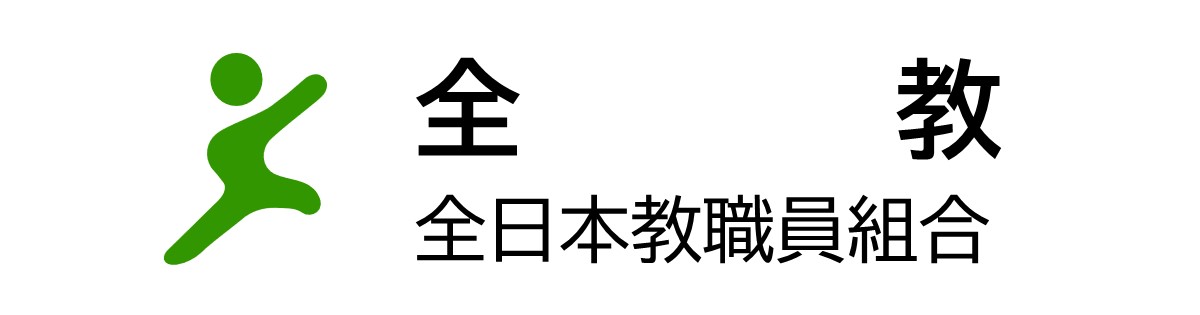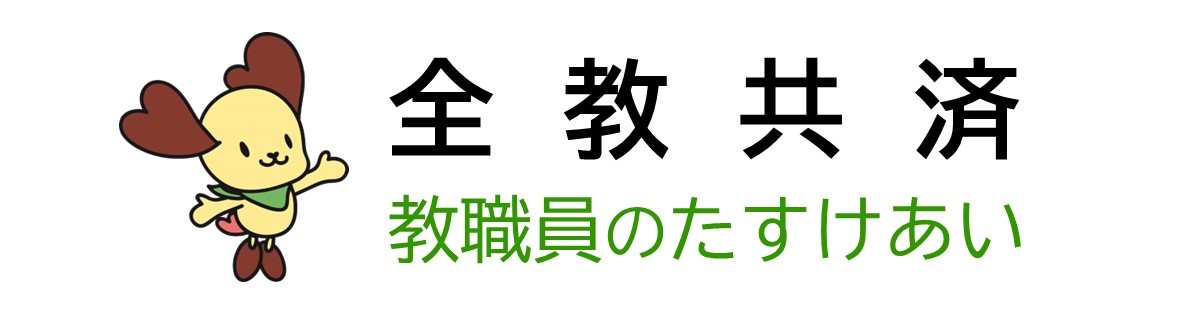全日本教職員組合中央執行委員会は、2025年6月10日、第217通常国会において、給特法をはじめ、学校教育法、地教行法、教特法等の一部を改定する法案が、参議院文教科学委員会において、21もの附帯決議とともに採択され、6月11日、参議院本会議で可決される見込みとなったことをうけて、声明「長時間過密労働を野放しにし、職場の共同性を破壊する給特法等改定案の成立に断固抗議します」を発表しました。
6月10日、第217通常国会において、「公立の義務教育諸学校等における教育職員の給与等に関する特別措置法(以下、給特法)」をはじめ、学校教育法、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下、地教行法)」、「教育公務員特例法(以下、教特法)」等の一部を改定する法案が、参議院文教科学委員会において、21もの附帯決議とともに採択され、明日6月11日、参議院本会議で可決される見込みです。
改定法案の最大の問題点は、公立学校の教員のみ、膨大な時間外勤務を「在校等時間」というあいまいな概念で労働時間として認めず、一切の時間外勤務手当を支給しないという労働基準法の原則を平然と踏みにじったところにあります。制定以来50数年ぶりの給特法改定の中心的論点は、私たちの願いである教職員の長時間過密労働の解消であったはずです。「超勤4項目」に該当する業務以外の時間外勤務を命じない代わりに、時間外勤務手当を支給しない現行の給特法のしくみは維持されたままです。
さらに「処遇改善」とされた教職調整額の引き上げは、長時間過密労働の解消とは無関係です。競争主義的なメリハリ賃金と「主務教諭」の創設は、職場を分断し、管理統制が強められ、教育そのものが破壊されることが懸念されます。決定的な矛盾を残したまま不十分な審議で採決されたことに断固抗議するものです。
全教は、長時間過密労働解消のため、時間外勤務手当支給を可能にするしくみづくりと、基礎定数の抜本的改善および教職員増、そのための教育予算の増額を求め続けてきました。各組織でも改定法案の問題点を広く知らせるための社会的アピールととりくみが進み、廃案を求める運動への連帯は大きく広がりました。繰り返しおこなった国会議員への要請やFAX行動により、改定案の矛盾や問題点を次々と明らかにしてきたのです。
審議を通して「「授業時数の削減」や「教職員定数の標準を改定」を盛り込まざるを得なかった附帯決議は重要である一方、「措置を講ずる」とするだけで、措置の中身をどのように具体化をするのかは明言していません。私たちが求めているのは、確実に実効ある基礎定数の改善と持ち授業時数の上限設定です。そのために追及の手を緩めることはできません。
政府の示した「在校等時間」の縮減と処遇改善等の具体化は、各自治体に丸投げされました。今後、たたかいの舞台は各自治体となり、改定法案の条例化を許さないことが重要です。いくつかの自治体では、法案通過の前にもかかわらず、「主務教諭」の創設前提の動きがあり、法案の問題点の社会的共有は急務です。法案に明記された「主務教諭」はあくまでも「置くことができる」規定です。
また日本の教職員の長時間過密労働は、国際的にも特異なものです。全教が申し立てをおこなっているCEART(ILO/ユネスコ教員の地位勧告適用合同専門家委員会)は、「所定労働時間を超える労働について適切に報酬を支払う透明性のある制度を工夫すること」と日本政府に勧告しています。無定量な時間外労働の放置は、許されません。
全教は、職場・地域における学習と対話を重ね、条例化を許さないとりくみに全力をあげるものです。すべての自治体において、当局との交渉で実効ある長時間過密労働解消のための施策の実施とすべての教職員の処遇改善、そして「主務教諭」の創設と特別支援にかかわる「給料の調整額」の半減に反対するとりくみを強めるものです。
「せんせいふやそう」の圧倒的な世論の構築は、まだまだ必要です。
子どもたちのSOSを受け止め、子どもたち一人ひとりの成長と発達に寄り添った教育を実現するために、長時間過密労働と教職員未配置の解消は絶対条件です。ゆきとどいた教育を実現するため、教育政策の転換と教育予算増の実現をめざすとともに、改定法案の条例化を許さないたたかいに全力をあげる決意を表明するものです。