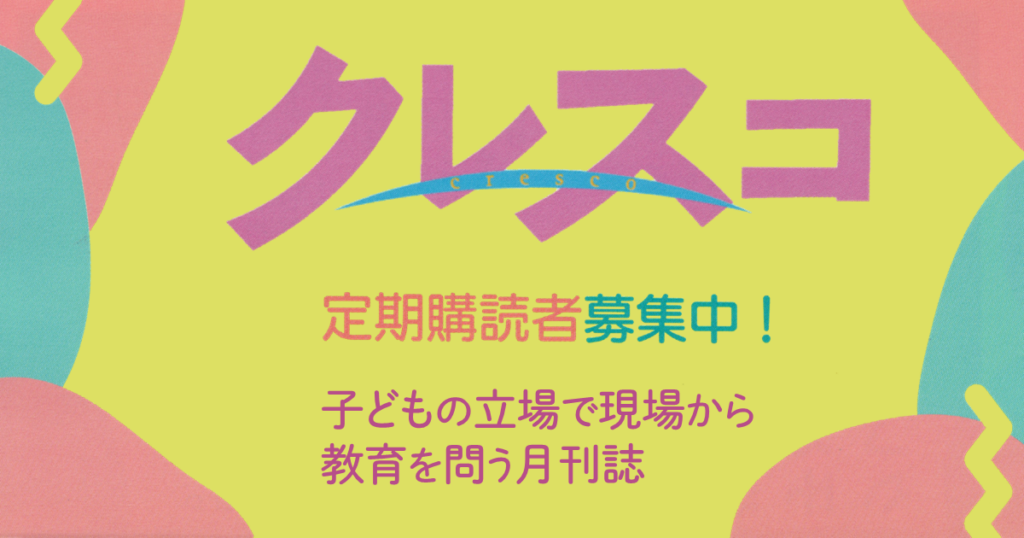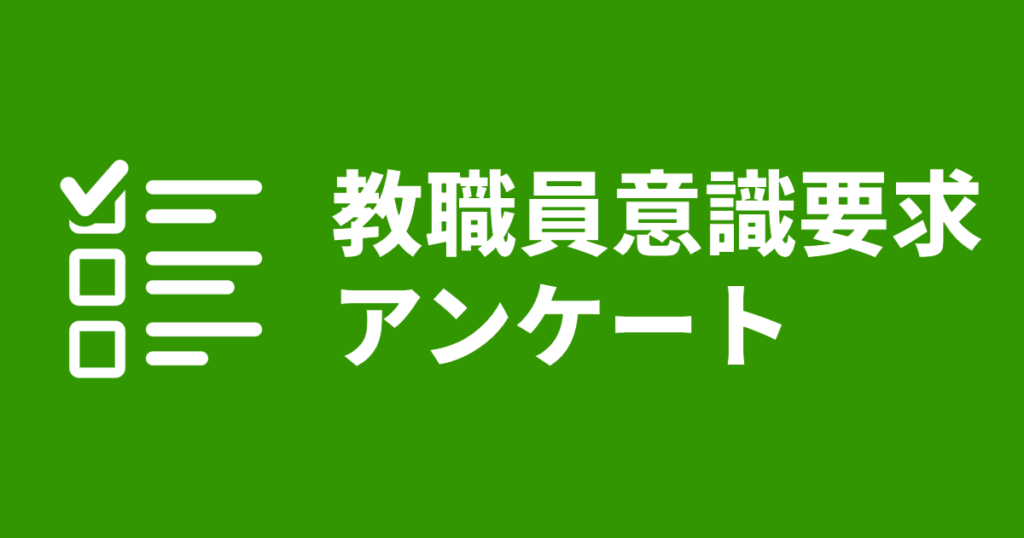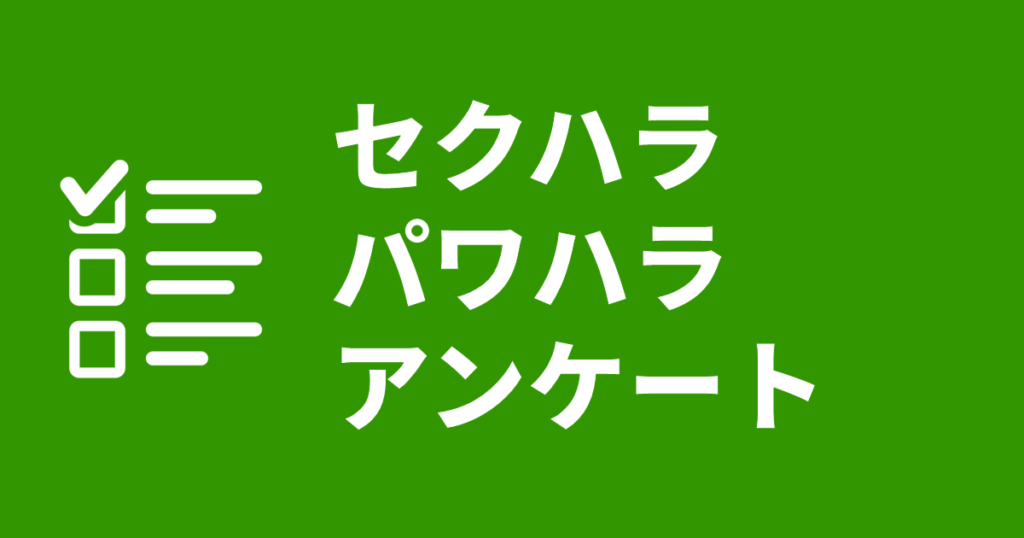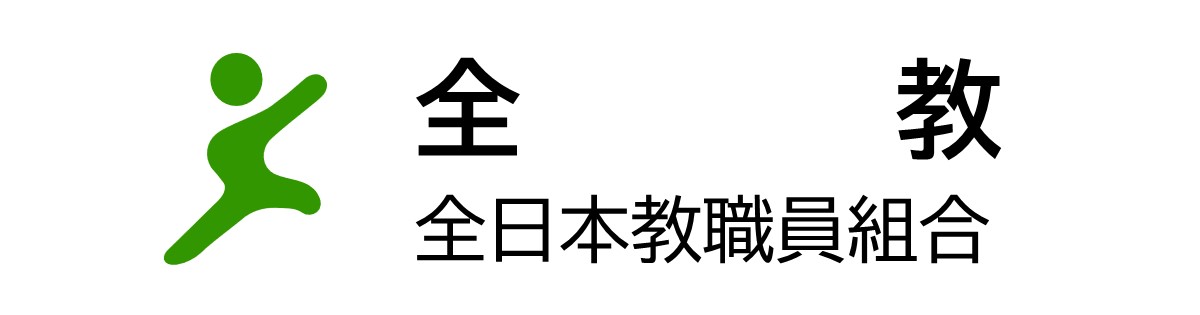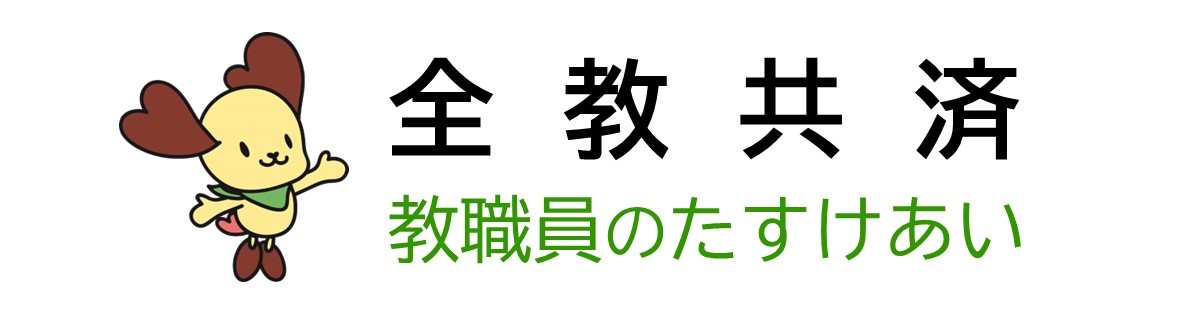給特法改定案では長時間過密労働は解消しない
5月15日、衆議院本会議において、政府の給特法等改定案が可決されました。全教は、政府の給特法等改定案の廃案を求め、本会議や委員会の傍聴行動や国会前集会、国会議員への働きかけ、街頭宣伝や記者会見をおこない、その問題性を広くアピールしてきました。
運動と論戦で明らかになった「給特法」改定案の問題点
4月10日、第217回通常国会において、「公立の義務教育諸学校における教職員の給与等に関する特別措置法(給特法)」等の一部を改定する法案が審議入りしました。私たちの運動と国会での追及によって「給特法」改定案の問題が明らかとなるなかで、4月中の衆議院通過はできなくなりました。しかし、5月14日、給特法等改定案は衆議院文部科学委員会で修正のうえ、自民・公明・立憲・国民・維新の賛成多数で採決されました。翌5月15日の衆議院本会議では、質疑をしないないまま採決されました。
長時間労働を抑制できない「教職調整額」
給特法により、教員は残業代が支払われない代わりに、4%が給料に「教職調整額」として上乗せされています。
しかし、この教職調整額は時間外労働の対価ではなく、あくまで教員の勤務の特殊性に配慮したものであり、時間外労働を抑制する効果は期待できません。実際に多くの教員が長時間労働を強いられており、過労死ラインである月の時間外労働が80時間を超えて働いている例も少なくありません。
時間外勤務は「自発的・自主的な活動」ではない
教員の時間外勤務は「自発的・自主的な活動」として、労働基準法上の労働時間とみなされません。時間外勤務や残業という用語が使えないため「在校等時間」という用語が生み出されました。時間外勤務とみなされないために、休日出勤や持ち帰り仕事、休憩時間中の勤務などが正確に把握されず、過労を防ぐための対策を講じることが困難になっています。
「定額働かせ放題」は解決しない
このような理由から、給特法は「定額働かせ放題」と批判されます。教職調整額の支給率が4%から10%に引き上げられても、根本的な問題解決にはなりません。
給特法は教員の健康と精神を蝕む
長時間労働や過大な業務量は、教員の精神的な負担を増加させ、休職や退職に追い込まれるケースも発生しています。給特法の問題は、単に金銭的な問題だけでなく、教員の健康に関わる問題です。
現状に合わない給特法
給特法は教員の職務の特殊性や、時間外労働の状況を踏まえ、給与や勤務条件について特例を定めるという趣旨で作られました。しかし、時代とともに教育現場の状況は変化しており、給特法は教育現場の現状に合わなくなっています。教員の過大な業務量の削減を進めるとともに、教職員を大幅に増やすことが現状の解決策です。