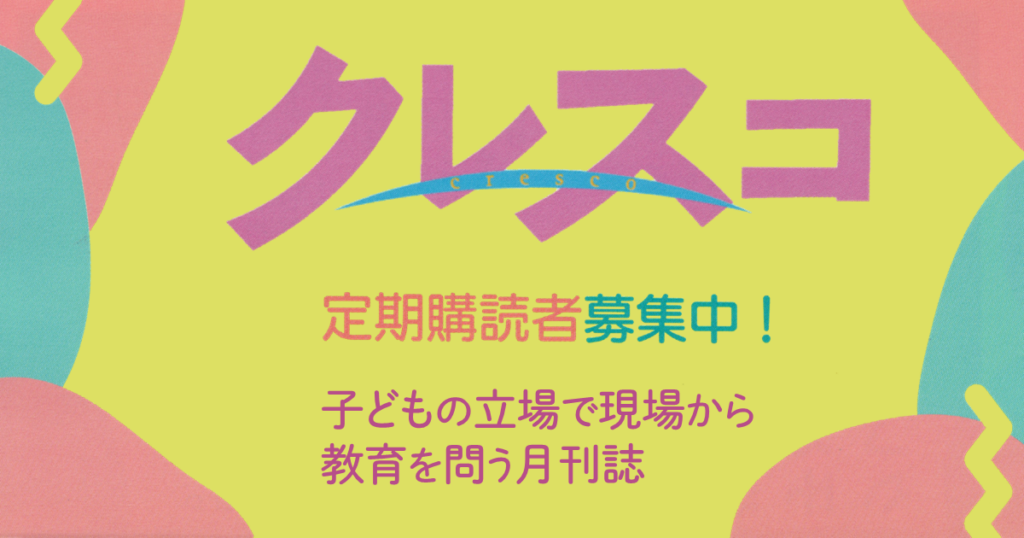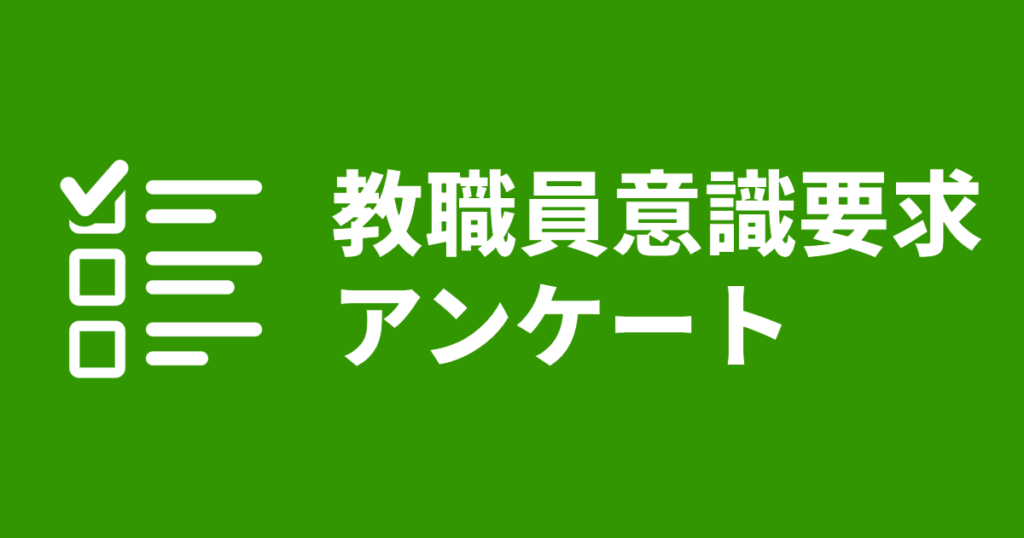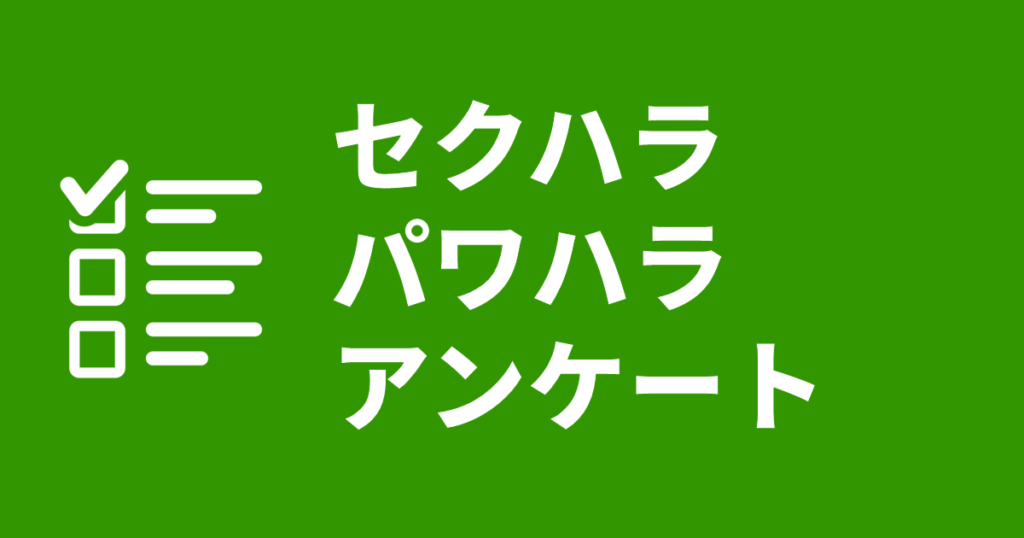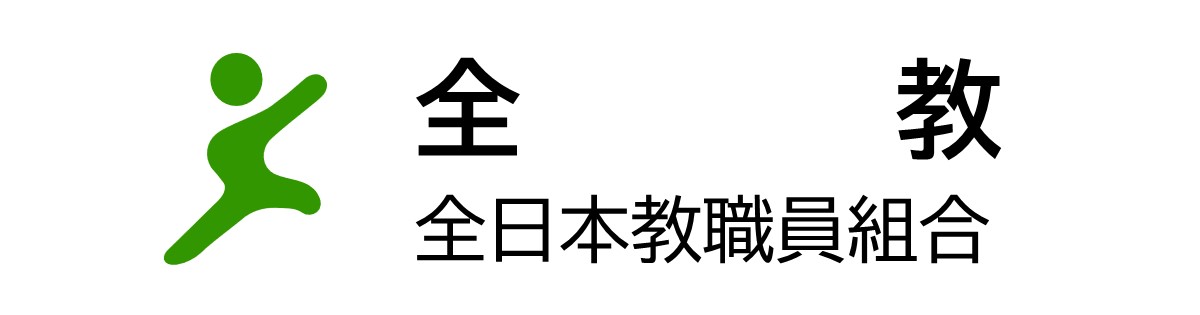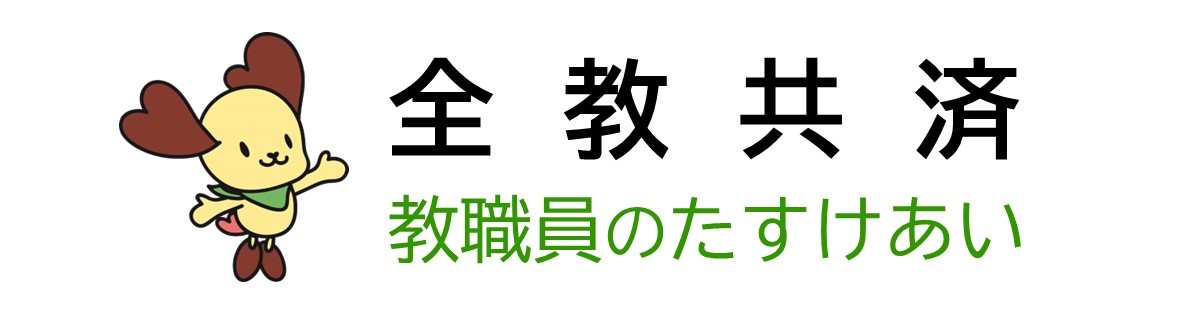全教(全日本教職員組合)「障教部ニュース4」より
衆議院文部科学委員会での「給特法」の審議では、4月23日、25日に与野党からの参考人質疑が行われ、政府の「給特法改定案」では長時間勤務が全く解消されない問題等が浮き彫りになりました。全国から組合員が国会にかけつけ、国会傍聴や国会前の座り込みをしました。政府案では教員定数は増えない。業務は減らない。増えるのは階層と評価と管理。給料の調整額が削られる。この法案に「反対」の声をあげ、廃案に追い込みましょう。
4月11日に全教障教部が文科省へ送付した質問書に対する回答が4月23日にありましたのでお知らせします。
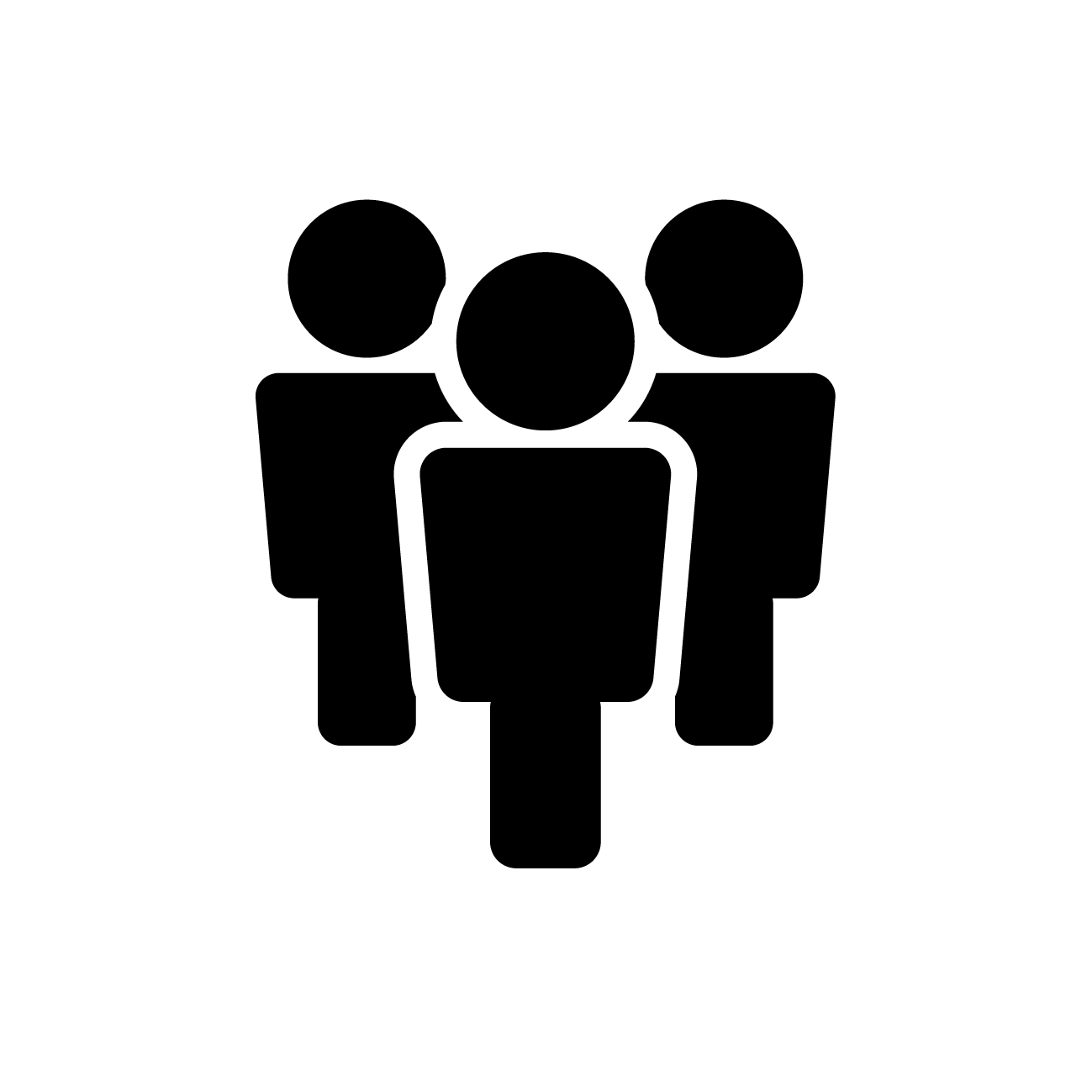 全教障教部
全教障教部「給料の調整額」が全廃されている自治体での「負担と処遇のバランス」
「学級担任手当」加算を特別支援学校、特別支援学級には行わない理由として、文部省から「給料の調整額」を半分残し「学級担任手当はつけない」ことにより通常学級との「負担と処遇のバランスをとる」という説明がありました。
「給料の調整額」がすでに全廃されている自治体があります。小、中学校にでは、「学級担任手当」加算がつく通常学級の教員と、手当加算がつかない特別支援学級の教員とが生じることから、校内人事で支障がでるのではないかとの心配の声があがっています。
「給料の調整額」が全廃されている自治体では、どのように文科省のいう「負担と処遇のバランス」をとるのでしょうか。
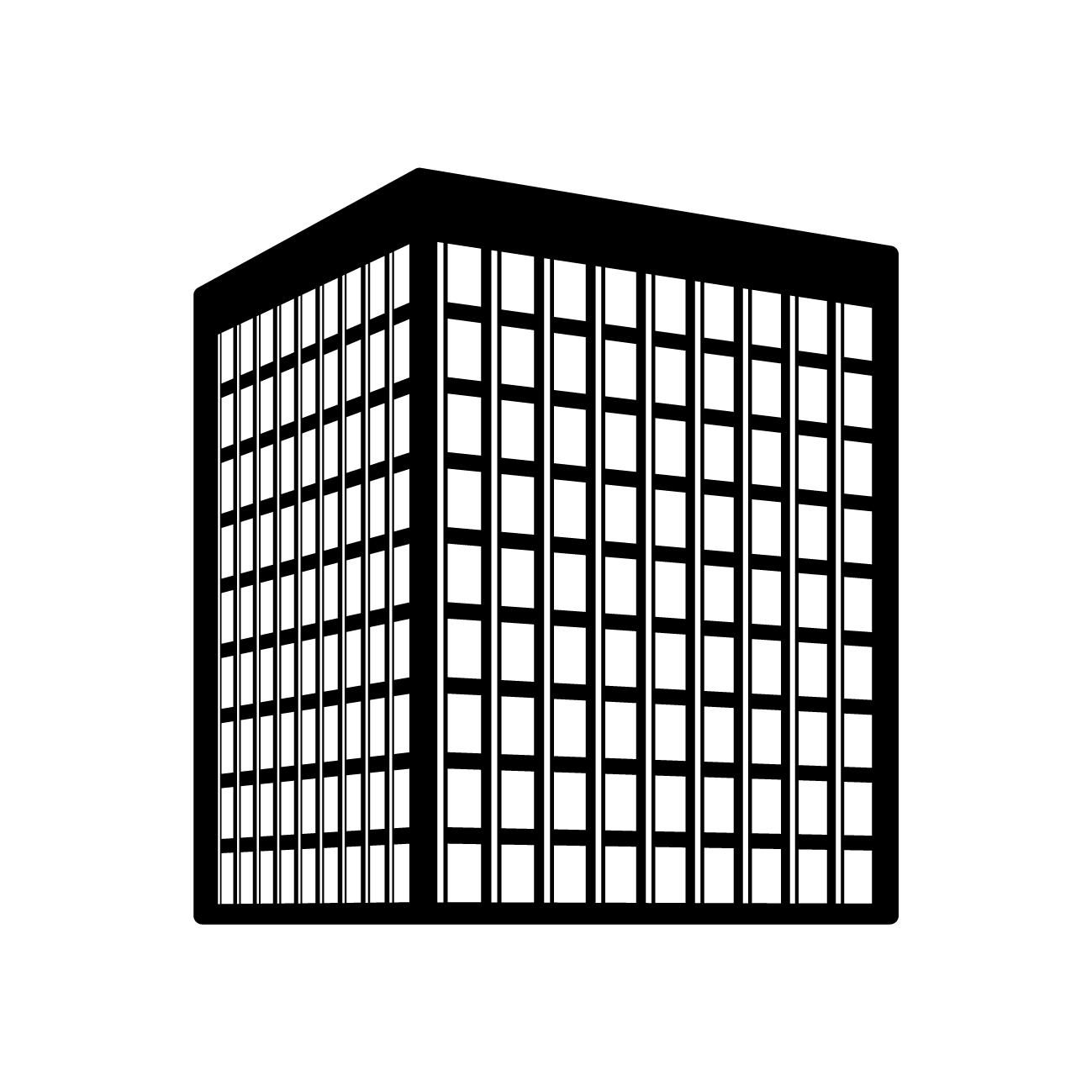
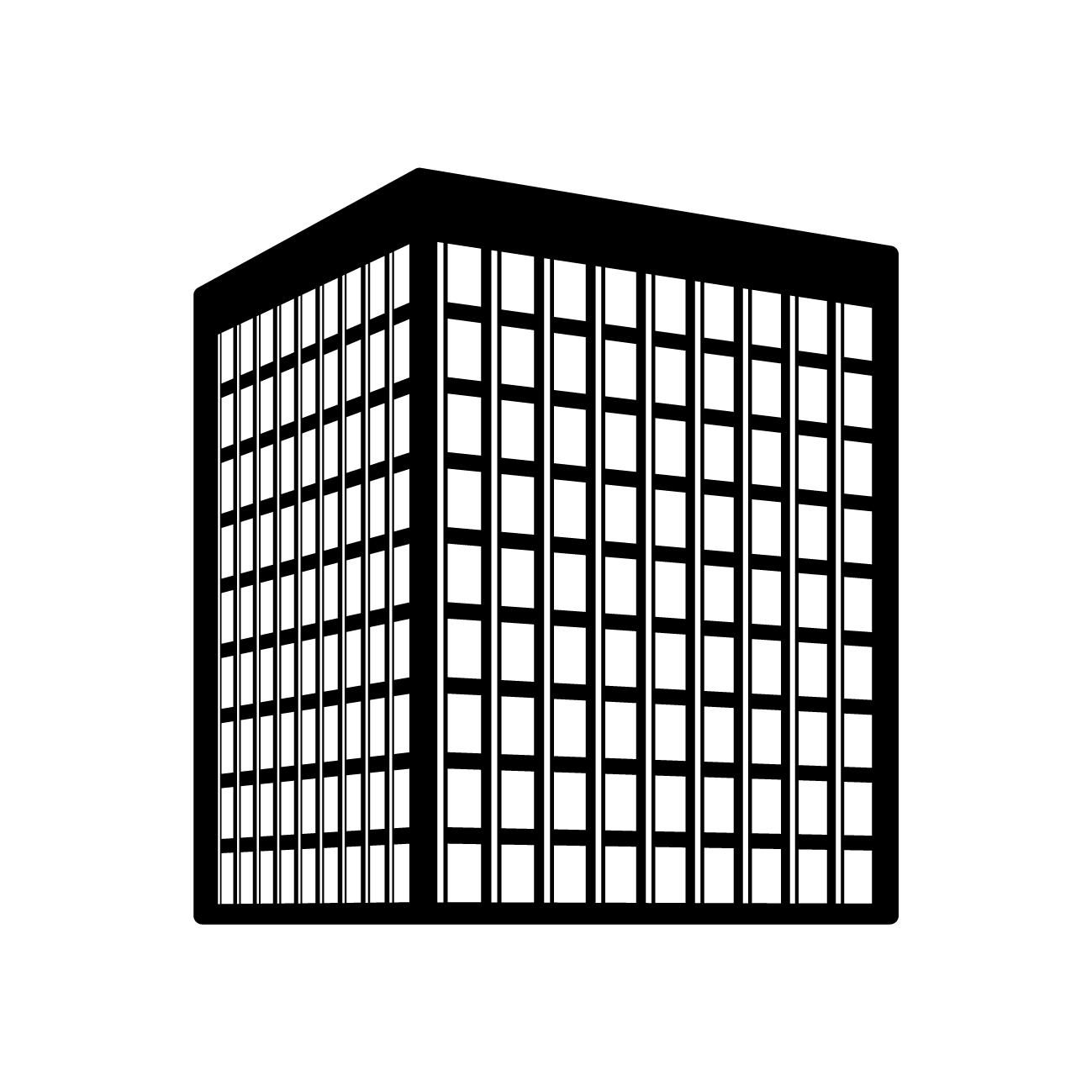
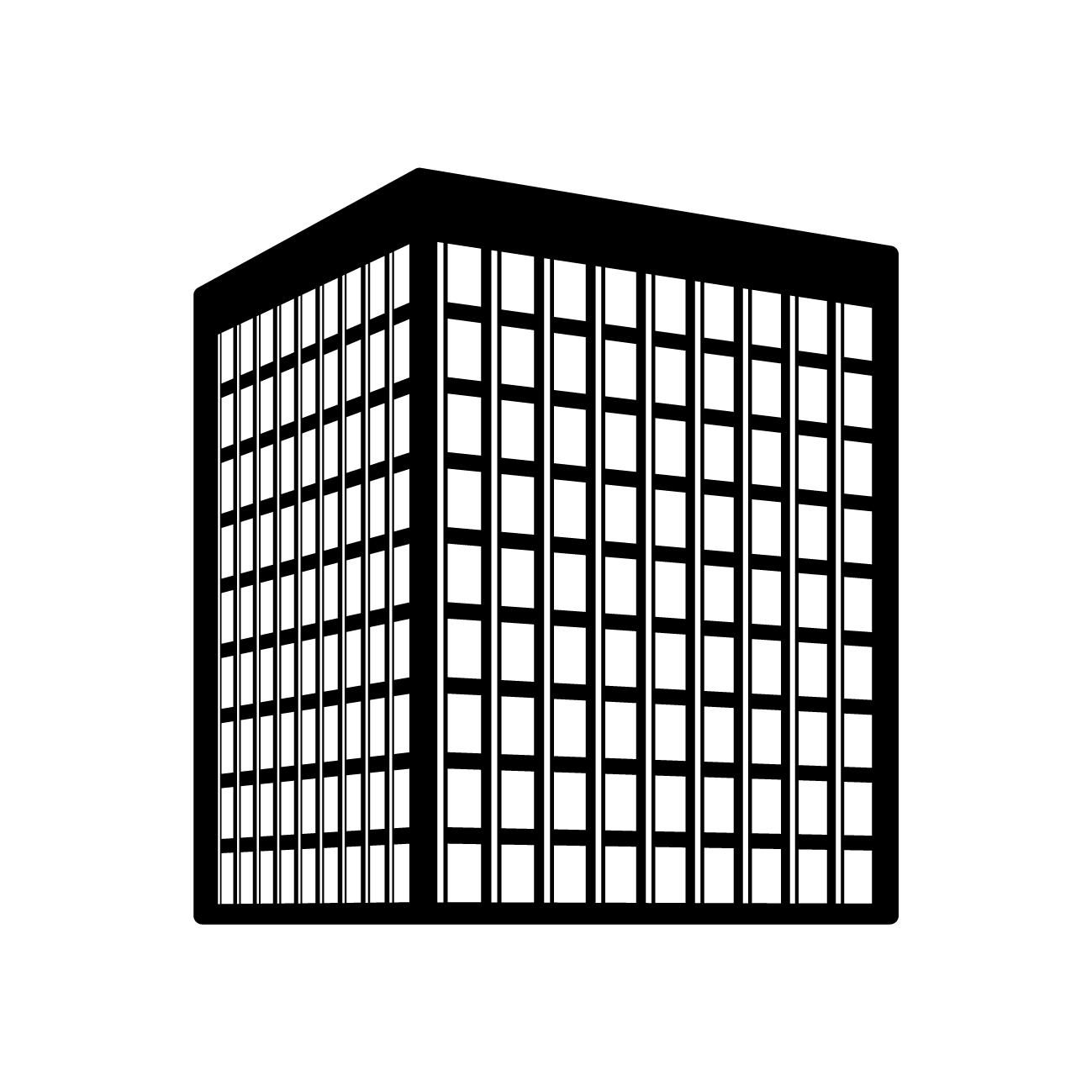
文科省は処遇改善を含め各種手当の考え方において、各自治体の支給状況によらず、国庫負担金の限度額の算定において、それらを反映して国庫負担をしています。
その上で給与条例主義をふまえて各自治体において対応するものと考えております。
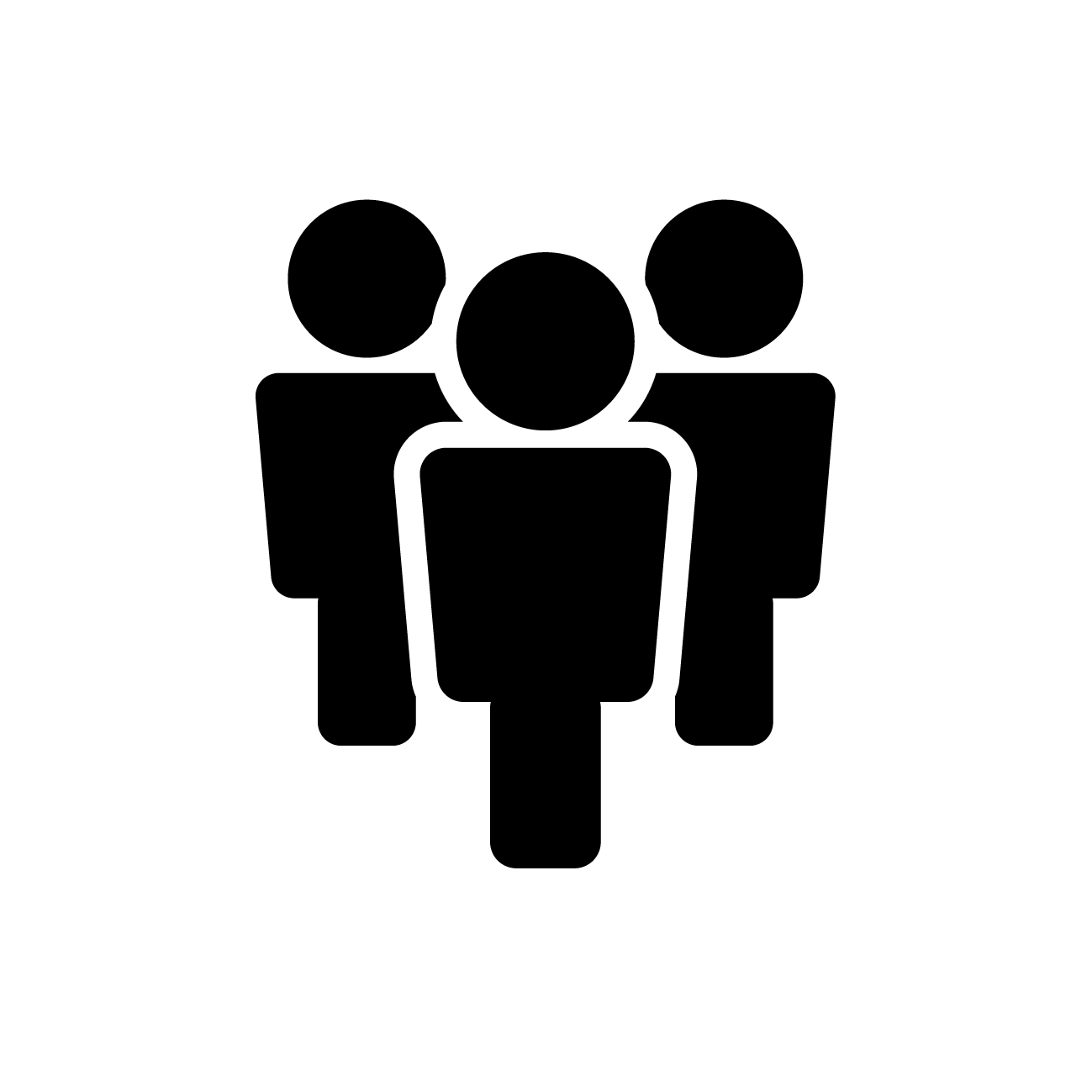
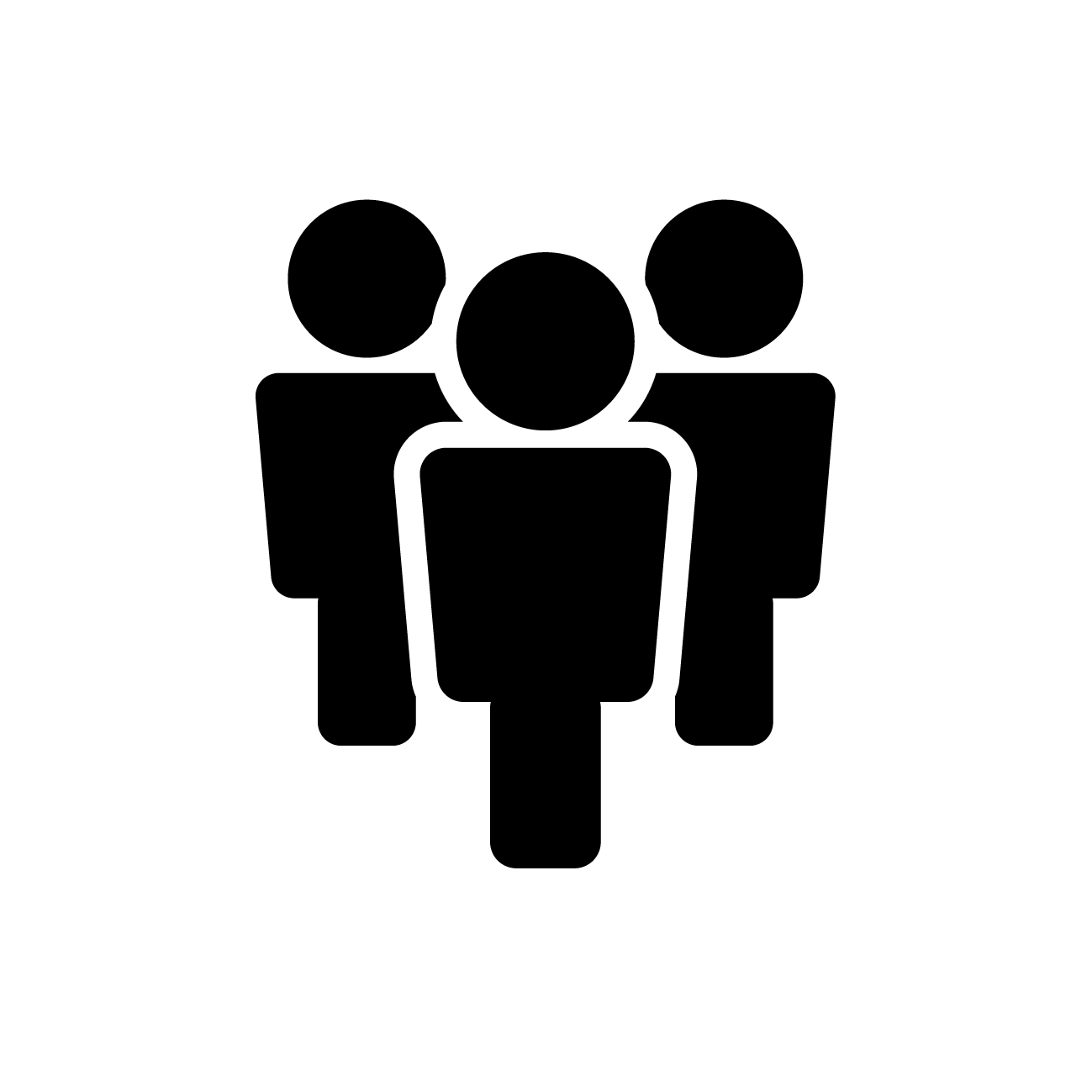
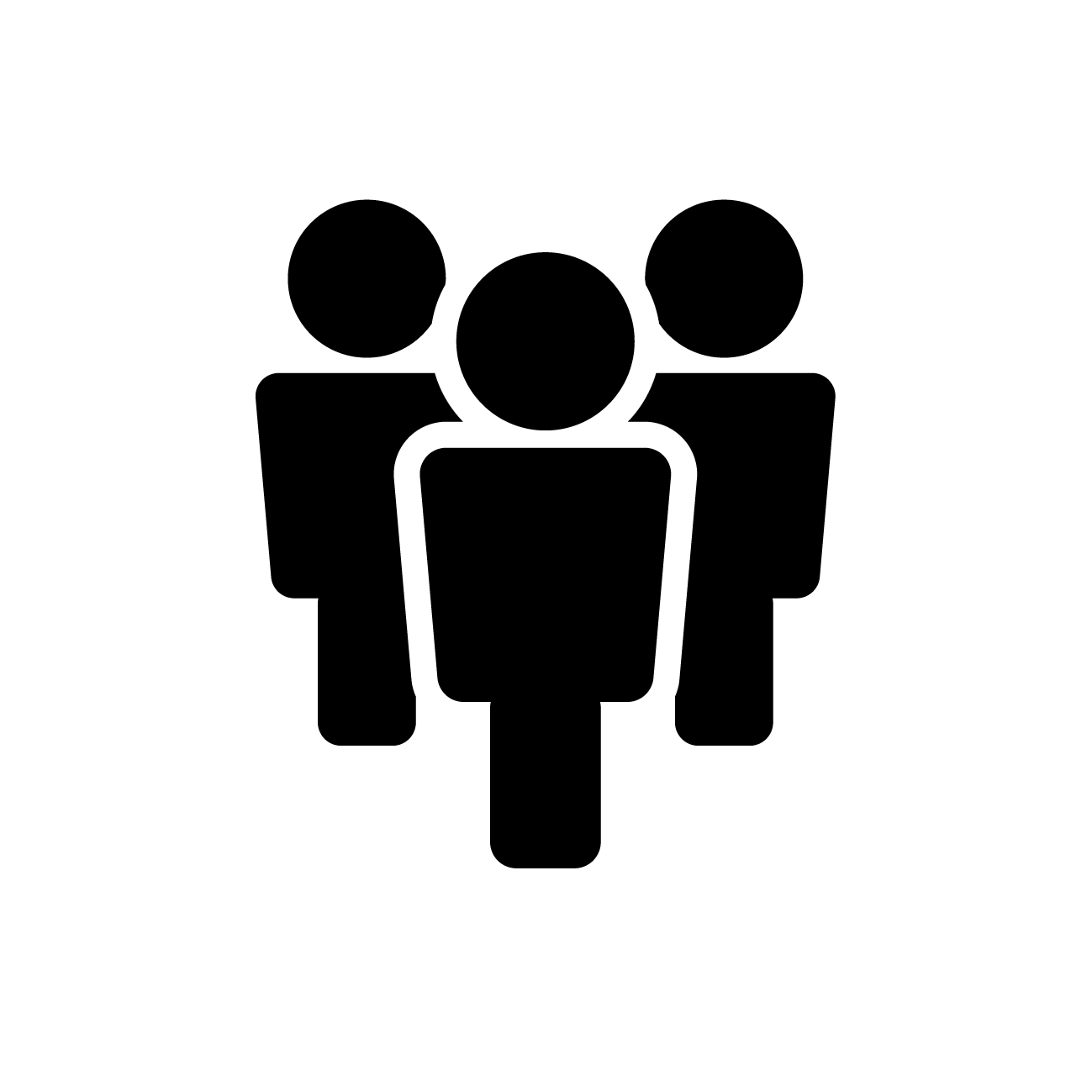
「給料の調整額」を本給で支給している自治体や、手当化して支給している自治体があります。
財源はいずれも国庫負担金であり、国庫負担金を配分して給与を支給する段階で、自治体ごとに条例で定めることになります。
条例化の交渉で、分断を持ち込む処遇を導入させないことが大切です。
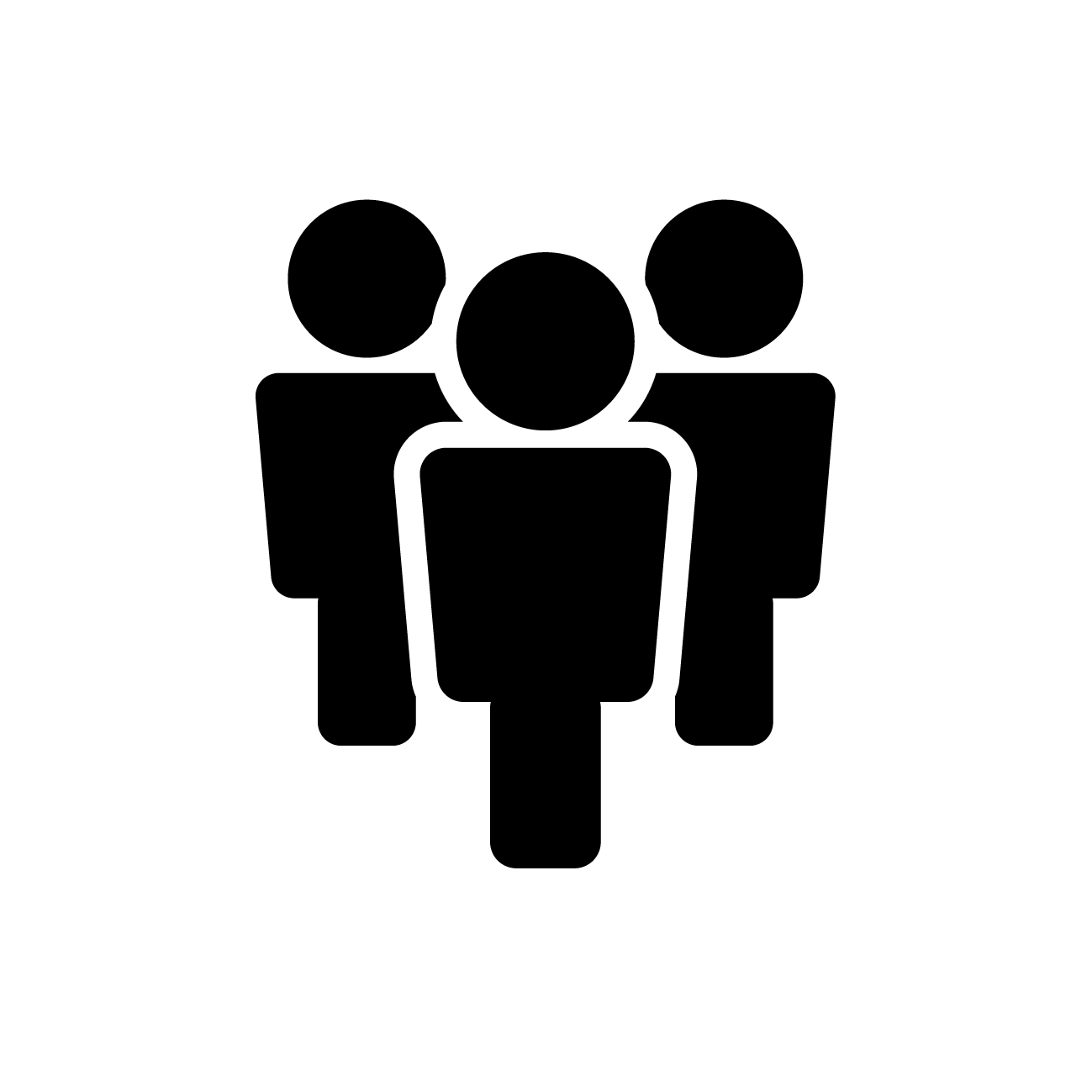
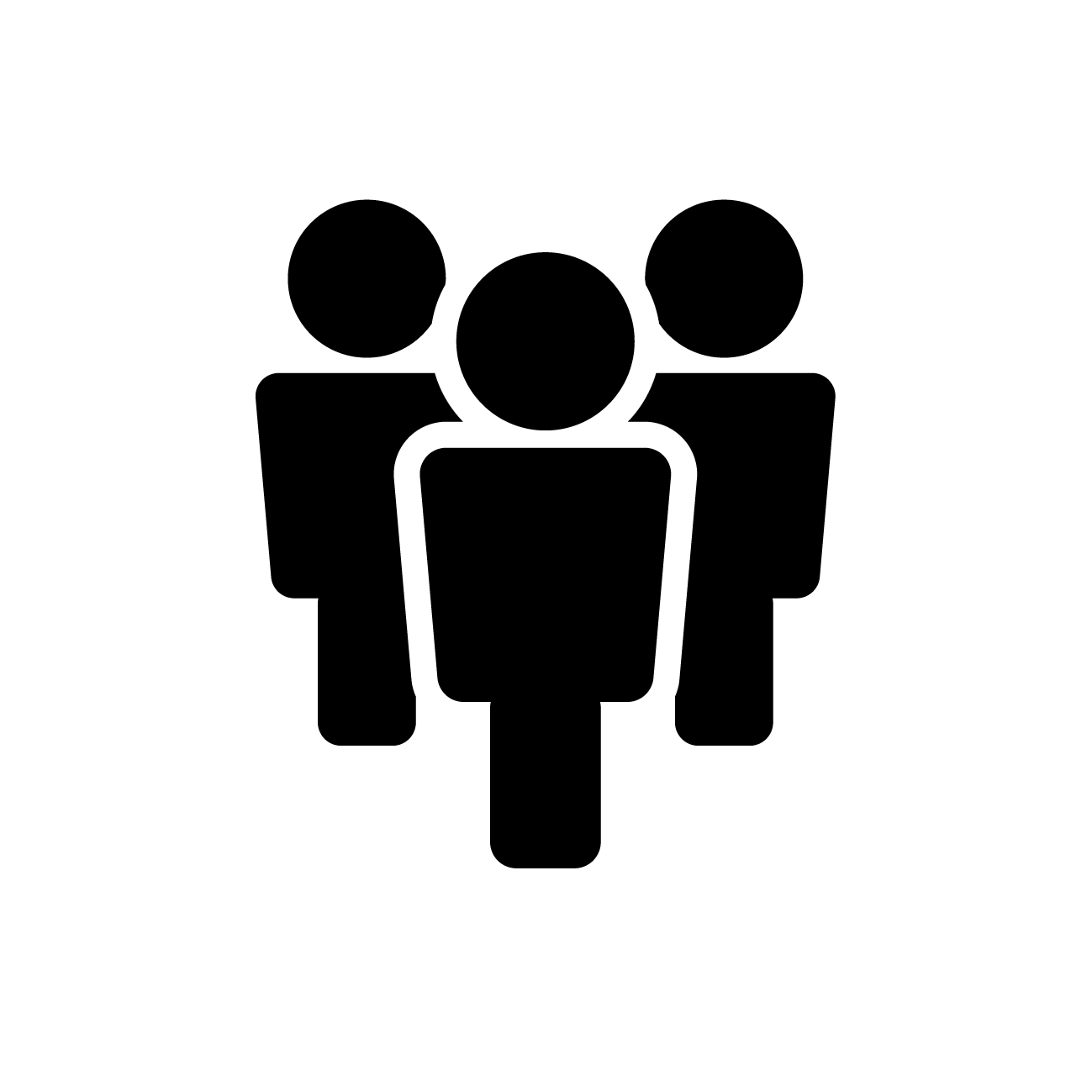
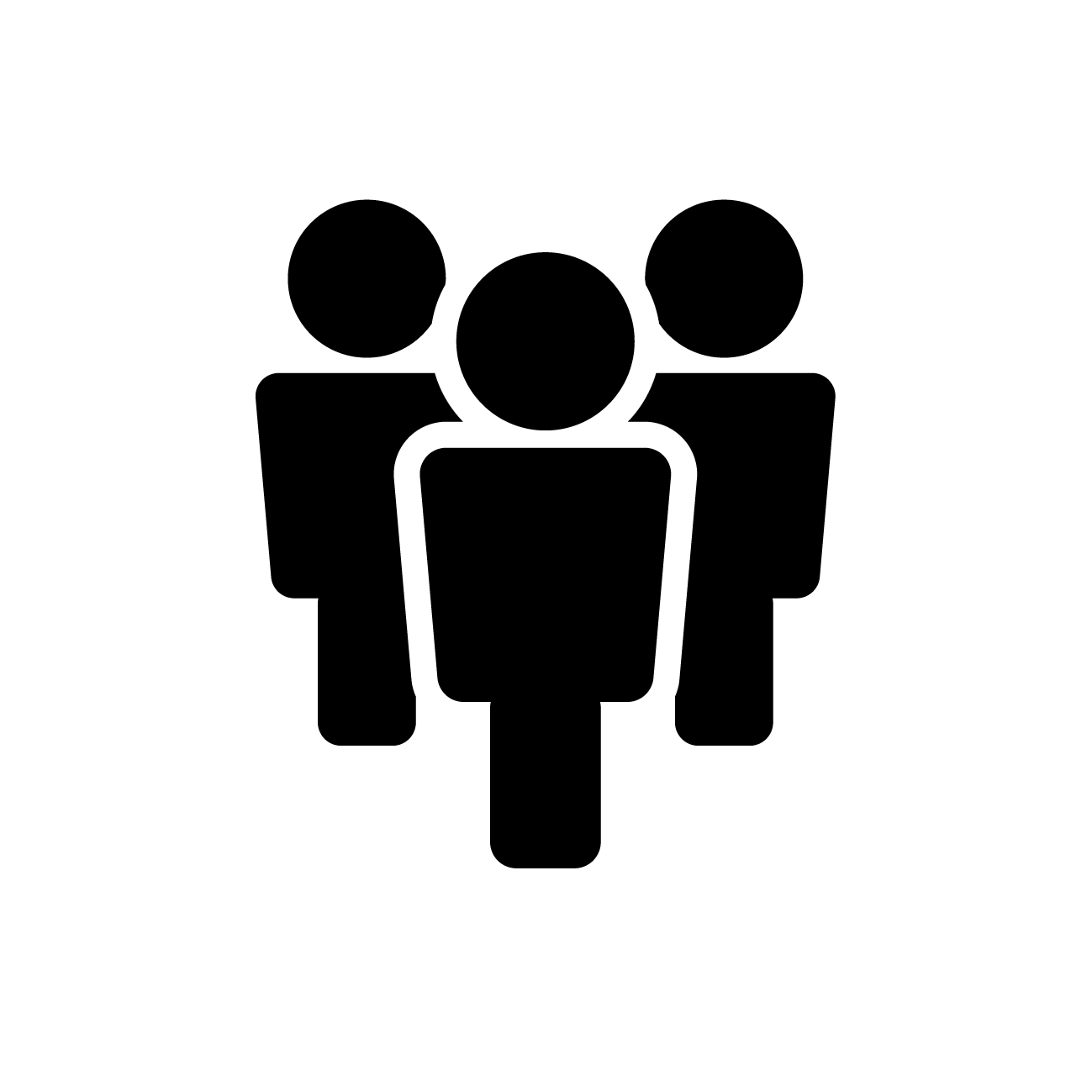
幼稚園教諭は、「子ども子育て新制度」による処遇の改善がおこなわれたことなどを理由に「教職調整額」を4%に据え置く案になっています。
特別支援学校の幼稚部の教諭も「教職調整額」は4%で据え置きですか?
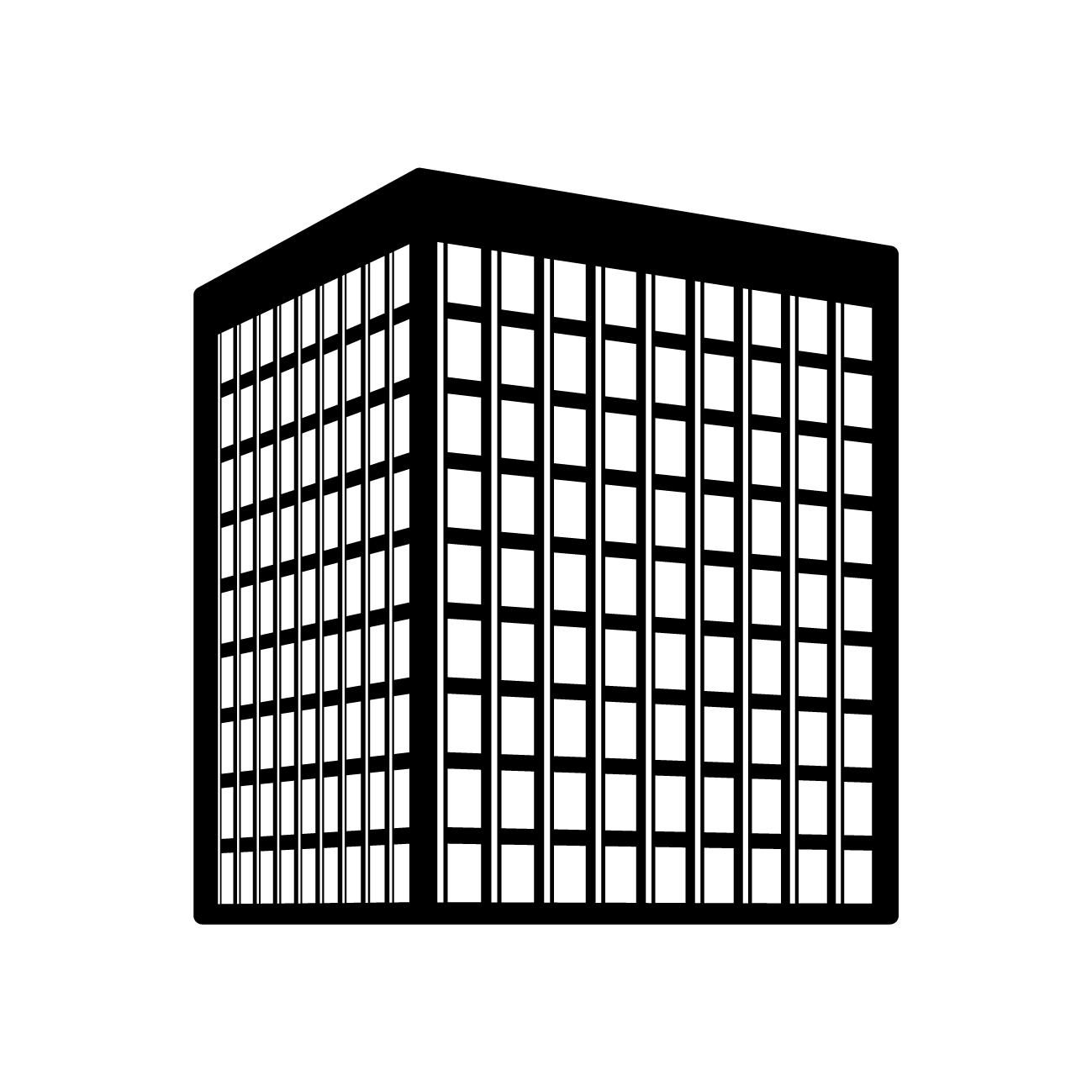
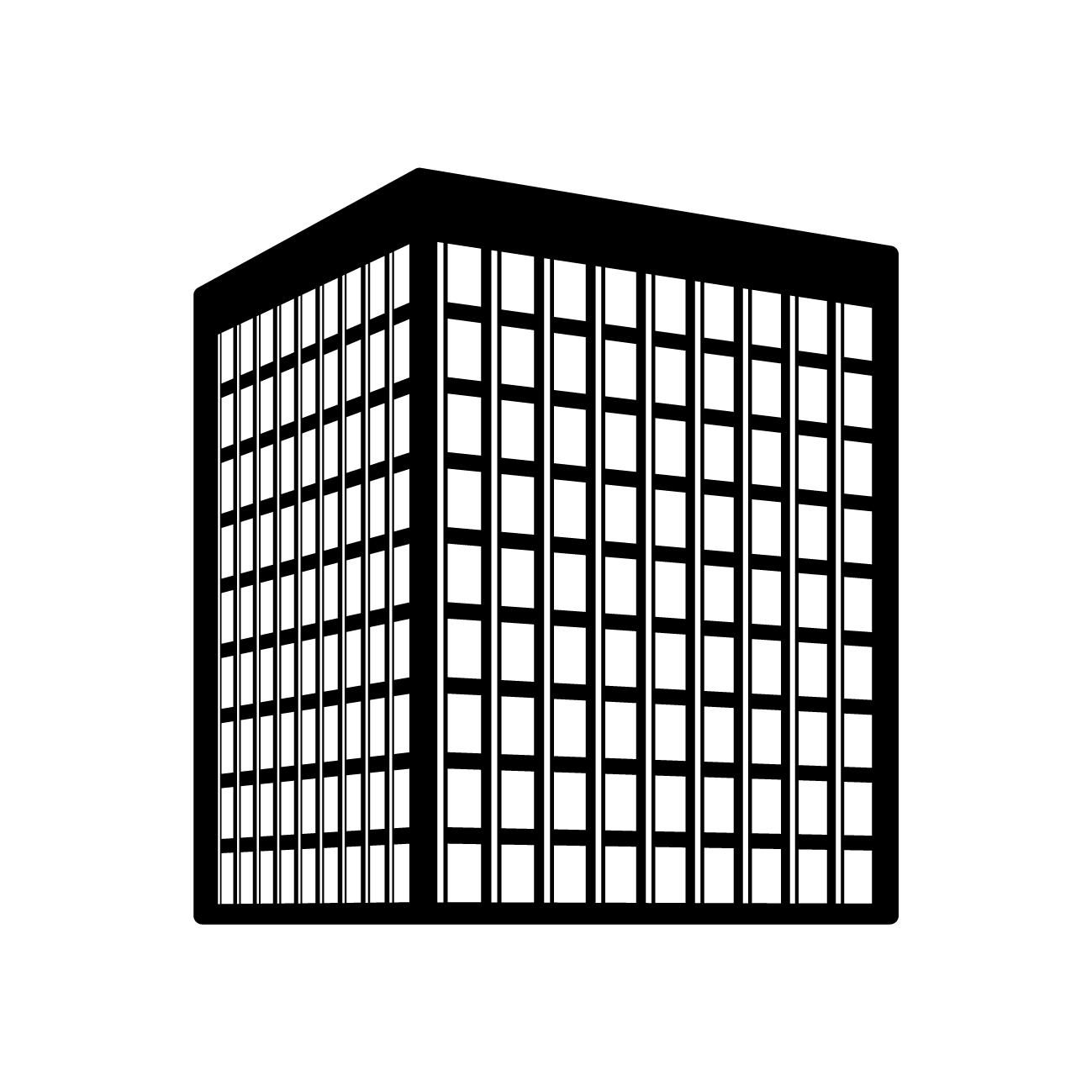
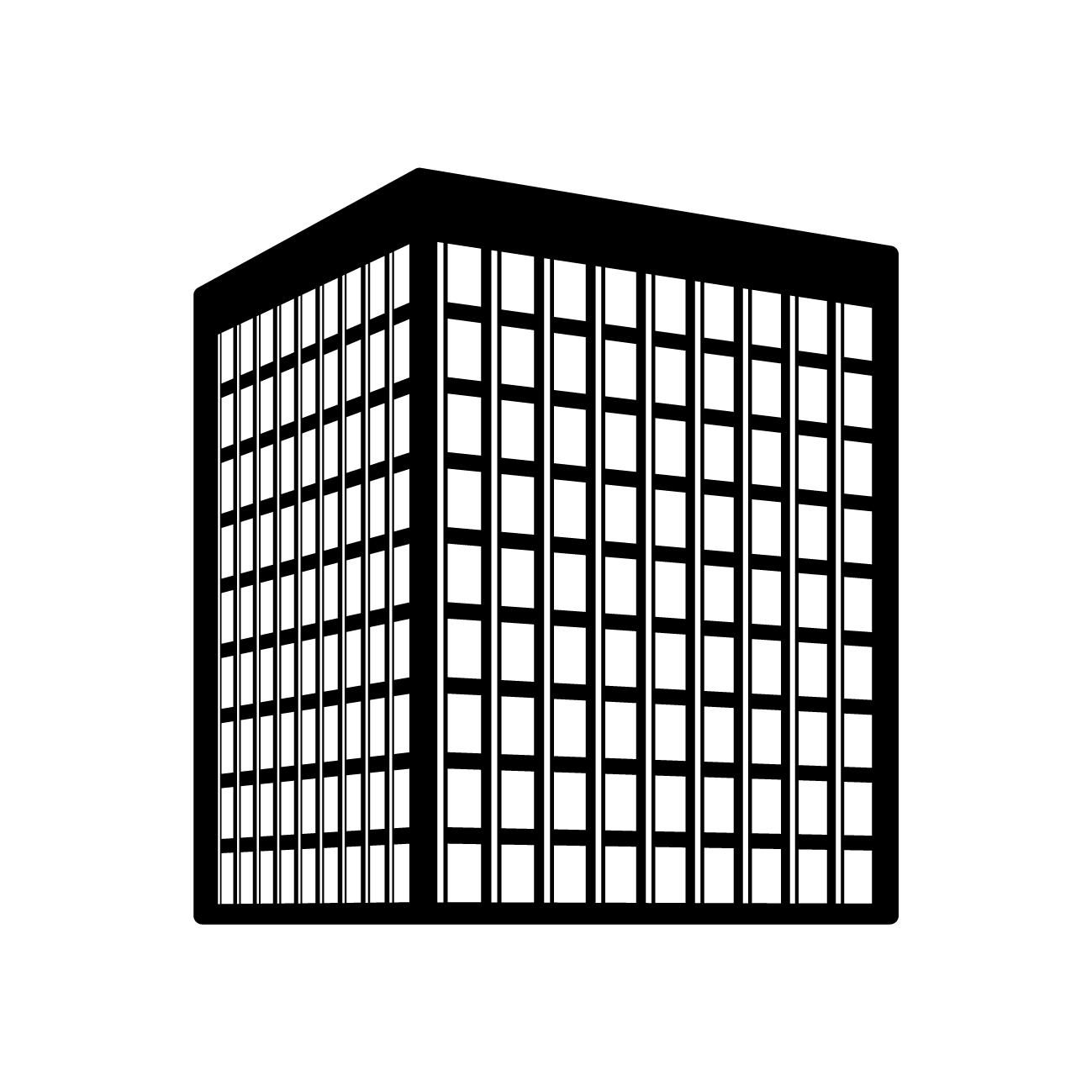
特別支援学校幼稚部の教諭の「教職調整額」は、特別支援学校の他の学部の教諭と同様に、毎年1%ずつ10%まで引き上げます。
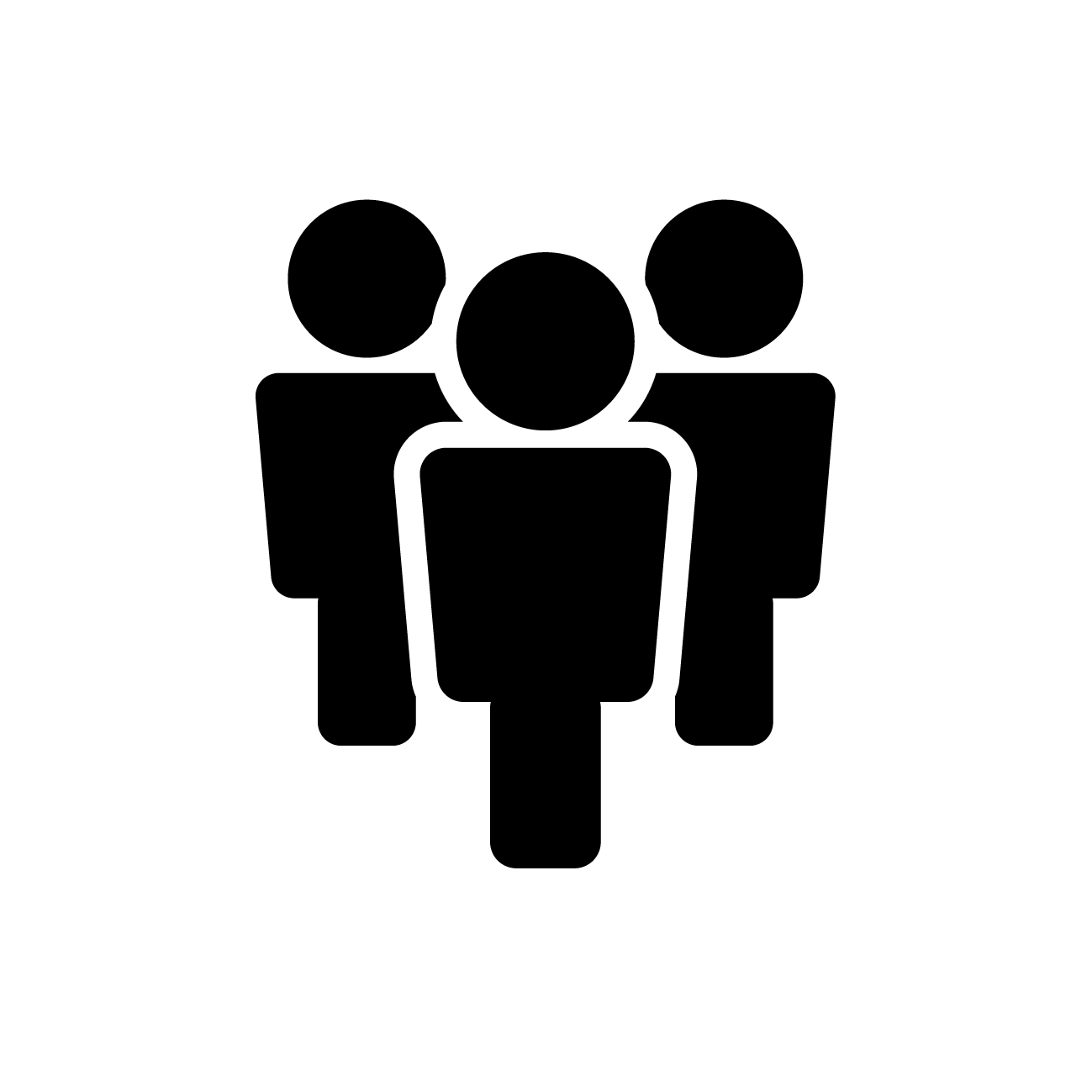
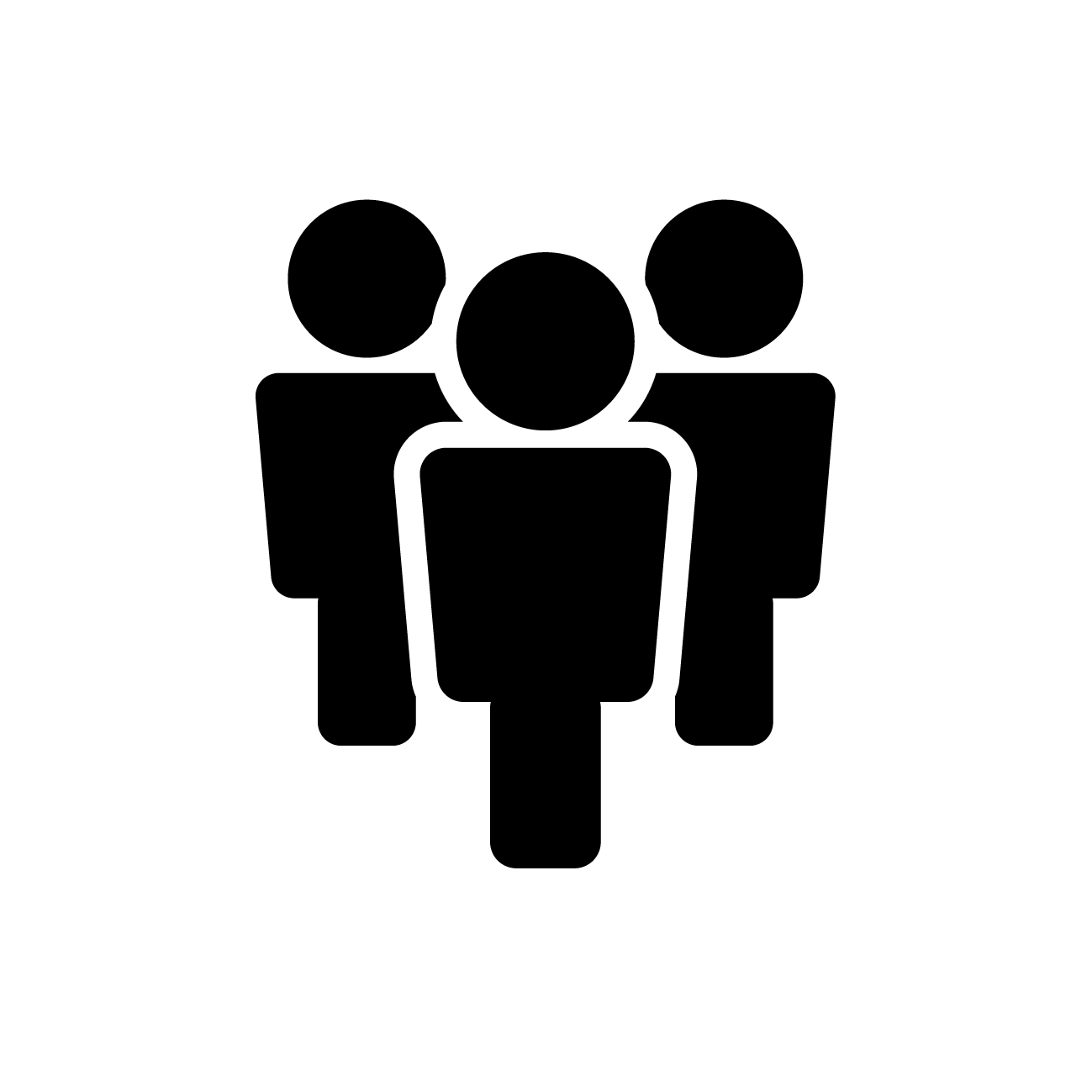
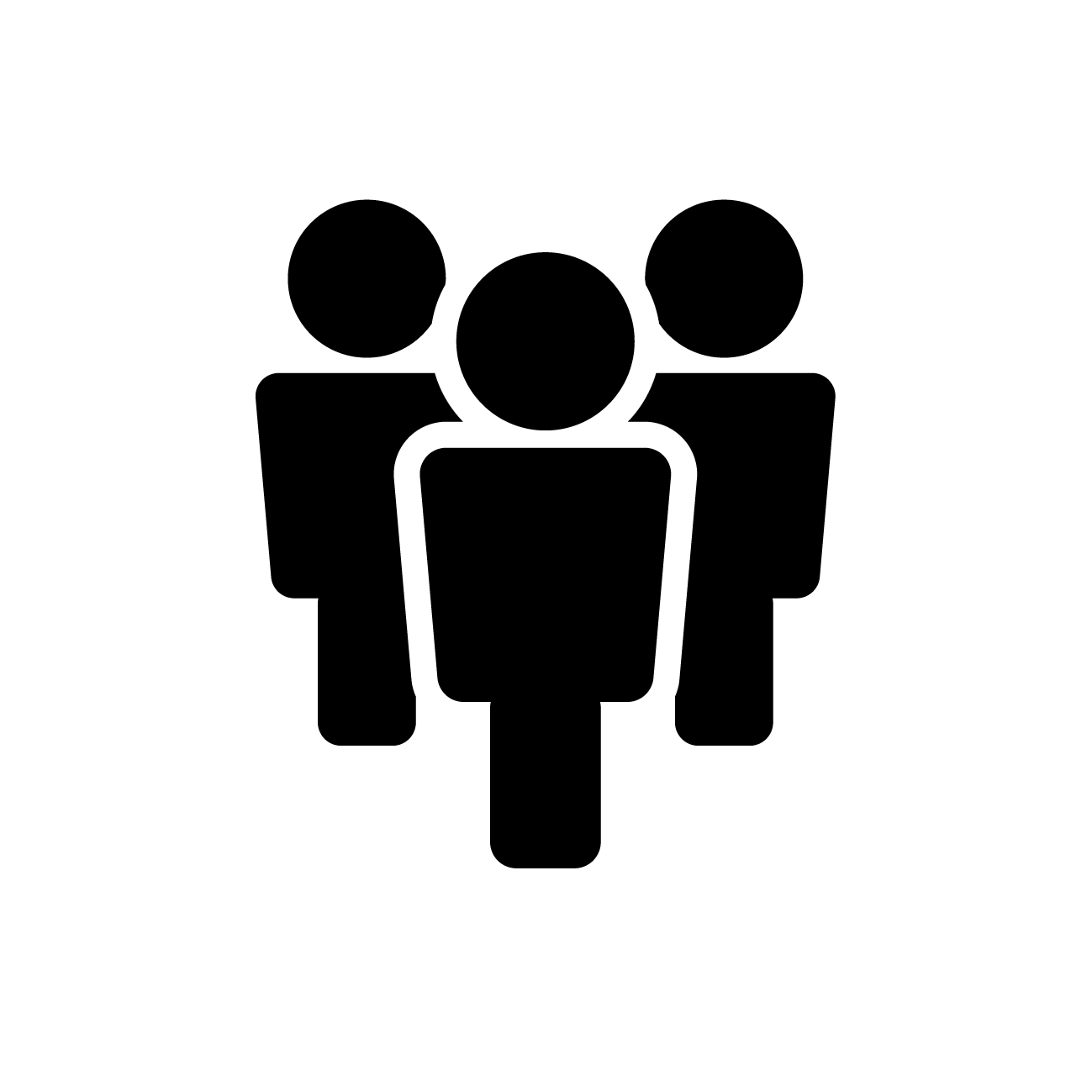
どうする?特別支援学校のセンター的機能強化のための定数改善
小、中学校、高等学校への特別支援教育の助言・支援等を行う「特別支援教育のセンター的機能」が、特別支援学校に課せられ、その機能を発揮していることは、特別支援教育に関わる教員の職務の特殊性や専門性にあたります。
しかし、特別支援教育の開始時からそのための教員配置は十分に行われておらず、特別支援学校の担任を削減するなどして特別支援教育コーディネーターを各校とも1名ないし複数配置している現状があります。
文部科学省の令和7年度予算の「特別支援教育のセンター的機能強化にかかわる教職員定数の改善」(拡充)という項目にかかわる、定数改善の人数と予算額を教えてください。
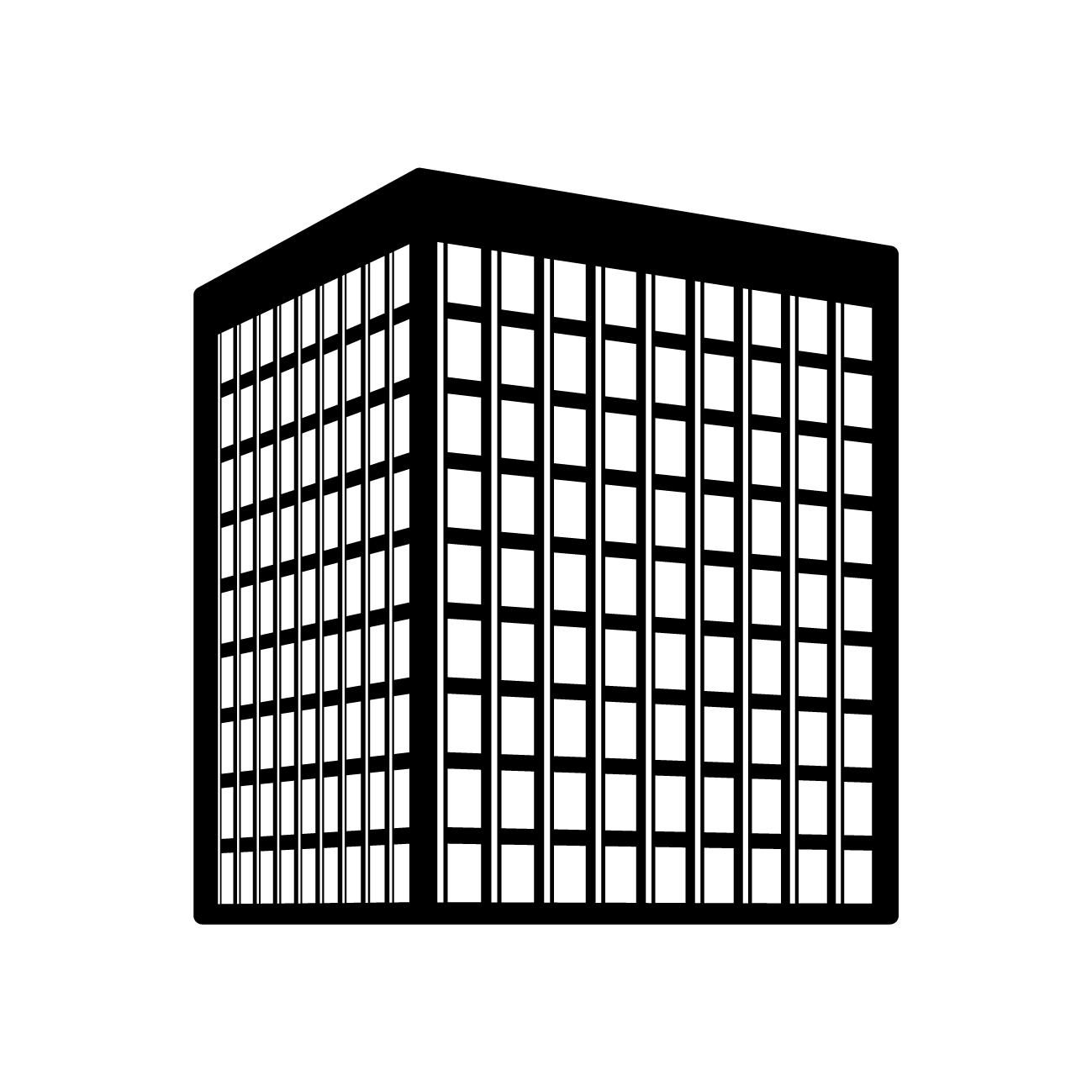
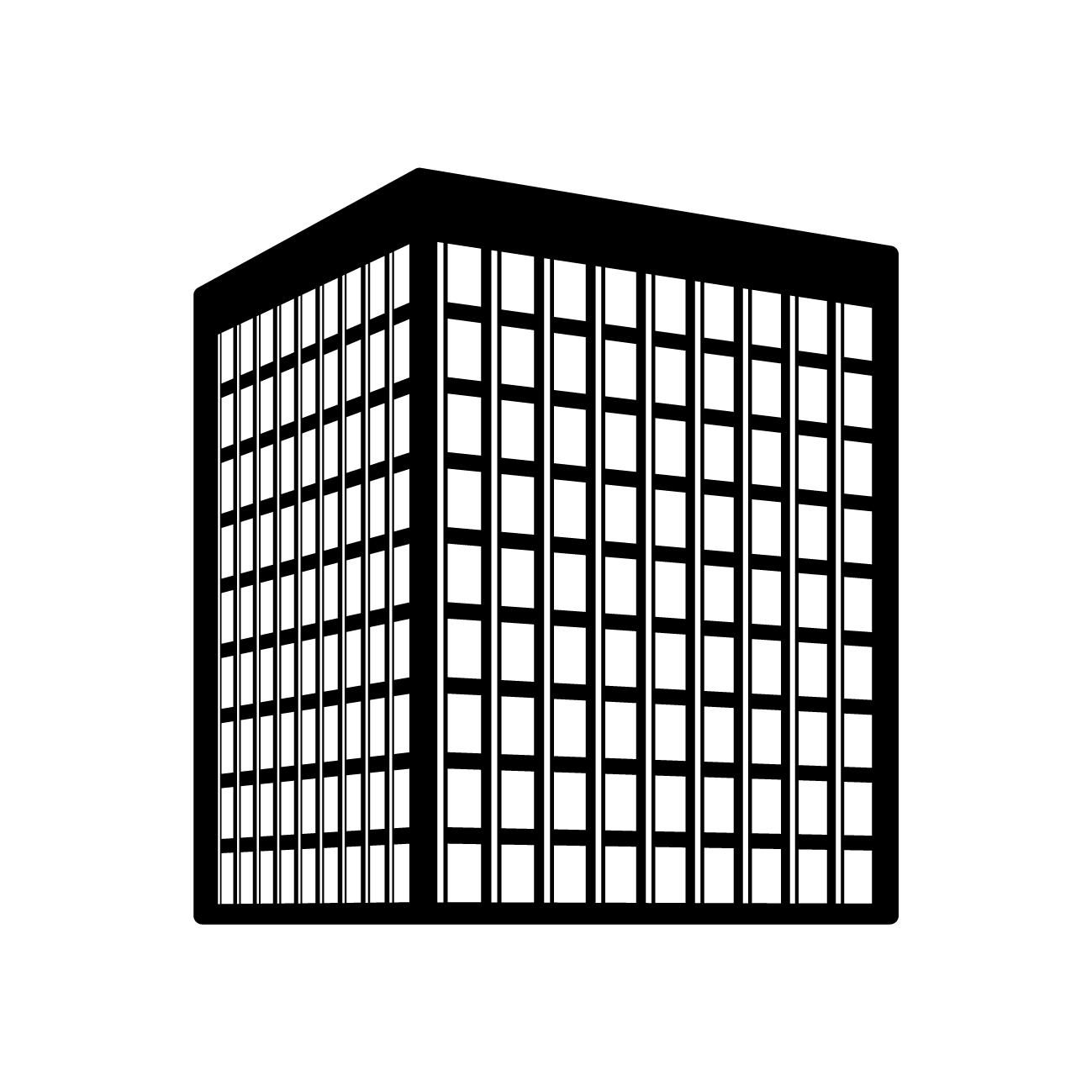
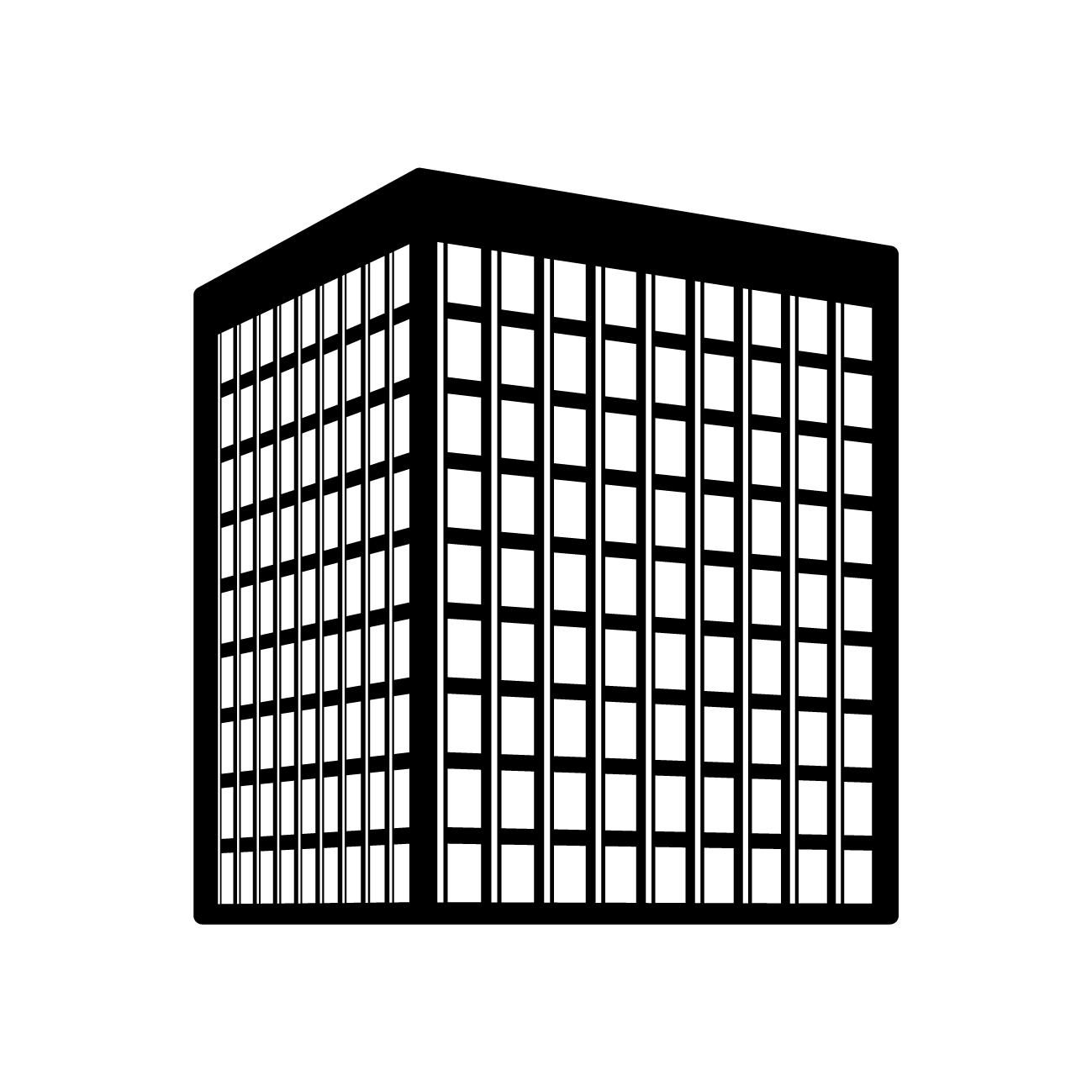
令和7年度の「特別支援教育のセンター的機能強化にかかわる教職員定数の改善」は100人分の予算を計上しています。なお、基礎定数ではなく「加配」として配置します。
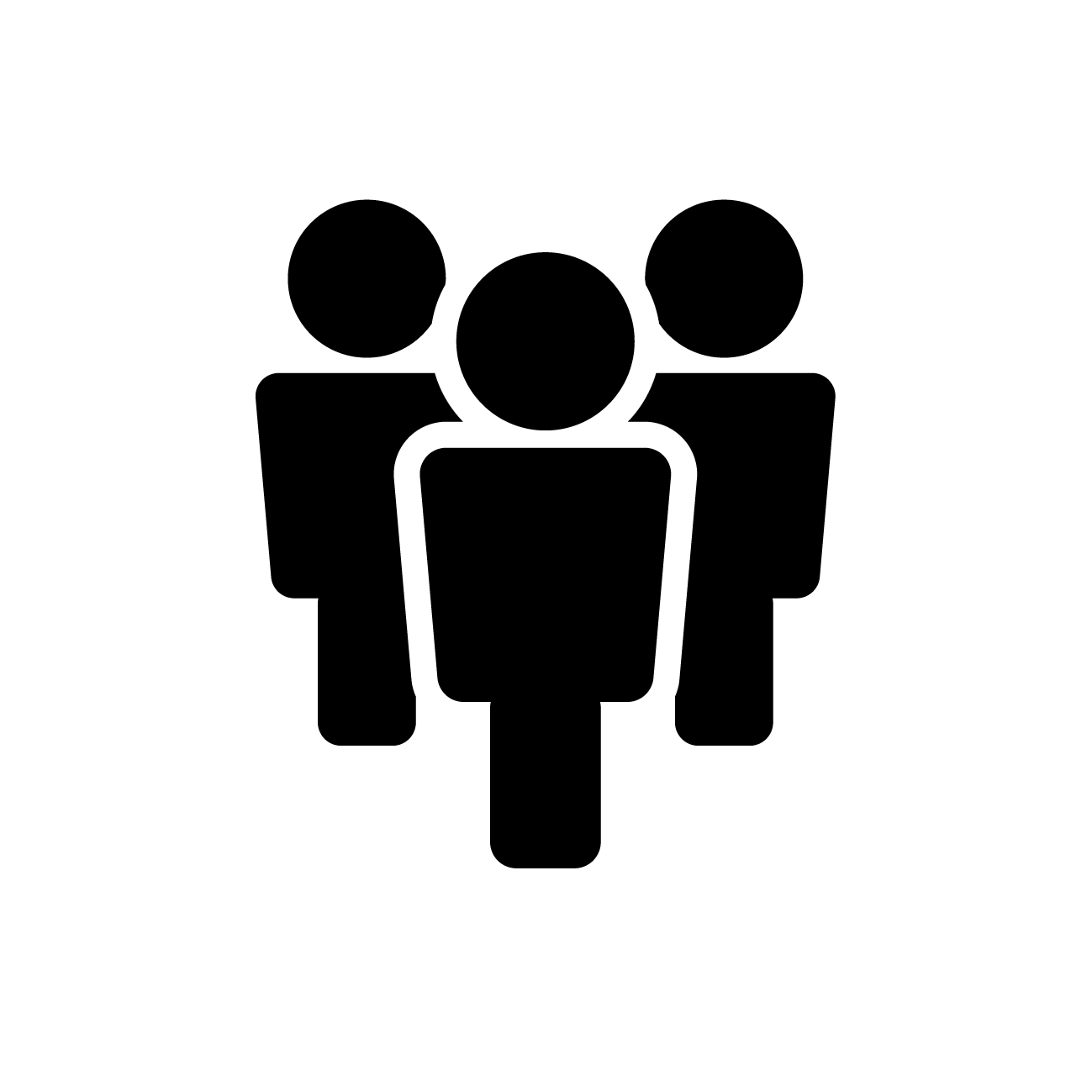
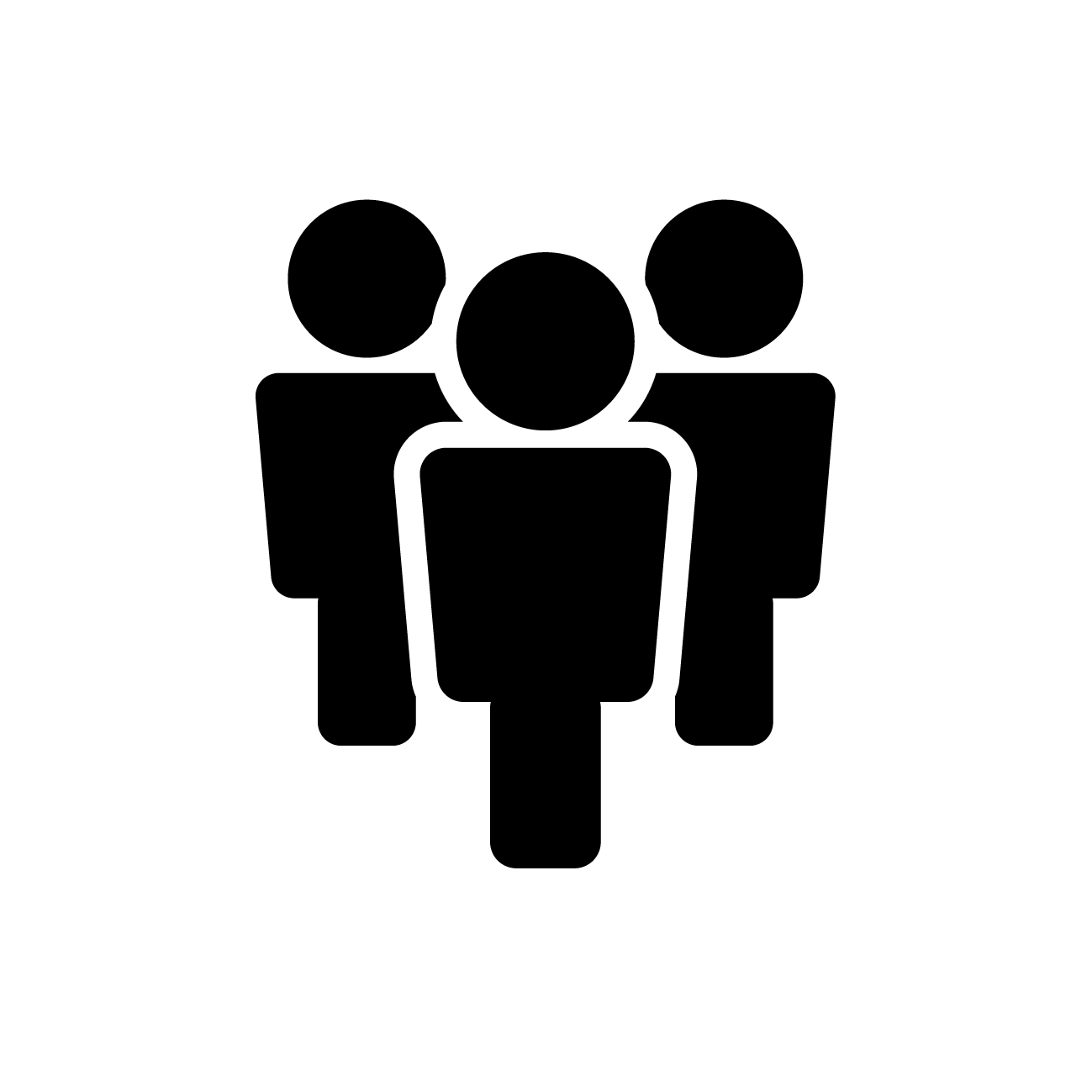
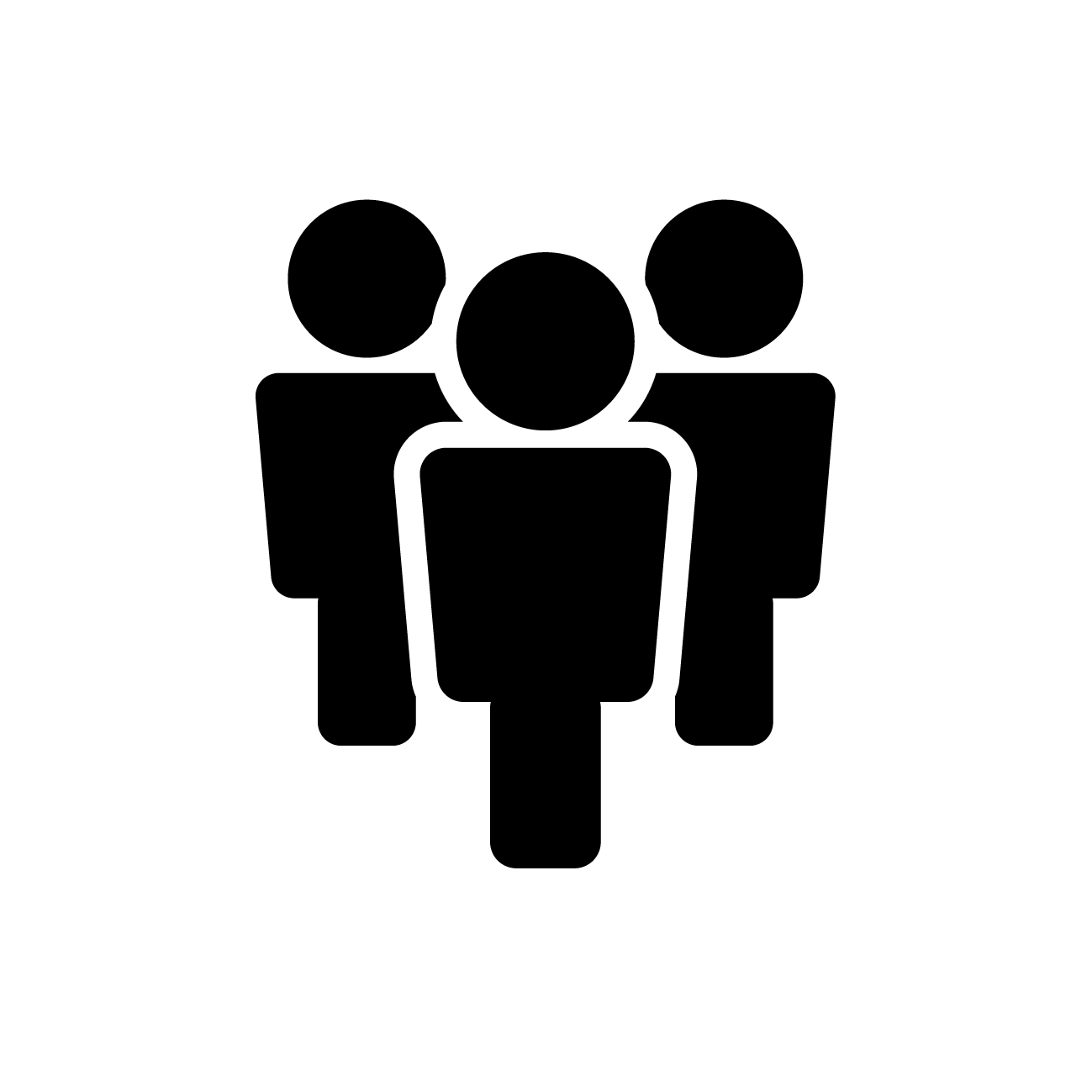
2024年度現在、特別支援学校は全国に1130校あります。
100人増やすということは1校あたり0.088人です。47都道府県で平均すると各都道府県あたり約2名です。
「特別支援教育のセンター的機能」を学校に課しておきながら、国による体制整備はあまりに不十分で無責任です。
保育所や幼稚園、小、中学校、高校の子どもたちへの支援、相談、助言件数は増える一方ですが、人も予算もつかないことにより学校現場の負担は増大するばかりです。