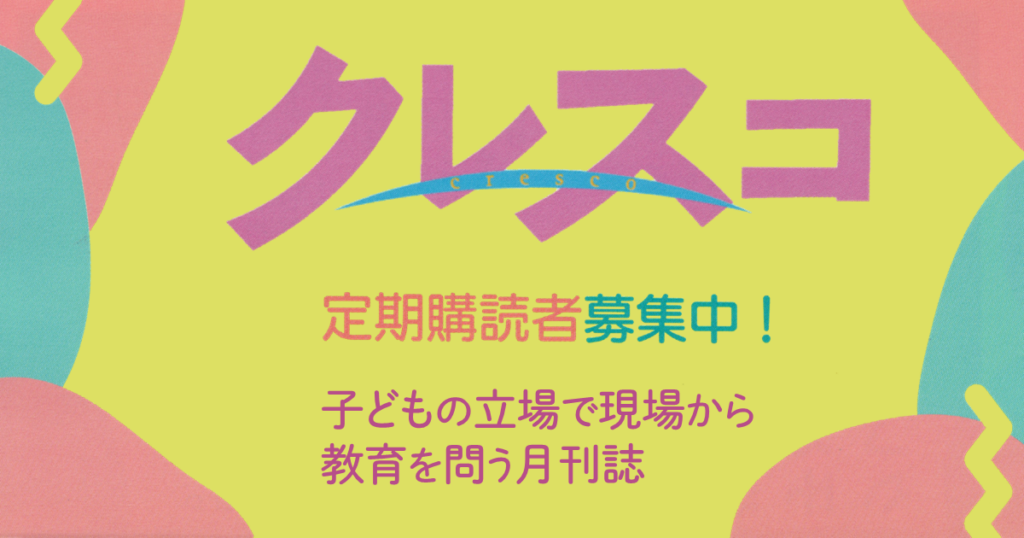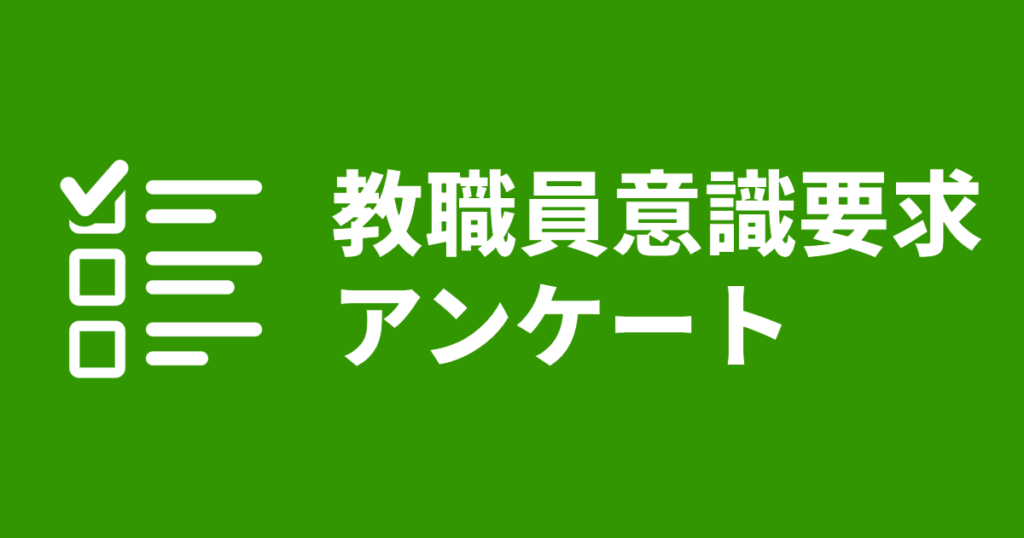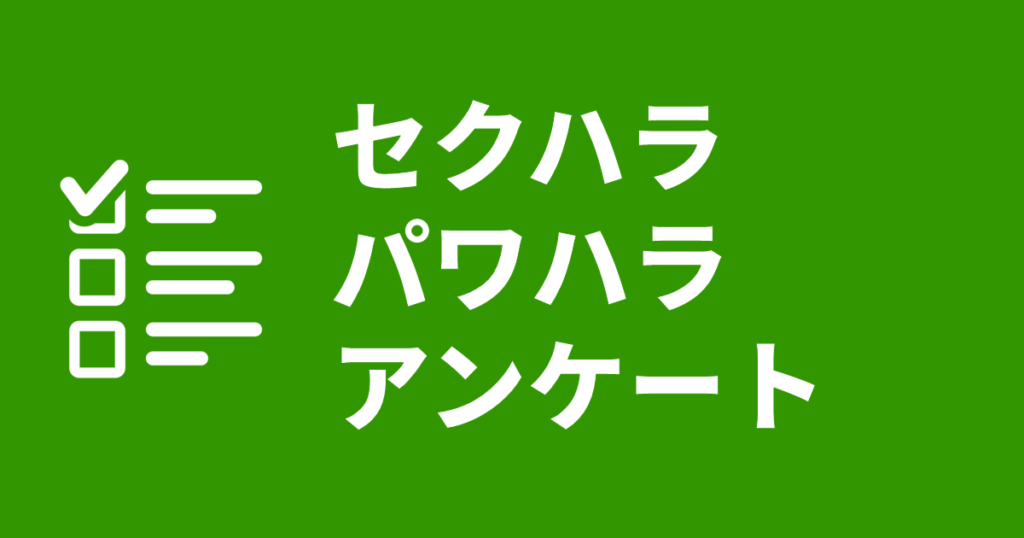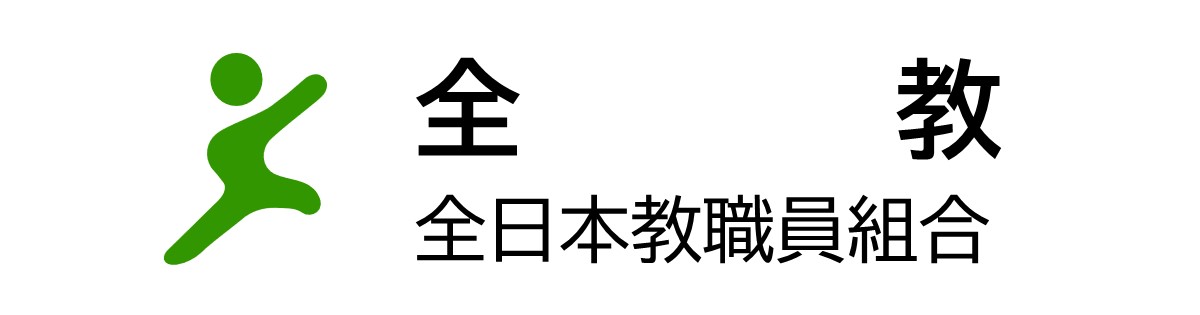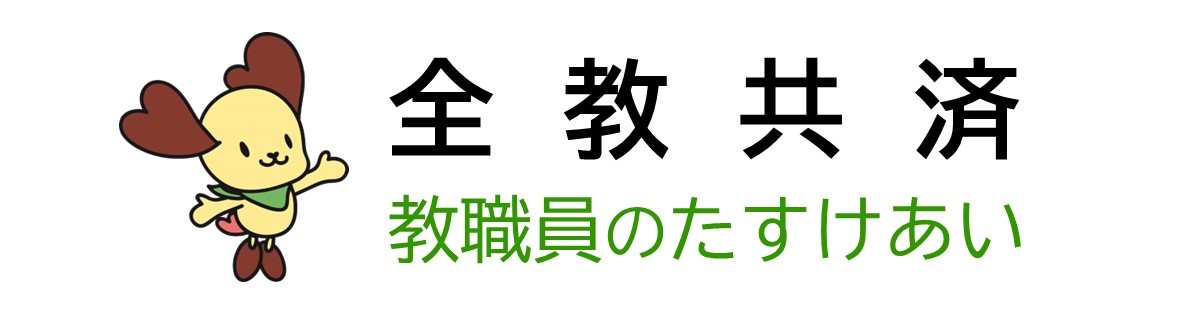全教(全日本教職員組合)は、1月8日、書記長談話『中教審への諮問「初等中等教育における教育課程の基準等のあり方について」について』を発表しました。
12月25日、文部科学大臣は中教審に対し「初等中等教育における教育課程の基準等のあり方について 」を諮問しました。(以下、「諮問」)
その中で、現状認識と課題意識を次のように示しています。
- 「学ぶ意義を十分に見だせず、主体的に学びに向かうことができていない子供」が多いのは「積年の課題でもある『正解主義』や『同調圧力』への偏り」が根本にあること
- 「自分の考えを持ち、根拠に基づいて他者に明確に説明すること、自律的に学ぶ自信がある生徒が少ないこと等に依然として課題」があること
- 「我が国のデジタル競争力は他国の後塵を拝しており、社会全体の生産性や創造性を高めていく観点からもデジタル人材育成の強化は喫緊の課題」であること
こうした認識がまったく的外れであるとはいえないものの、そのような状況をつくりだした文科省自身の総括と責任について言及がないことは問題です。学習指導要領の“しばり”が子どもや地域の実態をふまえた教育課程づくりを抑制し、厳然として学校に存在する「競争と管理」が文科省・教育委員会からの圧力と感じている学校・教職員は少なくありません。
そうした現状と課題に対して、「諮問」は次の4点について審議するよう中教審に求めています。
- 前回に引き続き「資質・能力」を中心にした学力観や評価の根本的な課題を見ようとせず、それを上書きするかのような検討を求めています。生成AIやデジタルを無批判に「利活用」することで子どもたちに深い学びを提供できるかのような幻想を与えていると言えるのではないでしょうか。
- 多様な子どもたちの存在が大きくなってきたことから、その対応を求められ、「多様な子供たちを包摂する柔軟な教育課程」について検討するとあります。その方向性は重要であるものの、その前提が「デジタル学習基盤」であり、子どもの成長と発達に寄り添った教育課程をつくるための環境整備を十分に位置付けていないことは問題です。
- 「情報活用能力」「探究的な学び」「生成AI」「文理横断・文理融合」「主体的に社会参画」など、内閣府総合科学技術・イノベーション会議「Society5.0の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ」が示した内容をなぞるものばかりで、経産省が主導する「教育政策」をますます強く押し出してきています。このような前のめりな議論を進めてよいのか、立ち止まって考えてみる必要があるのではないでしょうか。
- 「教育課程の実施に伴う過度な負担や負担感が生じにくい在り方」として学習指導要領や解説、教科書、入試、指導書の見直しが求められています。年間標準総授業時間数の在り方を取り上げ、時間数や受け持ちコマ数の削減を検討することも考えられるようですが、こうした課題が教員の働き方改革の観点のみから出されているのではないかと懸念されます。教員の働き方の改善とともに子どもたちの成長と発達に応じた教育課程・学習指導要領を考えるという原則から逸脱していないでしょうか。教員不足・教員採用試験受験者減だから教員の働き方改革をおこなわなければならない。だから、時数も減らす、行事も減らす、会議も減らす・・・という流れができているように思われますが、子どもたちの教育にとって一番大事なことが見過ごされているのではないでしょうか。
次期改訂学習指導要領は2026年度に答申されるようスケジュールされています。
まず、現状をよく見て、子どもたちの成長と発達に則った学習指導要領となっていない現状を改める上で何が必要なのか。現場から、そして子どもたちの声をよく聞いて、教職員や保護者の声も十分に聴き取ることが重要です。
全教は、今後の中教審の動向を注視し、大綱的基準の域を逸脱しない学習指導要領の策定を求め、要請や学習討議資料を作成し、広範な教職員や教育研究者、保護者、市民を視野に入れたとりくみを展開する決意です。