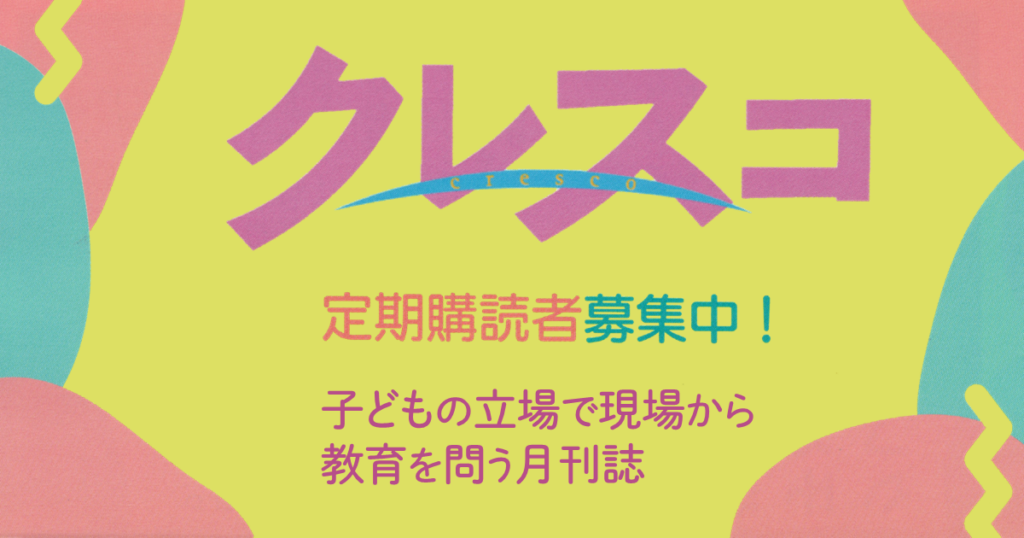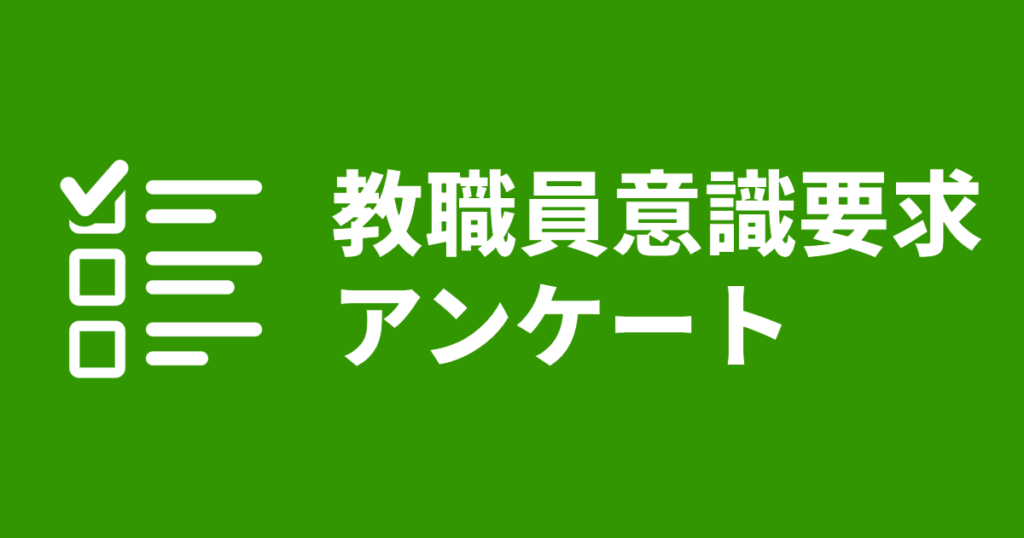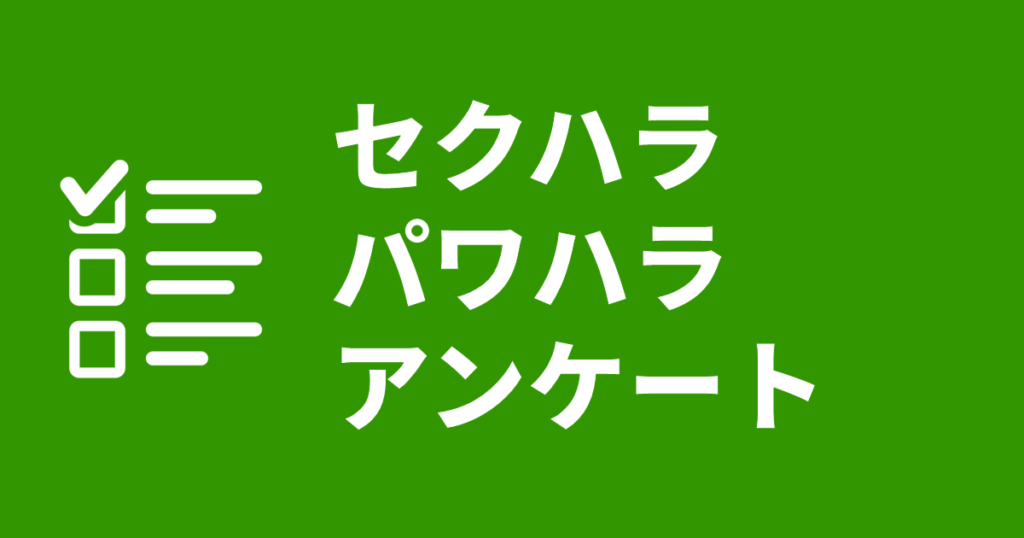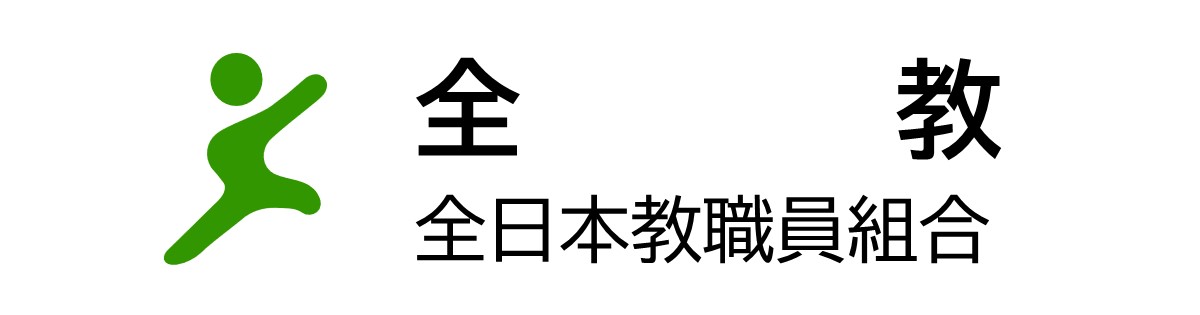全教(全日本教職員組合)「障教部ニュース1」より
給特法改正案の審議が始まりました。文科省は、現在、平均1.5%支給されている義務特手当を一律0.5%引き下げることにより、学級担任等の傾斜配分などの「処遇改善」の原資の一部にあてること、義務特手当の学級担任への加算について、特別支援学校および特別支援学級の担任は対象とはしないこと、さらに、2026年度以降、特別支援教育にかかわる 「給料の調整額」の削減を検討していることを明らかにしました。
この「給特法改正案」では、教職員の長時間労働解消の施策がないばかりか、1956年から障害のある子どもたちの教育に携わっている職員に支給されている「給料の調整額」(「教職調整額」のことではありません)の削減がねらわれており、大幅な「改悪」につながるといえます。
「給料の調整額」とは
「給料の調整額」は、特別支援学校・特別支援学級・通級指導教室担当の教員などの他にも、作業療法職員や福祉施設職員、特殊車両運転手など「職務の複雑、困難若しくは責任の度合又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件」が著しく特殊な職員に支給されているものです。これは給料の一部であり、「教職調整額」やボーナスにはねかえるだけでなく、退職金や年金算定の基礎になります。
「給料の調整額」は、1956年(昭和31年)から「心身の障害を持つ児童・生徒の教育をつかさどる、勤務の特殊性を考慮」して支給が始まりました。当時は本給の4%でした。
「行政改革」の名のもとに削減されてきた「給料の調整額」
2007年、2013年当時「行政改革」の名のもと「給料の調整額」は攻撃され、全国各地で削減反対の運動を展開しましたが、全廃や削減が強行され、今は給与額に関係なく一律の定額を対象者に支給している自治体が多いのが現状です(本給)。
中教審も攻撃する「給料の調整額」
通常学級にも障害のある子どもたちが在籍していることから、特別支援教育関連の教職員にのみの支給は不均等という理由で、中教審「質の高い教師の確保特別部会」においても「給料の調整額」の見直しについて言及されてきました。
「給料の調整額」を削減する合理的理由はない!
特別支援学校では、教職員の腰痛・頸肩腕障害、妊娠障害などの罹患が多く発生し、「職務の複雑、責任、勤務の強度、勤務環境」などの著しい困難を示す事例に事欠きません。
特別支援学級においても、全国的に障害の重度・重複化、多様化がすすみ、障害種別も年齢も発達段階も異なる最大8名の子どもたちの指導をたった一人の担任の努力に求めている学校は急増しています。通級指導担当は、年々増える子どもたちの指導に、放課後まで指導時間にあてているほど過酷な労働環境です。
さらに国の「特別支援教育」により、通常学級に在籍する様々なニーズを持つ子どもたちへの指導、援助などが、定数配置のないまま特別支援学校の責務とされ(学校教育法 74条)たために、特別支援学校の教員定数を削って(本来子どもたちの担任となる教員を減らして)コーディネーターを配置し、地域支援や小・中学校・高校などの特別支援教育の支援をおこない、特別支援教育のセンター的機能を担っています。 医療的ケアの子どもたちも増え、障害の重度・重複化の中で教職員に求められる専門性は一層増大し、子どものいのちの安全に関わるなど、職務は重くなってきています。
「給料の調整額」を削減する合理的理由はありません。「不均衡」をいうのであれば、通常学級で障害のある子どもたちの指導にあたっている教員にも同様に「給料の調整額」の名目のまま支給することが、整合性ある対応といえます。
特別支援学校と特別支援学級の担任には「学級担任手当」を支給しないのは差別的処遇だ
さらに義務特手当の学級担任への加算について月3000円程度が想定されていますが、この学級担任手当においても、特別支援学校および特別支援学級の担任は対象にしないというのが「給特法改正案」の立場です。このように職場を分断する「学級担任手当」等の傾斜配分導入には反対します!
私たちは「主務教諭」という「新たな職」を創設しないこと、義務教育等教員特別手当の学級担任など一部の教員への傾斜配分はしないこと、「給料の調整額」を削減しないことを求めます。