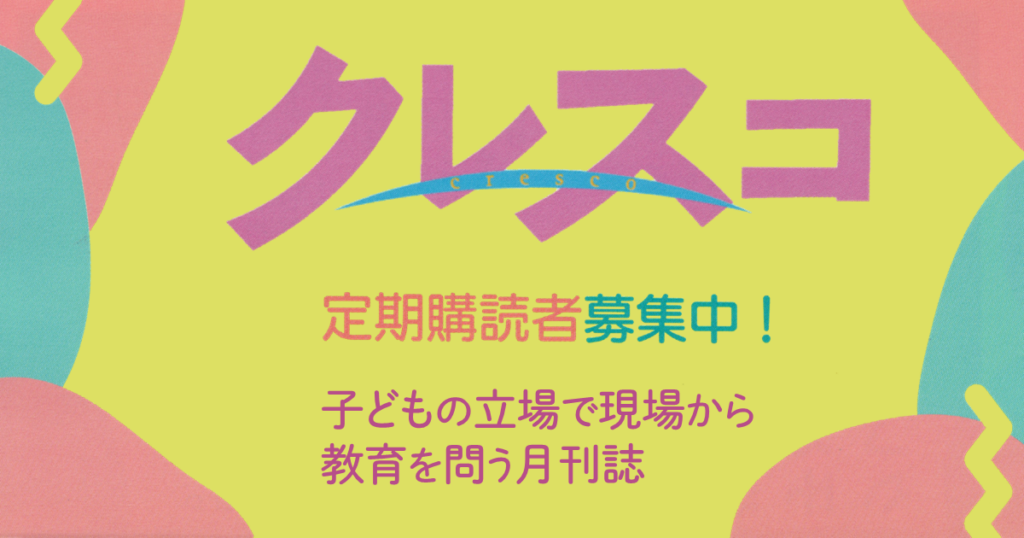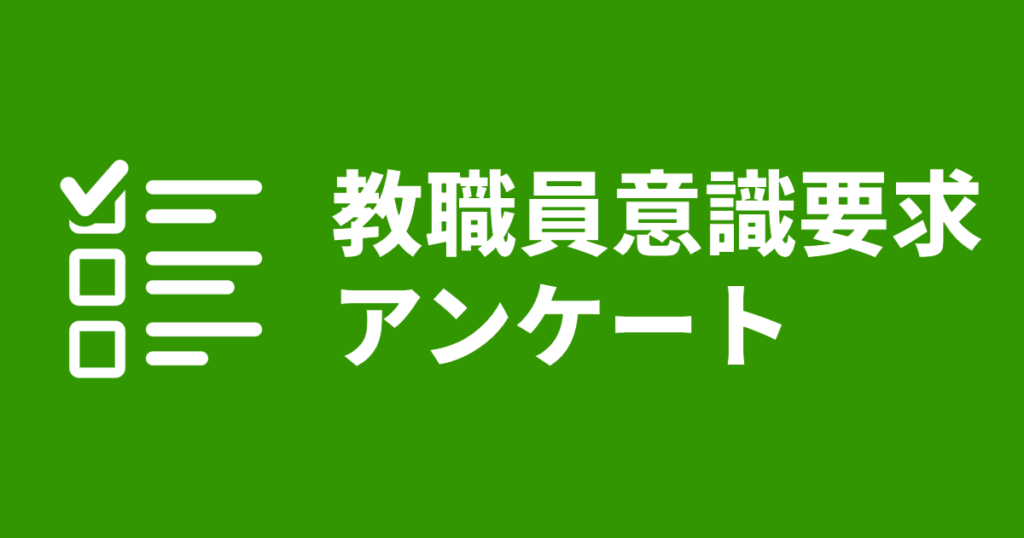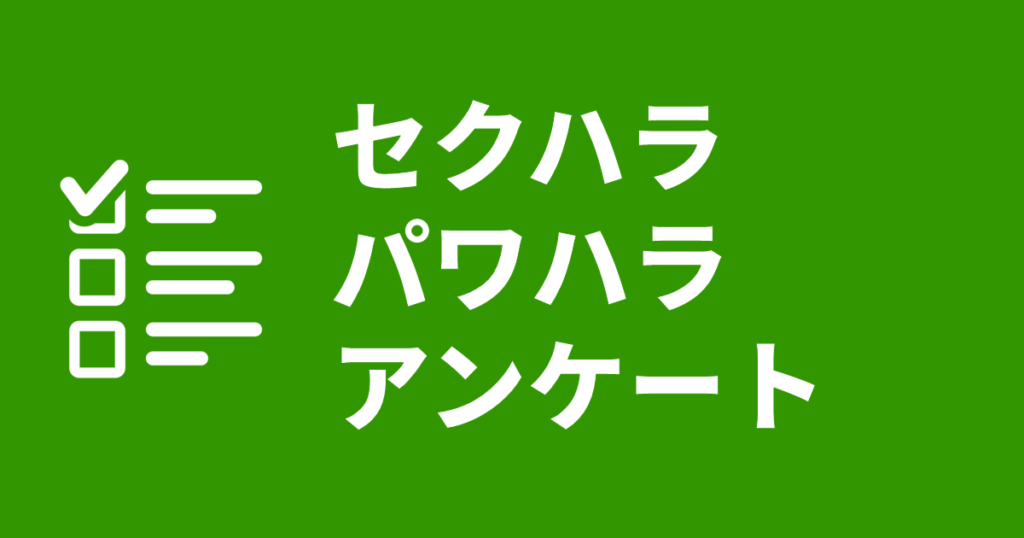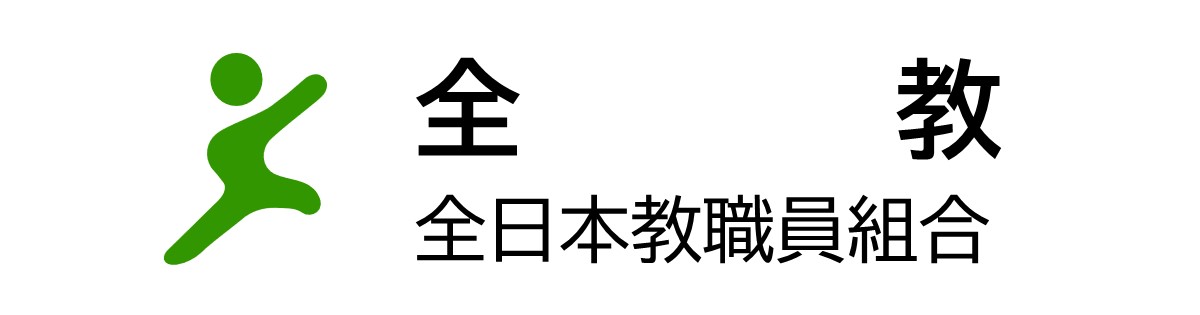スポーツ庁では表記の部活動改革に関する実行会議で、中学校部活動の地域移行について議論をすすめています。
実行会議は、2024年12月18日に中間とりまとめを発表し、全教に対しても意見書の要請がありました。これをうけ、2025年1月30日、中間とりまとめに対する意見書を提出しましたので紹介します。
はじめに
2023年度から「部活動改革推進期間」が始まり、「できるところから」中学校の土日部活動が地域に移行されることになりました。この中学校部活動の地域移行は、2019年の給特法一部改正の際、衆参両院附帯決議に明記された「教職員の負担軽減を実現する観点から、部活動を学校単位から地域単位の取組とし、学校以外の主体が担うことについて検討を行い、早期に実現すること」から、具体化がスタートしました。
全教は、
- 子どもたちのスポーツ・文化を享受する権利を実現する、
- 教職員の「働き方改革」を実現する、
という2つの視点から、学校部活動の地域移行のあり方を検討してきました。以下、全教としての意見を述べます。
1.実行会議に学校の関係者が1人しかおらず、学校部活動のことに目が向けられていない
実行会議ワーキンググループのメンバーを見ると、学校の関係者は校長会の代表が一人であり、これまでの部活動を担ってきた学校現場の課題や願いを反映させる議論ができたのか、地域移行完了までの学校部活動のあり方や学習指導要領における取扱いに向けた議論などもふくめ、今後、議論をすすめるにあたり、当事者である教職員の代表が入ることを強く求めます。
2.子どもにとっての部活動の意義を維持するための「改革」であるべき
全教は以前から、学校における部活動は、子どもの文化・スポーツ要求に根ざした、興味・関心にもとづく自主的活動であり、その活動と仲間のふれあいが、人間としての成長・発達に寄与するものだと指摘してきました。
すべての中学生において改革の理念に書かれている、スポーツ・文化芸術に内在する教育上の意義は尊重されるべきです。中学生のみならず全ての人々のスポーツ・文化芸術活動の充実に繋げていくという視点を重視するのであれば、生徒・保護者だけでなく、国民的理解を深めるためのとりくみを加えることが必要です。また、3頁の注6に、部活動の総合的なガイドラインにかかわる記述がありますが、残存する部活動や地域移行された活動の具体的な指針として、脚注でなく本文に掲載すべき重要な事柄があると考えます。
3.「地域クラブ活動」の実施状況の分析と対応策が書かれていない
「2.改革推進期間の成果と課題」では、「実証事業」等の成果や具体的にすすんでいる例が書かれていますが、多くの地方では地域移行がうまくすすんでいません。その記述こそが重要で、すすまない困難性や課題についての十分な分析を行った上で、課題解決のための具体的な解決方策等を示さない中で、「3.今後の解決の方向性」「(2)改革の進め方」を論じるには無理があります。
「(4)次期改革期間における費用負担の在り方等」について、受益者負担と公費負担とのバランス等の費用負担の在り方等を検討する必要があるとしていますが、全国町村会の伊藤委員の提出意見にあるように、すべての中学生を対象に改革の理念を広く浸透させるためには、受益者負担に依存するのではなく、可能な限り「公費負担」を原則とするべきです。
4.国民の文化・スポーツ要求に応えるための国の責任を明確に打ち出すべき
この改革を機に、中学生のみならず全ての国民の文化・スポーツ要求にこたえるための施策を各地域ですすめていくためには、国が十分な予算措置をとって、各自治体のとりくみを支援することが不可欠です。
地域移行にあたり、指導者の確保をはじめ、条件整備等に係る予算確保等のさまざまな課題が地域に丸投げされ、対応できない状況が指摘されています。それぞれのワーキンググループの議論でも、先進的なとりくみを行っている担当者をはじめ各委員から「財政上の支援」の必要性が語られています。しかし「中間とりまとめ」は、地方自治体に「要望」「期待」する記述ばかりで、「国として」の予算措置についての施策の提示はありません。「企業版ふるさと納税やガバメントファンディングをはじめとした寄付等の活用」との記述は、国の責任を放棄した無責任なものであり、撤回すべきです。
5.「次期改革期間の設定」について
次期「改革期間」については、前期3年間(2026年度~2028年度)と後期3年間(2029年度~2031年度)の計6年間を設定するとしています。一方で、「学習指導要領の次期改訂期にあわせて、学校部活動と地域クラブ活動に関する記載の在り方を検討する」としています。
先般、中央教育審議会に学習指導要領の改訂に関する諮問が行われ、その際、次期学習指導要領は2030年度から本格実施(中学校は2031年度か)と報道されており、「改革期間」の最中に学習指導要領の改訂が行われることになります。この点の齟齬はないのか。
また、活動が地域展開された際の地域クラブと学校との連携の在り方を明確にすることが必要です。現場の負担が軽減され、教員が本来業務に専念できる環境の実現が重要であると考えます。
6.高等学校における部活動への円滑な接続について
学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインでは、「ガイドライン策定の趣旨」として、「『Ⅰ 学校部活動』については、高等学校段階の学校部活動についても本ガイドラインを原則として適用する」とされています。高等学校における学校部活動も視野に入れた改革を示すべきです。
「中間取りまとめ」前文では、「今後の中学校における改革の進展を踏まえて必要な見直しの議論が行われることを期待する」とありますが、本改革の理念はさらに広く共有される必要があります。次期改革期間における高等学校への改革の方向性をメッセージとして発信する必要があると考えます。
7.「各論」の検討内容の提示がない
12頁に示された8項目の「各論」に関する検討内容の提示がないことは、重大な問題です。ここに例示されている課題こそ、これまでの「改革推進期間」のとりくみを踏まえて十分に検討されなければならない事項であり、その検討についての意見聴取を経ないで「最終とりまとめ」が行われることがあってはならないことだと考えます。
総じて、2019年の給特法一部改正の衆参両院附帯決議に明記された「教職員の負担軽減を実現させる観点」の視点が見えません。勤務時間内で終えることができる学校部活動のあり方や、現時点の調査で地域スポーツクラブ活動指導者の60%以上が教員の兼職兼業で成り立っていることから、指導を望まない教師の兼職兼業が生まれないための方策や、兼職兼業における勤務時間を正規の勤務時間に通算し、上限規制の範囲内に収めることなど、検討すべき課題は山積しています。
「各論」の内容に対する意見聴取を行うことを強く求めます。