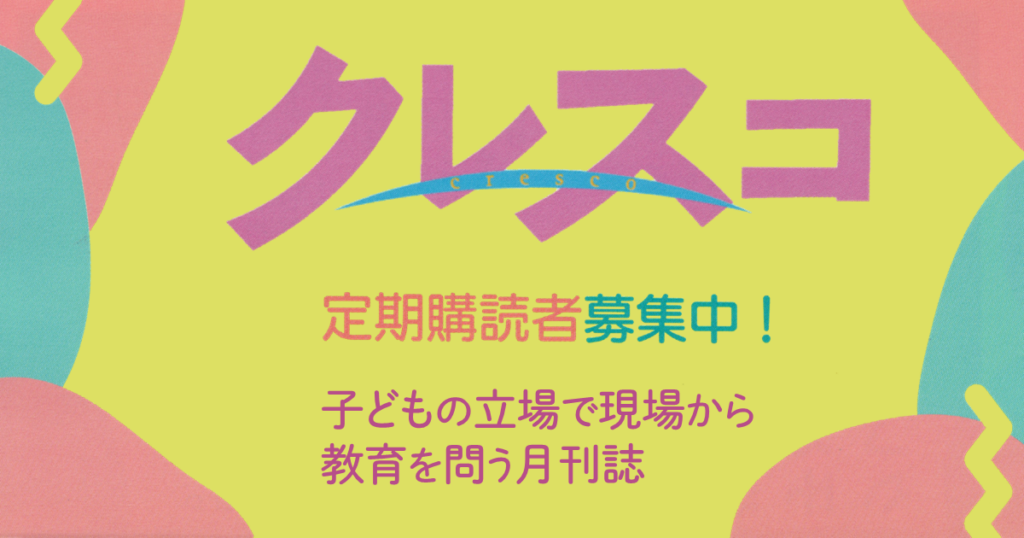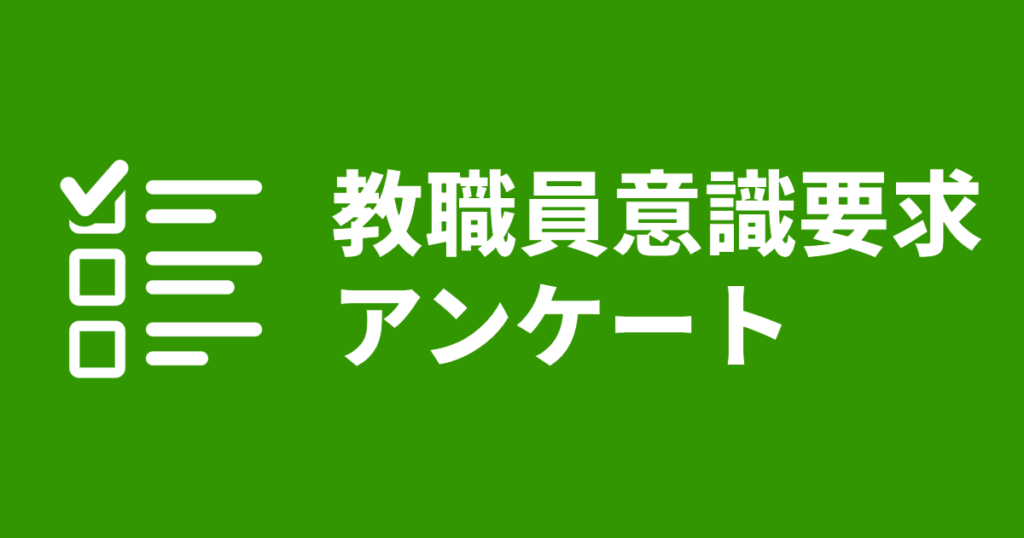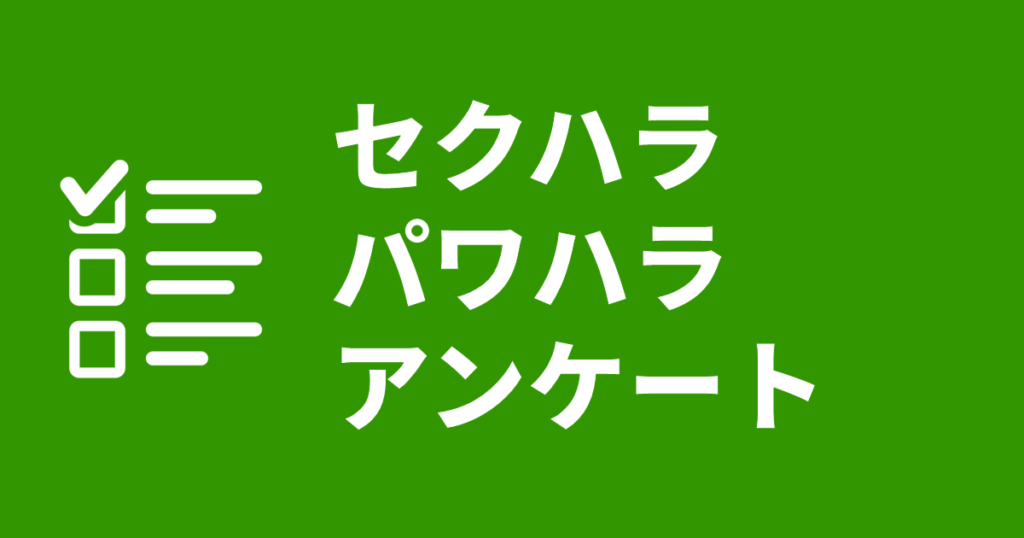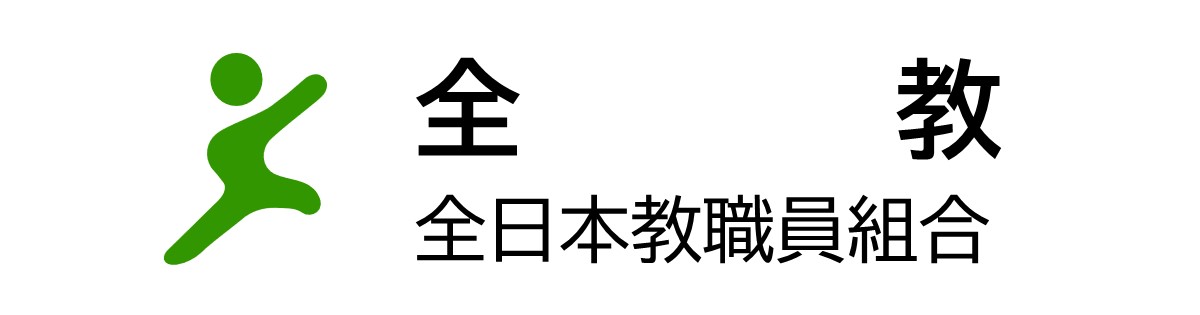人事院が2023年8月7日におこなった人事院勧告 に対して、全教は中央執行委員会声明を発表しました。
- 人事院は本日、一般職国家公務員の勤務時間及び給与の改定についての勧告・報告、公務員人事管理に関する報告を、内閣総理大臣と両院議長に対しておこないました。
- 職種別民間給与実態調査の結果にもとづき、今年4月における官民較差は、民間給与が国家公務員給与を3869円(0.96%)上回っており、人材確保の観点等を踏まえ若年層に重点を置き(高卒初任給1万2000円、大卒初任給1万1000円の引き上げ)ながら、再任用職員をふくむすべての号俸にわたる俸給表の改定をおこなうこととしています。一時金については、昨年8月から今年7月までの民間の支給割合が4.49月であるとして、現在の4.40月分を0.10月分引き上げ、引き上げ分は、期末手当及び勤勉手当に均等に配分することとしています。また、テレワーク中心の働き方をする職員について「在宅勤務手当」(月額3000円)を新設しました。
- 給与カーブのフラット化や能力・実績主義の更なる強化がねらわれているもとで、1997年以来の高水準の俸給表の改定、すべての号俸にわたる俸給表の引き上げ、一時金の引き上げ分の期末手当への配分がおこなわれました。これは、2023国民春闘のたたかいにおいて、公務労組連絡会が「物価高騰に対応する緊急勧告を求めるとりくみ」をおこない、全教として500を超える職場・団体決議を提出したこと、また、官民一体の社会的賃金闘争の強化としてとりくまれた「物価高騰から生活を守る大幅賃上げを求める署名」を全教として昨年度より1万筆以上上回る2万9825筆を提出したことなどにより賃上げ世論をつくりだしてきた私たちの運動の成果です。
しかし定期昇給分を加えても、月収で約2.7%、年収で約3.3%にとどまる給与改善は、前年同月比3.5%の上昇となった4月の消費者物価指数(総務省発表)と比べても、生活改善にはつながらない全く不十分な内容です。長時間におよぶ労働で必死に奮闘している公務労働者・教職員の労苦に報いるものとはなっておらず、労働基本権制約の代償措置として十分な役割を発揮していない勧告に、強く抗議するものです。 - 諸物価高騰が国民生活を苦しめています。今こそ岸田首相の言う「物価高を上まわる公的セクターでの賃上げの実現」が求められます。中央最低賃金審議会による今年の最低賃金引き上げ目安額は、昨年の物価上昇分を配慮し、過去最高の加重平均41円の目安額を決定しました。これにより最低賃金の全国加重平均は1002円となりますが、今回の俸給表改定後も国家公務員の高卒初任給は依然として多くの地域で最低賃金を下回っています。公務員賃金は900万人以上の労働者の賃金水準と連動し、地域経済にも大きな影響を与えます。疲弊した地域経済を活性化させるためにも、政府の責任で公務員賃金を政策的に引き上げ、深刻な地域間格差、正規と非正規の賃金格差解消を図り、経済の立て直しに踏み出すべきです。勧告の取り扱いについて、物価上昇に対応できる賃金引き上げを公約どおり実現することを強く求めるものです。
- 今年は例年にない「職員の勤務時間の改定に関する勧告」が出されました。内容は、2025年4月1日から一般の職員についても、フレックスタイムの活用により、勤務時間の総量を維持した上で、週1日を限度に勤務時間を割り振らない日(「ゼロ割り振り日」)を設定可能にするというものです。勤務時間の総量維持ということから、「ゼロ割り振り日」以外の勤務は、8時間労働の原則が破壊され、長時間労働や連続勤務が強いられるなど、労働安全衛生の面から課題があります。長時間過密労働が蔓延する学校現場では、健康・安全への影響、生活リズムの破壊や持ち帰り仕事の増加などが懸念されます。
- 「公務員人事管理に関する報告」では、公務人材確保の危機的な状況を背景に「給与制度のアップデート」にかかわる今後の措置について報告されました。地域手当の給地区分の設定を市町村単位から広域化すること、再任用職員について職務関連手当に限定されている現状から支給範囲を拡大するなど、私たちが要求してきた内容も一定含まれていますが、「人材確保への対応」「個々の成長を通じた組織パフォーマンスの向上」「働き方やライフスタイルの多様化への対応」という3つの課題について、2024年に向けて必要な措置を検討するとしています。その中心的なねらいは、メリハリある給与処遇等の推進という徹底した能力・実績主義の強化であり、断じて容認することはできません。また、65歳までの連続的な給与カーブについては見送られました。
報告は、人事院のおこなった各府省アンケートから恒常的な人員不足の理由として定員の不足が挙げられていることにふれ、「必要に応じ定員管理を担当する部局にお願いする」としていますが、政府の定員削減計画の見直しに言及していません。教育現場と公務職場で業務量に見合った定員確保に向けた政策転換を求めるとりくみを強化していくことが必要です。 - 今後、各地で人事委員会に対し、実質賃金引き上げにつながる勧告を求めるとりくみがすすみ、確定闘争がスタートします。深刻な教職員不足を解消するためには、教員の待遇改善は待ったなしの課題です。再任用職員や会計年度任用職員をふくむ臨時・非常勤教職員の待遇改善、ハラスメントの根絶、妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援の前進など、教職員が生活の不安なしに、力を合わせ、子どもたちの教育に専念できるよう、待遇改善を地方教育委員会にあらためて求めるものです。
全教は、新自由主義的政策から憲法が生きる社会への転換をめざし、給特法の改正と教職員定数の大幅増員とともに長時間過密労働の解消、能力・実績主義賃金の拡大を許さないたたかいに引き続き全力を挙げる決意です。