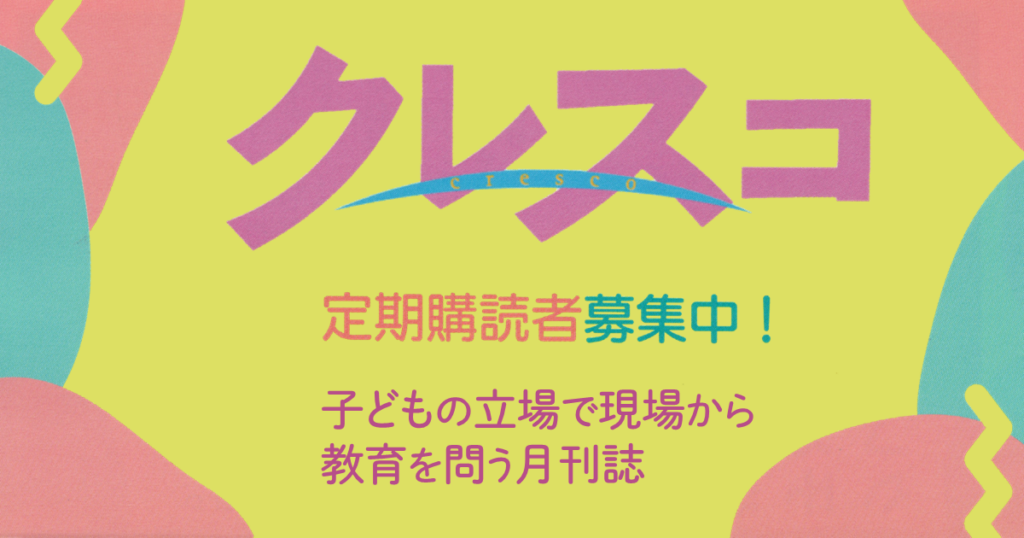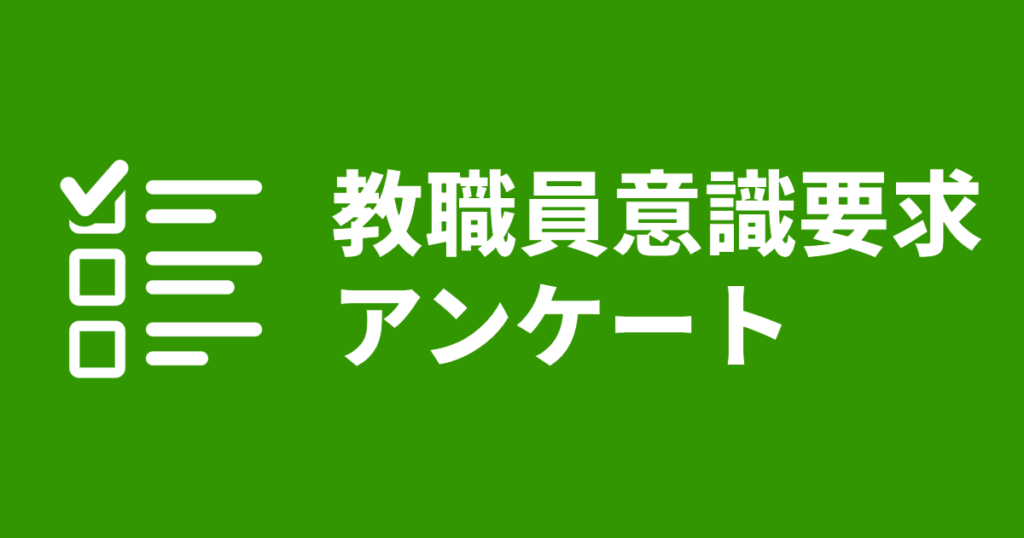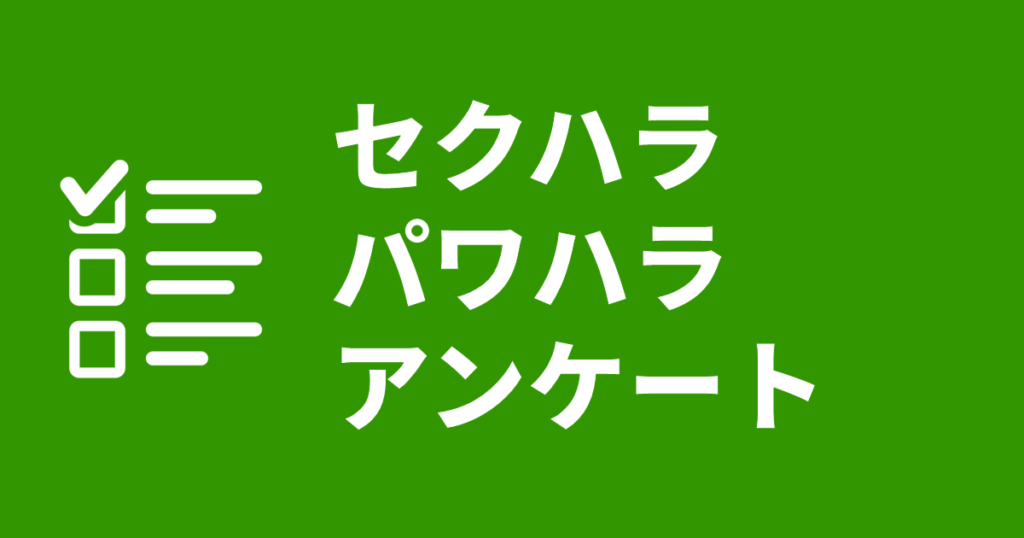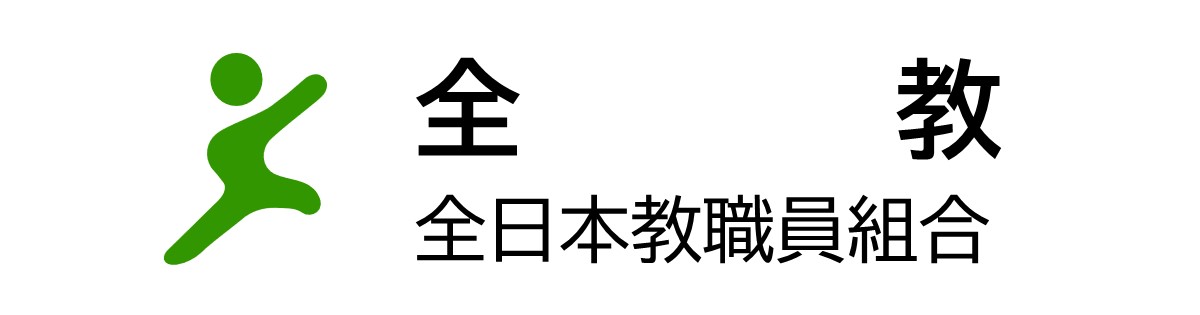全日本教職員組合(全教)栄養職員部が令和7年度農林水産関係予算をどう見ているかを紹介します。(栄養職員部ニュース No.247より)
掲載内容に関するお問い合わせは、全日本教職員組合 栄養職員部までお願いします。
総論
気候変動、世界情勢に関わる食料供給の不安定、円安による物価高騰、不景気及び就業困難等を背景に、食の多様化・食の貧困により様々な健康課題が子どもたちに押し寄せ、家庭・地域・行政の深刻な問題となっています。
「令和の米騒動」に象徴される国の農業政策の問題も加わり、給食内容の維持も難しくなる中で、児童生徒の心身の成長発達を保障する学校給食の役割が見直され、給食無償化の運動が広がっています。また、急速な経済変化や情報処理科の中で、心への影響に関わって「何を」に加えて「どのように」食べるのかが問われ、心を育む給食の役割が大きくなっています。
作られた製品として口にするのではなく、「地球にも体にも安全で安心な食べ物」を「食べ手を思い調理された食事」として受け取り、「自分と人とのやり取りの中で味わい自己を育む」営みにより食事観を育むことが大切と言えます。安上がりではなく、人間的発達を保障する「教育としての食育」がかつてなく保護者・地域・行政で求められています。
各論
- 学校施設整備費は、教育予算全体のわずか1.3%であり、改善交付金として扱われるに留まり、喫緊の課題である衛生管理改善が後回しになっています。児童生徒の命に直結する給食調理に従事する者の労働安全衛生と共に、切実な現場の実態を示しながら、給食内容充実に向けてさらに強く要求します。
- アレルギー対応に配慮し、学校給食の安心・安全の確保のため、十分選択した食品による献立作成、食べ手の児童・生徒が作り手とつながる自校直営方式の実施、放射線測定のきめ細かい体制と予算措置など、環境に配慮した教育的な学校給食の充実めざした条件整備が求められています。
- 「何をどう食べるのか」を学校給食作成の根幹に位置づけ、生きた教科書としての献立作成を担う業務の専門性の重要性が正当に評価されることが求められています。健康課題対策や食の指導の予算増に関わり、食育がまさに一人ひとりの課題となる中、専門的に担う栄養教諭の配置は、担任と連携し推し進めるためにますます重要となっています。今こそ、「一校一名の栄養教諭・学校栄養職員の配置と複数配置」をすすめ、全国の各学校で、学校栄養職員・栄養教諭が中心に、食育を進められるようにと考えています。
- 『食料・農業・農村基本法 』に合わせ、『食料安全保障の強化』が強く打ち出され『スマート農業技術活用促進』が加速されています。地場産・国産の食材の確保に向け予算減の課題を取り上げていくとともに、「環境負荷低減や気候変動に対応する新品種・技術の開発」のもとに進められる、遺伝子組み換え・ゲノム編集食品・培養肉・RNA農薬などの安全性の問題について学習し、学校給食とつながり、家族型生産制につながる産直運動を全国でとりくみ、国内農業を支え、食料自給率向上をめざします。