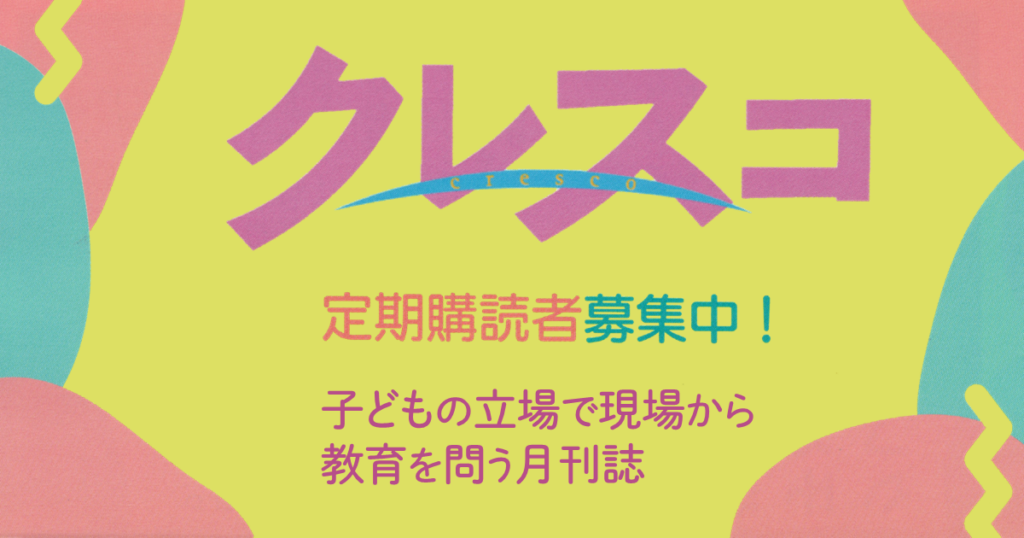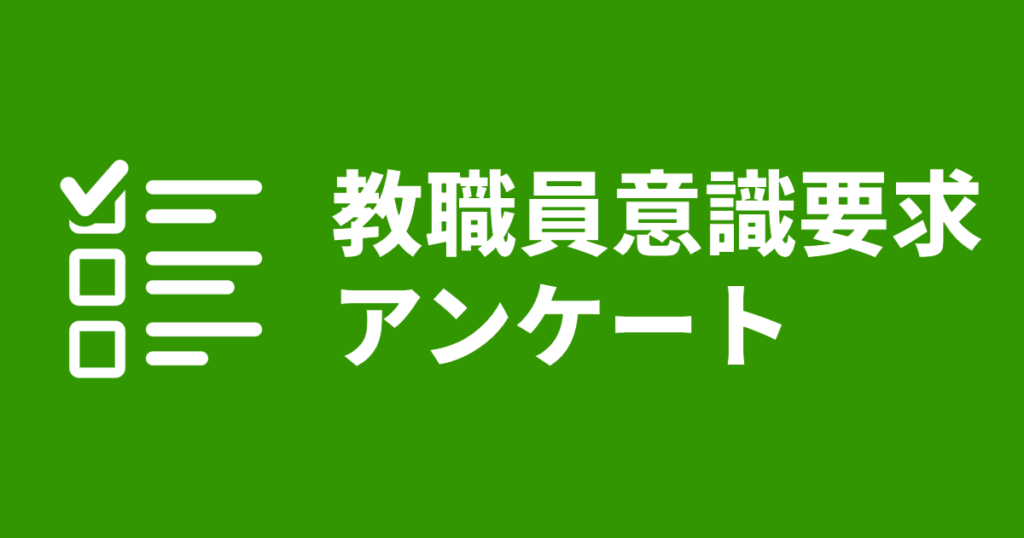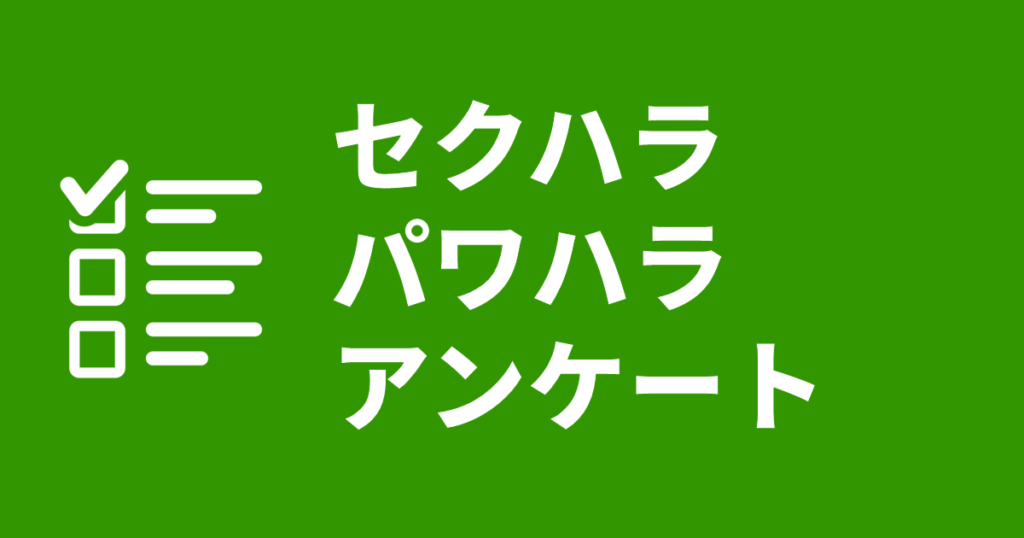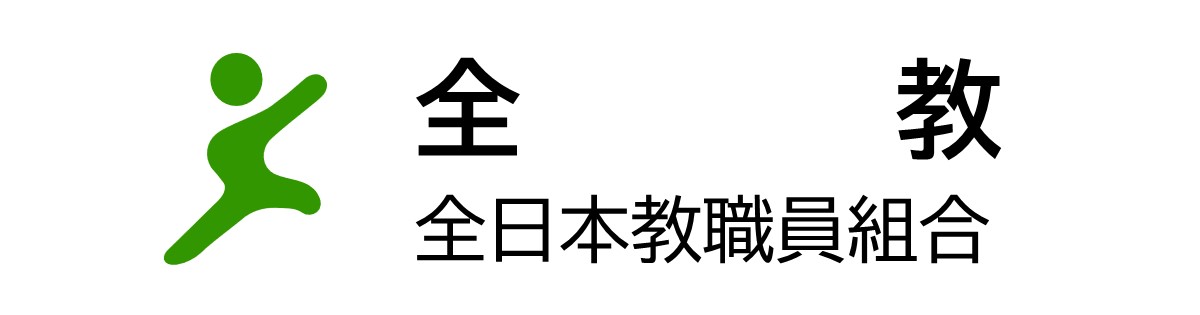全教(全日本教職員組合)・教祖共闘会議は、2025年1月9日に「教育に穴があく(教職員未配置)」実態調査結果(2024年10月)を発表しました。
資料(PDFファイル)は全教のウェブサイトからダウンロードできます。

調査の目的
- 今回の調査は5月1日時点に続く二次調査で、さらに深刻となっている教職員未配置の実態を明らかにし、改善を求める。
- 代替教職員の配置は「フルタイム」が基本だが、短時間勤務や時間講師などの非常勤等の教職員が配置される、あるいは配置せざるを得ない実態を明らかにし、改善を求める。
調査方法
全日本教職員組合・教組共闘連絡会に参加する組織を通じるなどし、各都道府県市区町村教育委員会に対して、教職員未配置の実態を明らかにすることを求めるとともに、調査用紙を組合員に配布する等して教職員未配置の実態を集約した。
(1)調査対象日
2024年10月1日
(2)調査項目
- 教職員未配置数
- 都道府県市区町村、学校種別、未配置数、未配置の職種・教科・担任の有無、校内対応等
- 子どもたちへの影響や変化、学校現場での対応の実態や教職員の様子などのアンケート
調査への回答
34都道府県・11政令市から集約した。
教職員未配置数は小学校2248人、中学校1304人、高等学校385人、小中一貫校・義務教育学校・中等教育学校59人、特別支援学校512人、校種不明231人、合計4739人となった。
34都道府県・11政令市で4700人超の未配置
※表中の「小中一貫校等」には義務教育学校・中等教育学校を含みます。
(1)未配置の状況
①校種別の欠員の内訳
| 校種 | 定員① | 中途退職② | 代替者③ | 不明④ | 加配⑤ | 短時間勤務・時間講師⑥ | 教員以外⑦ | 教職員の欠員合計(①から⑦合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 418 | 61 | 1138 | 404 | 79 | 141 | 7 | 2248 |
| 中学校 | 206 | 37 | 461 | 214 | 39 | 337 | 10 | 1304 |
| 小中一貫校等 | 13 | 0 | 19 | 0 | 3 | 24 | 0 | 59 |
| 高等学校 | 108 | 26 | 164 | 31 | 0 | 54 | 2 | 385 |
| 特別支援学校 | 132 | 21 | 277 | 59 | 6 | 11 | 6 | 512 |
| 不明 | 0 | 0 | 2 | 211 | 0 | 18 | 0 | 231 |
| 校種合計 | 877 | 145 | 2061 | 919 | 127 | 585 | 14 | 4739 |
| 校種 | 産育休 | 病休 | 看休 | その他・不明 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 499 | 380 | 19 | 240 | 1138 |
| 中学校 | 197 | 166 | 5 | 93 | 461 |
| 小中一貫校等 | 6 | 8 | 0 | 5 | 19 |
| 高等学校 | 70 | 76 | 3 | 15 | 164 |
| 特別支援学校 | 115 | 103 | 4 | 55 | 277 |
| 不明 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 校種合計 | 887 | 735 | 31 | 408 | 2061 |
②未配置に対する対応
(2)教職員未配置の特徴
- 「定数の欠員」が877人と、未配置数全体の約19%になっている。
- 途中退職者が145人にのぼり、全体の約3.1%になる。高等学校では約6.8%にあたる。
- 「代替者の欠員」が、「産育休」「病休」「看護休」「他、不明」を合わせて2061人と、全体の約44%で、「定数の欠員」を大きく上回った。
- 産育休代替の欠員が最も多く、定数の欠員、病休代替の欠員と続く。
- 未配置に対する対応として、「非常勤等で対応」が59.2%と、最も多く報告されている。
- 「教員以外」の職員についても欠員が報告されている。事務職員や特別支援学校の調理員、介助員についても報告されており、学校現場全体の人手不足が起きている。
(3)教職員未配置の実態(記述欄より抜粋)
子どもたちへの影響、変化など
不安を抱える子どもたち
- 病休が2名同時に出て、途中から担任が来ない状況は不安感を持ったと思う。長期になるにつれて「ウチの担任はどうしたんかな」と周りの教員に聞いたりしていた。(高校)
- 「うちのクラスに先生いつ来るんやろ?」と寂しそうに教頭に話してくれた子どもがいたそうです。自分のクラスだけいつも自分たちを見守ってくれる人がいない状態を放置して良いのでしょうか…(小学校)
- 休んだ先生のことを心配しすぎて、自分がやるべきことに手を付けられない生徒もいた。(高校)
- 卒業式にも担任の先生が欠席せざるを得なかった事態に対し、生徒はもちろん保護者も大変困惑していた。こんなことなら、卒業式前にビデオメッセージなども作成したのに…と悔しがる生徒もいた。(高校)
教職員を頼れず、不安定になる子どもたち
- 教務、教頭が担任業務を兼任することで、常に忙しく子どもたちは近寄りがたい雰囲気。(小学校)
- 4月から今も担任不在で、交代で教職員が対応しているために、子どもが落ち着かない。未配置が原因で新たな荒れに発展していく。(小学校)
- 教頭が元栄養教諭の方で、担任初めての方が穴を埋めるために担任に。授業がうまくいかず、学級も荒れていった。(義務制)
- 先生がどういう状況なのか生徒に説明するわけにもいかなかったので、3年の1学期の大切な時期に生徒を非常に不安にさせてしまって申し訳なかった。(高校)
- 担任が代わる代わる別の人がきて不安定(小学校)
授業への影響
- 美術の担任が10月から産休に入るが、代替が見つからない。当面、11月以降の2学期の美術の授業はカットし、9月10月の2か月間、美術の授業を倍にして対応したので、美術を授業する分、カットした他の授業もある。その授業は11月以降に設定されていて、学習の進度等が無茶苦茶になっている。(中学校)
- 当面、2学期は家庭科の授業はやらず、技術の教科を行っている。3学期に詰込み授業にならないか心配。(中学校)
- 教頭や校長まで授業を持っている状態。授業の進度もとても遅れたり、授業内容も大きく変わるので戸惑いはある。(義務制)
- どうしても自習にせざるを得ない時もあり、生徒が不満を露わにすることもあった(高校)
安全面の配慮ができない
- 生徒に目が行き届かず、トラブル(ケンカ、異食、ケガ)に対応できない。(特別支援学校)
- 未配置のクラスで子どものアレルギーに対応できず、命にかかわる事故が起きた。(特別支援学校)
- 一人あたり担当する生徒が4人から5人等になり、目が行き届かず、教室を抜け出しても分からず、「あわや」ということが2度あった。2度とも事故なくすんだが、1回目は警察沙汰にもなった。(特別支援学校)
学校現場での対応や実態、教職員の様子など
長時間過密労働がさらに悪化していく
- 担任外の教職員(教務主任や管理職など)が常に穴埋めに授業に入ることになり、本来の業務がタイムスケジュール通りに計画・準備・実施することにかなりの無理が生じている。そのため、学校全体での残業も大幅に増えている。それでも夜7時には学校の鍵が閉まるので、記録には出ない持ち帰り仕事の量が膨大な量・時間になっている。(特別支援学校)
- 途中退職された先生の代わりに、教頭先生が授業を受け持ち、さらに忙しくなって、とても大変そうだった。人が少ない分、分掌や部活など、あらゆる場面で、一人一人の負担が増えた。(中学校)
- 空き時間の教員・教務主任を総動員して業務・授業に対応して、全くゆとりのない、トイレに行くにもはばかられる状況となっている。(特別支援学校)
- 管理職も補教に入るため、様々な問題の報告や相談をする時間が、勤務時間外になる。(義務制)
- 担任がいないため通知表の入力は誰がするのか。どう評価するのか。など、担任の事務的なことを誰がするのか。管理職は、成績は病休中の担任にやらせて、入力は同期の若手教員にやらせた。(義務制)
- 担任未配置を避けるため専科や加配の教員を担任にあてる対応が多い。そのため、本来専科や少人数授業のところを担任が持つことになり、空き時間が無くなり担任の負担が増大。(義務制)
- 途中退職により、学級担任や教科担任の変更、児童生徒会や部活動の担当変更があり、さまざまな混乱を生んでいる。(義務制)
授業が「増える」負担
- 体育の教員が体調不良で不在となり、体育が出来なくなりました。学年の教員で、ダンスなどの映像でできる授業を行いました。その後、特別支援学級や体育の免許も持っている教員が授業できるように時間割が再編成されました。(中学校)
- 社会は中学全体を1人で担当しており、作問、採点がかなり大変である。三学年を担当するため、授業数もかなり増えている(中学校)
- 教員の持ち時数が増えた。(義務制)
- 非常勤講師も見つからない学校では、他の教員が授業を受け持ち、1日6時間のコマのうち6時間を受け持つ週が2日も生じ、授業準備が深夜にまで及んでいる。(高校)
- 家庭科教員がいないので、英語の教員と教頭が指導。※まだまだこんな状況が多々あると思います。ひどい状況です。子どもにとってマイナスですし、教員の負担も大きすぎます。(中学校)
疲弊し、倒れていく教職員
- 校内の担任が休みに入り、未配置対応のためそれまで専科だった教員が担任をすることになったが、急な変更で専科だった教員も休みがちになっている(小学校)
- 未配置の学校では、ドミノ式に病休者が出てくる状態。(高校)
非常勤等が配置されても、埋まらない仕事
- 非常勤が多く、部活動をもてない、生徒の引率ができない、担任がもてない。常勤の職員に負担が大きい。(高校)
- 教員の代わりに講師が入っているので、校務分掌を担当させられない。一人当たりの負担量が増している。(義務制)
慢性的な人手不足
- 県教委が報告する教員未配置だけでなく、風邪などの病欠、お子さんの発熱による特休などが重なると学校は人手不足で非常に危険な状態。(小学校)
- 未配置でなくても、人手は不足しています。働き方改革という掛け声はかかりますが、人は増えないので、全く余裕がないのにさらに工夫したり、効率UPを求められるのはきついです。手間がかかっても、子どもの育ちにとって大切な教育活動まで、過密な労働条件に耐えられずに、縮小・削減されています。(義務制)
子どもたちを取り巻く学習環境や学校生活の実際
子どもとの関係が変質していく
- 学級経営に余裕が無く、感情的に子どもにかかわる教員が増えた。(小学校)
- 子どもが先生と話をする時間が減少している。(義務制)
特別支援への影響
- 結局支援級にしわ寄せがいっています。通常級を担任していた常勤職員がいなくなる→非常勤職員しか確保できない→支援級を受け持っていた常勤職員を通常級担任にして、新しく来た非常勤職員に支援級を担当させる。こういう状態が続いているので、支援級担当の教員が何度も入れ替わります。支援級の教育水準が保てませんし、この調整を図る特別支援教育コーディネーターの負担がまた過重になります。今のところ支援級児童の保護者が受け入れてくれているから何とか学校が回っていますが、ほんとうに申し訳ない状態で、抗議を受けても仕方のない状態です。(義務制)
- 特別支援学校はTeamsティーチングという言葉に甘えて本来の配置より少なくてもスタートした。休職者も担任数にカウントしていたから。今はマンパワーで何とかギリギリ保っているが、生徒に何かあったら言い訳出来ないし、目も行き届かない。動けるし頭も良い、逆に情緒不安定で自傷や他害するなどけして目を離せない生徒が少なくない。大人の見てない場所で起こり得るので非常に危険。甘えて未配置を先送りした人事はやめて欲しい。そして、担任のシゴトと言う名の書類仕事をこれ以上増やさないでほしい。生徒の話し合いも、やることが多すぎて毎日共通理解する時間もない。しっかり人手確保して余裕のある生徒との対話、生徒の情報共有の時間を作らせて欲しい。(特別支援学校)
その他
教員に留まらない未配置の影響
- 県では、全ての小中学校と県立の特別支援学校の学校給食の無償化が始まりましたが、ある特別支援学校では、給食員の未充足(3人)により、病気等で給食員が休んだ数日ですが、学校給食の提供ができなくなり、保護者に弁当を持参させるようになっています。弁当は学校給食じゃありませんから無償化の恩恵が受けられなくなり、保護者からクレームの声が上がっているようです。
現場から、採用や定数改善に関する思い
- そもそも、欠員が出ないように県教委が責任もって正規採用すれば、こんなことにはならない。
- 定数内や産育休といった未配置となる教員が予め早い段階で出ることがわかる場合であっても、農業や工業、福祉などの少数科目や障害児学校で、代替者がいない状況。
- 未配置があることで、学校はギリギリの状況ですから、教員もその家族も病気になることがあるのに、安心して休めない状況です。未配置になってしまう学校そのものにも、教員の余裕を持って授業に臨めない業務過多や子どもの荒れの問題などがあることにも目を向けなければいけないような気がします。
- 3年間調査を続ける中で、市教委自身が困り果てている状況がよくわかるようになって来た。未配置解消は「共通の要求」になっている。
- 未配置による「教育の質の低下」について、国の責任が大きい。定数増は新政権で最も早く取り組むべき課題。
わずか5か月間で未配置は約1.38倍に
今年度5月時点の調査にも回答のあった都道府県、政令市の内、今回の調査にも回答のあった30都道府県8政令市のみを抜き出して、比較を行った。
(1)2024年5月調査結果(うち30都道府県8政令市を抜粋)
| 校種 | 定員① | 中途退職② | 代替者③ | 不明④ | 加配⑤ | 短時間勤務・時間講師⑥ | 教員以外⑦ | 教職員の欠員合計(①から⑦合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 342 | 3 | 465 | 368 | 16 | 159 | 4 | 1357 |
| 中学校 | 127 | 3 | 186 | 164 | 2 | 351 | 3 | 836 |
| 小中一貫校等 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 高等学校 | 171 | 4 | 95 | 60 | 0 | 29 | 0 | 359 |
| 特別支援学校 | 105 | 1 | 132 | 76 | 1 | 10 | 7 | 332 |
| 不明 | 0 | 0 | 31 | 11 | 14 | 0 | 0 | 56 |
| 校種合計 | 749 | 11 | 912 | 679 | 33 | 549 | 14 | 2947 |
| 校種 | 産育休 | 病休 | 看休 | その他・不明 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 234 | 140 | 2 | 109 | 465 |
| 中学校 | 95 | 48 | 1 | 42 | 186 |
| 小中一貫校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 高等学校 | 34 | 25 | 0 | 35 | 95 |
| 特別支援学校 | 52 | 46 | 6 | 28 | 132 |
| 校種不明 | 0 | 19 | 0 | 12 | 31 |
| 校種合計 | 396 | 279 | 9 | 226 | 912 |
(2)今回調査の結果(うち30都道府県8政令市を抜粋)
| 校種 | 定員 ① | 中途退職② | 代替者③ | 不明④ | 加配⑤ | 短時間勤務・時間講師⑥ | 教員以外⑦ | 教職員の欠員合計(①から⑦合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 365 | 52 | 930 | 336 | 25 | 141 | 6 | 1855 |
| 中学校 | 163 | 37 | 389 | 182 | 13 | 337 | 10 | 1131 |
| 小中一貫校等 | 10 | 0 | 17 | 0 | 3 | 24 | 0 | 54 |
| 高等学校 | 96 | 25 | 153 | 30 | 0 | 48 | 1 | 353 |
| 特別支援学校 | 123 | 21 | 230 | 55 | 6 | 11 | 6 | 452 |
| 校種不明 | 0 | 0 | 2 | 211 | 0 | 18 | 0 | 231 |
| 校種合計 | 757 | 135 | 1721 | 814 | 47 | 579 | 23 | 4076 |
| 校種 | 産育休 | 病休 | 看休 | その他・不明 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 394 | 310 | 18 | 208 | 930 |
| 中学校 | 174 | 137 | 5 | 73 | 389 |
| 小中一貫校 | 5 | 7 | 0 | 5 | 17 |
| 高等学校 | 69 | 70 | 3 | 11 | 153 |
| 特別支援学校 | 100 | 99 | 4 | 33 | 230 |
| 校種不明 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 校種合計 | 742 | 619 | 30 | 330 | 1721 |
(3)未配置に対する対応の比較(30都道府県8政令市を抜粋)
(4)比較の結果
- わずか5か月で約1.38倍もの教職員未配置が起きている。小学校で約1.37倍、中学校で約1.35倍、特別支援学校で約1.36倍になっている。高等学校については約0.98倍とほぼ横ばいになっている。
- 途中退職者による未配置が135人にのぼる。割合でも5月の約0.4%から約3.3%へと増えている。
- 未配置が起きた時の対応として、非常勤等での対応が約1.44倍に増えているが、5月の70.2%から59.2%へと11ポイント低くなり、割合は減っている。一方、「見つからないまま」が約2.30倍に増え、割合も29.2%から39.2%へと10ポイント増えている。
- 代替者全体では未配置が約1.89倍に増えている。占める割合も約30.9%から、約42.8%となった。小学校で2倍、中学校で約2.09倍に増えている。産育休代替未配置は約1.86倍へ増えており、高等学校では約2.03倍、特別支援学校で約1.92倍に増えている。病休代替未配置は約2.22倍に増えており、中学校で2.85倍、高等学校で約2.69倍に増えている。
- 5月調査よりも未配置の総数が減ったのは8自治体。小学校で減ったのは9自治体、中学校で減ったのは4自治体、高等学校で減ったのは6自治体、特別支援学校で減ったのは6自治体。その内、全ての校種で減ったのは、1自治体。
調査結果のまとめ
今年度の調査結果
- 全教・教組共闘連絡会の調査で、34都道府県11政令市で4739人の教職員未配置(教員未配置は4714人)が起きており、依然として改善されず、さらに深刻な実態が明らかになった。
- 代替者の未配置合計が10月1日時点でも2061人確認されている。まだ年度の後半を残している状態であり、教職員未配置のさらなる増加や、教職員を取り巻く環境のさらなる悪化が懸念される。
- 教職員未配置への対応として「見つからないまま」の状態は、常に未配置分の授業や仕事を校内で負担するよう強いているため、既に長時間過密労働に置かれている教職員の負担をさらに増大させるものであり、労働環境の更なる悪化が懸念される。子どもたちにとっても少人数指導や少人数学級の見送り、取りやめ、授業の詰込みや教科外の教職員による指導など、教育を受ける権利が侵害され、学校生活そのものや心的な不安などにも影響を及ぼしている。「非常勤等」で「授業の穴のみ」を埋める対応が最も多い。非常勤講師は授業のみが業務であり、生活指導や部活動など校務分掌は業務外となる。それらの負担は常勤の教職員が負うしかない。
昨年度との比較から
- 今年度5月にも回答のあった30都道府県8政令市で比較したところ、わずか5か月で未配置は約1.38倍に拡大している。産育休代替未配置が約1.86倍、病休代替未配置は約2.22倍に増えており、5月時点の未配置を埋められないまま、新しい未配置が発生している。
- 未配置が起きた時の対応として、「非常勤等での対応」が依然として最も多いが、5月よりもその割合を大きく減らし、「見つからないまま」の割合が大きく増えている。5月以降の新たな未配置に対して、新たに非常勤等を配置することが困難になっている状態が伺え、非常勤等による授業の「穴」埋めさえも難しくなっていることが推測される。教職員1人1人にかかる負担の大きさ、そして子どもたちの学習権の保障が懸念される。
- 産育休代替未配置よりも病休代替未配置の方が増える割合が大きく、いわゆる「病休ドミノ」など、教職員の心身に対して深刻な懸念が推測される。
「教育に穴があく(教職員未配置)」の改善・解決のために
教職員未配置は国が正規教員を抜本的に増員するための「定数改善計画」を策定してこなかったこと、人件費抑制のための「定数崩し」や「総額裁量制」によって、正規で配置すべき教職員が臨時的任用教員や非常勤講師に置き換えられ続けた結果、引き起こされている問題である。若手教職員の増加に伴う産育休代替の増加に教職員不足の原因を求めるのではなく、病休代替未配置の増加にも目を向けるなど、文科省、財務省は教職員の置かれている労働環境を改めて分析しなおすべきである。学校現場で常態化している過労死ラインを超える長時間過密労働、教育の自由を奪う管理・統制の強化、ハラスメントの増加等によって、教職員の早期離職があることや教員志望者が減少していることも背景にある。教職員不足による教職員の働き方は限界を超えており、子どもたちへの影響も深刻である。直ちに改善・解消が求められる。
教職員を増やし、少人数学級化を図ることで、学級事務や校務分掌など1人あたりの業務量削減こそ行うべきである。教職員が心身や時間的に余裕を持って、子どもたちとかかわり、授業や学校行事、自主的研修など行えるよう、国が責任をもって教育予算を増額して、教育条件整備を行う必要がある。
教育を取り巻く諸問題解決に向けた全教提言「このままでは学校がもたない!子どもたちの成長が保障され、せんせいがいきいきと働くことができる学校をつくる」(全教7つの提言)も踏まえ、「教育に穴があく(教職員未配置)」問題を改善・解消するよう以下求める。
(1)すぐにできる職場環境改善を行い、教職員の負担を減らすこと。
- すべての都道府県・政令市・市区町村に組合代表も含めた総括衛生委員会を、すべての職場に衛生委員会等を確立し、実効ある取り組みをすすめること。(提言5)
- 教育の専門職としてふさわしい適正な賃金水準を確保すること。(提言4)
- 各学校において行われる各種取り組みについて、教職員が納得して行えるよう、トップダウン型の学校運営から、民主的な学校運営へ切り替えること。(提言7)
- 教員1人あたりの持ち授業時数を軽減すること。そのために授業時数の点検を行い、「余剰時数1」が過剰になっている場合は速やかに2・3学期の授業時数を減らすこと。来年度の教育課程編成においても過剰な「余剰時数」の確保を行わないことを徹底すること。また、各校で取り組めるよう各教育委員会は励行、尊重すること。(提言1)
- 管理職や同僚間のあらゆるハラスメントの根絶を行うこと。各教育委員会は現場に負担を求めることなく実効ある対応をするために、ハラスメント窓口への相談内容の匿名性の確保や、ハラスメント根絶に向けて徹底的な対応を行うこと。教職員組合に寄せられたハラスメント相談に対して、解決に向けて協力して取り組むこと。
- 観点別評価を機械的に押し付けず、「通知表」の簡素化や面談への置き換えなどの取り組みについて、必要に応じて各校で行うこと。また、各校での取り組みや判断を各教育委員会は尊重すること。
- 国・教育委員会による学校現場への調査や報告書等のさらなる削減・簡素化を行うこと。
- 文部科学省は教職員の欠員に関する調査を毎年行い、その結果を公表すること。その際、2022年1月に公表した『「教師不足」に関する実態調査』で除かれた養護教諭や栄養教諭等、事務職員等、学校現場で働いている全ての職種を対象にすること。また、非常勤講師、再任用教員(短時間)をフルタイム勤務に対する勤務時間数に応じた人数(換算数)として計算しないこと。調査結果をもとに適切な教職員数が配置できるような予算要求を行うこと。
(2)中・長期的に、教職員不足を解消し、また「20人以下学級」を展望した少人数学級の段階的実現に向けて教職員を確保すること。そのための予算確保と職場環境改善、待遇改善を図ること。
- 教育予算の対GDP比をOECD諸国平均並みに引き上げること。
- 教職員にも残業代を支給し、見合った給与を支払うとともに、必要な人数の教職員を配置すること。(提言4)
- 義務・高校標準法改正による抜本的な定数改善を行うこと。(提言1)
- 「定数くずし」「総額裁量制」を見直すとともに、義務教育費国庫負担金を2分の1に戻すこと。(提言1)
- 管理的・競争的な教育施策を見直すこと。(提言3)
- 全国学力・学習状況調査の悉皆調査を中止すること。(提言3)
- 教職員評価制度見直すこと。(提言3)
- 学習指導要領を見直し、過大・過密な内容を改めるとともに、学校現場に押し付けないこと。(提言3)
- 教員が受け持つ授業時間(コマ数)の上限を定めること。(提言1)
- 定年延長に係り、高齢期雇用者の処遇を抜本的に改善すること。
- 臨時的任用教員、非常勤講師等の処遇を抜本的に改善すること。
- 余剰時数
各教科で定められている「標準授業時数」が、休校や学級閉鎖などの措置が取られても下回らないように、多めに確保された授業時数のこと。
- 定数くずし
2001年の義務標準法改正で、正規教員の代わりに短時間勤務の非常勤教員に置くことができるとしたことによる、教職員の非正規化が進んだ要因のこと。